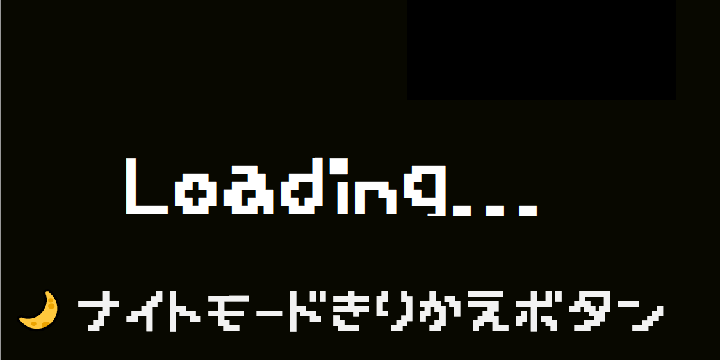エルス ストーリー「初めの一歩」
ガン! ガン! そして…ガン!
これくらいでいいだろ。
エルスは額の汗を拭きながら家を一巡りした。
村から少し離れた森にあるこの小さな小屋は、一時は家族みんなで住んでいたが、これからは完全に空き家になる。
家の扉と窓を板で隙間なく塞いだことを確かめると、さっぱりする一方で不思議と寂しい気持ちになった。
エルスは父が家を出た時を思い出した。
王国を守るため、旅に出て行った父のことをかっこいいと思って笑いながら手を振ってあげたのだろうか。
しばらくだと思った別れは4年が経ち、その次は姉だった。
二人がいなくなった後、狭くなった家を見渡しながら変だと思ったことがある。
人が減ったのなら広くなったと思うはずなのに。
どの部屋のドアを開けたって、誰もいない。自然と足を運ばなくなった。火も灯さなくなった。
闇が家を隅っこから飲み込んだ。家は同じなのに、生活圏だけがだんだんと狭くなっていった。

鬱陶しさが孤独に変わるまで、そう長くかからなかった。少年は、この家に閉じ込められているように思った。
思いで頭がいっぱいになると剣術の修練に没頭した。自分を苦しめる雑念を斬り払うように。
でも。
これからは違う。
今日は待ち焦がれていたエル捜索隊入団の最後の試験を受ける日だから。
姉もエル捜索隊から始まって、今は王国の剣士になった。
自分だって、いつか同じ道を進むつもりだ。
数日前から丁寧に家を掃除して、板で扉と窓を念入りに釘で塞いでおいたのは、
エル捜索隊になって必ず独りだけのこの家を出るという意志の表れだった。
(すぐに追いついてやるぜ。エル捜索隊がそのスタートだ)
エルスは固く決心して家を出た。持ち慣れた大剣を握りしめながら。
*
「試験は日が暮れるまでだ。それまでに戻れなかったら俺たちが探しに行く。もちろんその場合、試験は不合格だ。何か質問は?」
「本当にアレを持ってくるだけでいいのか?」
「ああ、すごい試験を期待してきたみたいだけどな」
「エル捜索隊の目的はその名の通り、エルを探すことだ。いくら強くてもエルを感じられないようならエル捜索隊にはなれない!」
「物を探すだけなら難しくないな。武器を持っていく必要もないんじゃねぇか?」
「やれやれ、剣士が剣を置いて行ってどうする? 実際はそう簡単じゃないぞ。ここにはエルの樹があるおかげで、エルエネルギー装置のような小さい力はすぐ埋もれてしまうんだ」
「再試やりたくないなら頑張れよ」
「そんなもん受けるつもりはねぇ! 一発で通過してやるぜ!」
「はいはい、迷子にはなるなよ。お前がケガでもしたら先輩に面目ないんだぞ。とにかく、時間になったら探しに行くから、覚えておけ」
「ピィィー!」
ロウのホイッスルの音と同時にエルスは森へ駆け出した。誰よりも早く入団試験を終わらせるつもりだった。
…………
ドカーン!
「くそっ、こんなこと、言ってくれなかったじゃねぇかよ!」
地面を転がりながら、エルスは何かがおかしいことに気づいた。
微かなエルの力を追って森の奥まで入った時までは問題なかった。
エルエネルギーを放つ装置もすぐに見つけた。
問題は、その装置を握っている奴がこの辺りでは見たこともないモンスターだったということだ。
「グルル…」
「おい、エル捜索隊に入団したいなら正式に申し込め!」
(くっそ、ロウはこんな奴がいるとは言わなかったぞ…これも試験の一部なのか?)
(いや、そんなわけがない。これだけ不愉快な力を持っている奴はこの森で見たことも聞いたこともねぇんだよ。どうすればいい? 戻って知らせるべきか?)
(でも…)
(……。)
(ねぇちゃんなら、敵の前から逃げたりしないはずだ)
(オレだってその覚悟でエル捜索隊に入ろうとしたんだ。このまま引き下がるわけにはいかねぇ!)
エルスは剣を握り直した。モンスターは邪魔者には目もくれず、装置を注意深く見ていた。顔を近づけ、匂いを嗅いでいるような様子だった。
(オレだって、ねぇちゃんみたいにやれる! 見せてやる!)
「はぁ…クッ。」
エルスは剣に寄りかかりながら、辛うじて起き上がった。モンスターは見た目と違って手ごわい相手だった。
疎かに見える行動の割には力が強く、動きも速くて苦戦した。
奴に殴られた脇腹がヒリヒリする。着地する時に足を滑らせたせいで、足もズキズキする。エルスは赤く染まる空を仰ぎながら、息を呑んだ。
(こうしている間にも、日は暮れてしまう。そろそろ戻らないと間に合わない…)
「おい! 何しやがる!」
バキッと音がしてモンスターが持っていた装置の外の面が壊れてしまった。
奴は戦闘中も興味を示していたが、結局壊すつもりのようだ。
(壊れたものを持って行っても合格できるのか? いや、その前にこいつを先になんとかしねぇと…!)
焦りの片隅には敗北感があった。自分は姉の足跡を辿ることすらできないのか?
いや、だとしても。
(オレがどんな覚悟でここまで来たと思ってんだよ!)
やられてたまるか。
試験は何度でも挑戦できる。だが、こいつは、今ここで倒さなければならない。
エルスがまた化け物に突っ込もうとしたその時。何かが視界に入った。それは草むらだった。
何の変哲もない、ごく普通の草むら。
草むらを見惚れたように眺めていたエルスは、茂った藪の中に手を入れ、土を少し掘った後、埋まっていた何かを取り出した。
それは古びた木の球だった。
エルスはそれを一度握りしめ、装置の破壊に夢中になっているモンスター目がけて力いっぱい投げつけた。
「カン!」
軽快な音と同時に、玉に当たったモンスターの首が玉の方を向いた。
「それも持っていけよ。探してたんだろ?」
モンスターが隙を見せた瞬間、エルスはニヤッとして剣を握り直した。そして、全力でモンスターに襲い掛かった。

*
ロウは焦りながら日が暮れるのを見ていた。
時間だ。
これ以上遅れてしまえば森はたちまち暗くなり、捜索に支障が出て受験者が森で遭難してしまう。
試験の中止を知らせるために口を開けたその瞬間、パサッと草むらをかき分ける音が聞こえた。ロウは内心にやりと笑った。
捜索隊員が出発する前だから、ギリギリ合格だ。装置さえちゃんと持ってきていれば。
安堵で胸をなでおろしていたロウは、エルスを見て慌てた。絶壁から転げ落ちたような格好をしてひょろひょろと歩く様子は明らかにおかしかった。
「その恰好はなんだ? 何かあったのか!?」
「森で初めて見たモンスターと出くわしたんだ…。奴に装置を持っていかれてさ…」
「初めて見たモンスター、だと?」
ロウはそっと眉をしかめた。試験にモンスターと戦うという内容はなかったはずだった。しかも初めて見たモンスターだと?
それでこんなケガを?
「その顔だと、やっぱりあれは試験に入ってなかったみたいだな。けど心配はいらないぜ。なんとか倒してきたからな。はい、これ」
エルスは壊れた装置と、その中に入っていたエルエネルギーが付与された小石を渡しながら、気まずそうに付け加えた。
「オレが装置を見つけた時、すでに奴が持っててさ。倒したけど…見ての通り、壊れちまった」
ロウは狼狽した。いくら試験中に予想外の出来事が起こったとしても、こんなに粉々になってしまっては…もしもこれが本物のエルだったら任務は失敗だ。これは脱落だった。
困惑しながら頭を掻いていたロウは、エルスがもう片方の手に何か握っていることに気づいた。
「それはなんだ?」
「あ、これも森で見つけたけど…昔のものみたいだし、オレの試験とは関係ないと思うぜ。でもエルの力が感じられたから、一応持ってきたんだ」
「……。」
古びた木の玉を手に取ったロウは目を疑った。それははるか昔の試験で回収しきれなかった装置で、頻繁な破損事件で最近は使われていないものだった。

装置は土に埋まっていたのか、半分以上は湿気った土で濡れていて、他の部分にも苔が生えていた。それに…。
付与されていたはずのエルの力はとっくの昔に漏れて消えてしまったようだった。
(ここから、エルの力を感じたって?)
「何してんだよ。試験は脱落なんだろ? 早く言ってくれよ」
エルスに促されたロウは悩んだ末に口を開けた。
「…上に連絡しないといけないから、結果は保留だ! 今日は隊員の寮で休んで治療してもらってこい!」
「はぁ~? 何だよそれ! この場で発表されるじゃなかったのかよ?」
「元々はそうだけど、今回は例外だ。数日かかるから、待ってろ」
「あーもう! こんなことになるなら板を釘打っておくんじゃなかったぜ!」
「…板?釘?」
「けどさ。オレは隊員の寮に行っていいのか? 合格じゃないんだろ?」
「今日は見学ってことにしておいてやる」
ぼやっとしているエルスを他の隊員に任せて、ロウは再び古びた玉を見つめた。
集中しても自分にはエルエネルギーが感じられなかった。
五、六年前につくられたものだし、感じられないのが当然だ。それに、その頃のエルスはとても幼かったから、これが試験に使われた物だと知っていたはずもない…。
(エルを探すことに限っては、姉以上の才能を持っているかも、な)
ロウは玉を弄りながら伝書鳩がいる場所へ足を運んだ。
*
数日後。
エルスは正式にエル捜索隊になった。
「俺もエル捜索隊になって長いが、お前みたいにベッドで任命状をもらうやつは初めてだ」
ロウがからかうと、エルスは拗ねた顔でブツブツ言った。
「うるせぇな。オレもカッコ悪くて嫌なんだよ」
エルスは試験の日の戦闘で足首にヒビが入って寝込んでいた。口ではそう言いながらも、胸はいっぱいだった。
しばらく任命状を見ながら、思った。
(やっと…ねぇちゃんに一歩、近づいたぜ。)
「なあ、お前はどうしてそんなに目標に対して一生懸命なんだ?」
「バカなこと聞くなぁー…ロウはいつになったら大人っぽくなるんだろうな?」
「なんだと!?」
「目標は全ての剣士が持つものだろ? オレの目標はねぇちゃんだぜ。ねぇちゃんみたいに強くなって、ねぇちゃんと一緒にエルを守る!」
「エル? そりゃあ、そのためのエル捜索隊だが…普通は『世界を守る』とか、そんな風に言うもんじゃないか?」
「エルがなければエリオスもないだろ? だから、エルを守るんだぜ!」
「まぁ…そうだな」
(エルをここまで想う新米は初めてだな。感知能力が優れているからなのか?)
「あ、そうだ。今日からエル捜索隊になったんだよな? 訓練はいつから始まるんだ? オレの隊服は?」
「隊服は今日から支給するが、足首が完全に治るまでは訓練に来るなよ。来たら追い出してやるからな。分かったか?」
「ほら、これがお前の隊服だ」
「おい、どうしてオレだけ半ズボンなんだ! オレも長ズボン穿きたいんだよ!」
「エル捜索隊にお前みたいなチビが入るのは滅多にないことでな。お前のサイズがないんだ。それだって、直した物なんだぞ」
「長いのが着たけりゃ、とりあえず大きくなれ!」
「オレがチビでいる時間はそう長くないぜ? ロウより背も高くなって、立派な剣士になって、ねぇちゃんと並んで立ってやる!」
イヴ ストーリー「独り目覚めた女王」
知らない人間達としばらく同行していたイヴはポンゴ族たちの村に向かう道で足を止めた。
「うん?イヴ、どうしたんだ?」
「…ボクは…行かない」
赤い髪の子は不思議そうな顔をしてイヴを見た。他の3人もそれぞれ疑問の顔でイヴを見ていた。
「ふむ…」
人間の魔法使いはイヴと出会った瞬間からどこか不満げに見えた。ただ、口数が多いだけかもしれないけれど……。
何れにせよ、歓迎しているようには見えなかった。
「でも、一緒に行った方がいいと思うけど…他に行きたいところでもあるの?」
エルフは一応優しく好意的に見えたが、イヴは判断を留保した。
データを基盤として判断すると、エルフが人間たちと一緒にいる理由から疑問だったからだ。
「……。」
そして…一番気にかかる人間。
イヴは憎悪に満ちた目で自分を睨んでいる男のナソードハンドからあえて顔を背けた。
やっぱり彼らに同行するのは無理だ。そう決めたイヴは彼女の提案を断るために慎重に言葉を選んだ。
「…ボクが眠っていた間に起こったことを確認したい。だから、キミの提案は遠慮する。それに…」
”コアを壊した人間とは一緒にいられない。”
イヴは同行していた短い間、何度も心の中で繰り返したその言葉を飲み込んで、沈黙で話を終えた。
「あ…そう? そうなんだ…。じゃあ、用事が終わったら来てくれ!」
「え…? でも、ボクは…」
「大丈夫さ! オレたちはルーベン村に戻るから、そこに来て、な?」
「……」
イヴはポンゴ族の村に行く人間たちを苦々しく見つめながら考えた。
婉曲した拒絶表現だったのに…。気づかなかったのか、それとも…本気で提案したのか…。
「本当に、困ったね。コアをあんな風にしたくせに友達だなんて…」
「……。」
「…心配してくれるの? 大丈夫。ボクがあの村に行くと住民たちに警戒されてしまう。それと…起きたばかりだから、色々調べないといけないことがいっぱいだから。」
「さあ、一緒にアダムの足跡を辿ってみようか?」
*
イヴはポンゴ族の村から少し離れた場所、浮遊島アルテラの隅っこに着陸した飛空艇の信号を探知してそこに向かった。
「…ブラッククロウ号。ナソード軍団のエネルギー源になるエルの欠片と魔法石を調達するためにアダムが運用した飛空艇…」
「この飛空艇がいつから使われたのかが分かれば、アダムの活動時期を特定できる」
「Σ(゚ □゚ )」
「どうしたの? レビ?」
レビの視線を辿って行くと、壁に寄りかかって座っている人間たちがいた。イヴは一瞬ひやりとしたが、彼らが動けないことに気づいて警戒を解いた。
「これは…ナソードに改造された人間…。アダムが消えて命令がなかったから機能が停止したみたいだね」
「…失礼。モビ、レビ? コードを調査したい。手伝って」
「<(’∀’)」「<(’∀’)」
イヴはブラッククロウ団員の体に移植されたコードを調査した。
記録を辿って行くと、コードの基盤になる『ナソード改造兵』がデータベースに残っているのを発見した。
記録を調べていたイヴは驚いた。ナソード改造兵はエリアン王国時代、ナソード戦争の時から存在した概念だった。人間族の対ナソード兵器…イヴは急いで記録を読み続けた。
「これは…信じられない。人間たちがナソードと戦うために自らナソード技術を体に使ったなんて…人間たちはナソードを増んでいたのではなかったの?」」
「…アダムは…アダムはどうしてこんなものを再び作ったんだろう…」
アダムは人間を機械に改造する興味があったようだ。アダム自身も改造兵を作って運用していた。
しかし、単純に利用するだけではなかったようだった。
「ボクを敵対視するレイヴンという男…アダムは彼の精神に接近するだけじゃなくて、感情まで制御しようとした。なぜ?」
(アダム…キミにとって人間はどんな存在だったの?)
心の中で問いかけてみても分からなかった。
(ボクにとって人間はどんな存在?)
憎悪に満ちた目で自分を睨んでいたレイヴンが再び思い浮かんだ。同族の腕を持っている人間の男…。
イヴの目には、その腕は狩りに成功した猟師が獲物から取った戦利品のように見えた。
それが…アダムによる望まない改造だったなんて…。
(人間たちにとってボクはどんな存在なんだろう…)
「……」
モビとレビが心配するようにイヴの足元で騒いだ。
考え込んでいたイヴは彼らを安心させるようにそっと微笑みながら声をかけた。
「ここでの用事は終わったよ。アダムがいないから飛空艇も、改造兵たちもこれ以上問題を起こすことはない。」
「行こう。ここに留まる理由はない。」
イヴはギアたちと一緒に黒い飛空艇を去った。
沈む日が飛空艇のデッキの上を暖かい光で照らしていた。
*
しばらく歩いていると、地平線の向こうから果てしなく広がっているような枯れ果てた荒地が現れた。眠った同族たちがそこにいた。
お互い絡まりあったまま停止したナソード達の上に沈む夕日が差し込んで、デコボコの影を描いた。
ナソードではない他の種族が彼らを見たら、ただの岩だと思ってそのまま歩き去るかもしれない。
しかし、消えた同族たちが残した信号を読めるイヴは通り過ぎることができなかった。

(残念なこと…ボクの同族たちよ…安らかに眠って)
込みあげる悲しみを感じながら、イヴは同族たちが発する信号とコードを読み込んだ。
「…ほとんどが土木建築のために作られたナソードだね。」
アダムが最初から戦争を準備したようには見えなかった。
おそらく、アルテラを中心としてナソード種族を再建しようとしたのだろう。アダムが試みた無数の実験痕跡が今は停止された同族たちに残っていた。
しかし、ある時期からほとんどのナソードたちに戦闘コードが入力された。
(魔族…確かにそれを警戒しているとアダムが言った。)
アダムは間違いなくある危険要素を発見したはずだ。しかし、必要以上に急いでいたとイヴは思った。彼があれほどに警戒していた魔界と魔族とは一体何なのだろう?
「Σ(゚ ▮゚ )」
「うん、モビ。僅かに…信号が残っている」
「危険、守らないといけない… 何から?」
眠っている同族から答えは戻ってこなかった。
イヴはナソードの素体に付いた胞子を手で払い落としてから手を離した。
これ以上自分にできることはなかった。
しばらく平原を見渡したイヴはそっと目礼をして平原を離れた。
夕日に向かって歩くイヴの後ろに影が未練のように長く伸びた。
*
「!!!」
「うっ、ここは…。」
イヴはアルテラシアに覆われたトンネルの中を見て唖然とした。見ているだけで気分が悪くなる寄生花の胞子が壁や機械装置、そして壊れたナソードたちに付いていた。
「これは確か…ナソード戦争当時に人間達がばら撒いたアルテラシア…思い出した。同族が眠っていた冬眠装置の近くにもあった。」
「島に残っていることは分かっていたけど、これだけ増殖していたとは…」
「(;`Д´) (0ω0;)」
「(;0ω0) (0ω0;)」
「大丈夫。心配しないで。誰かが整理したみたいね。その道で行けば大丈夫」
「それに、ボクは胞子にある程度免疫があるから」
不足なエルエネルギーと質の悪い素材で急いで作られたアダムのナソードたちはやられるしかなかったはずだ。
(守らないといけない…この話だったの?)
イヴは平原のナソードたちを思い出した。自分たちの体で巨大な防壁を作った同族たち…彼らの体に付いていた粉のような胞子…。
他の同族たちがこれ以上被害を受けないように体で胞子と立ち向かうことが彼らの最善だったのだろう。
「戦争は終わったのに…キミたちはまだ戦っていたんだね」
「……」
「モビ、レビ。少し危険かもしれないけど…アルテラシアを排除しながら進もう」
「同族たちが安息できるように…したい」
「(*´∀`)(*´∀`)」
イヴは残ったアルテラシアを処理した後、逃げるようにそこから離れた。訳の分からない辛い気持ちが回路を侵食して堪えられなかった。
*
運送トンネルを通じてナソード生産基地に辿り着いた。
ここはブラッククロウ号と違ってアルテラシアと繋がっているため、まだ残っている少しの動力で工場の一部がまだ稼働中だった。
生産基地内部をしばらく歩いたイヴは天井に設置されているレールに沿って一体のナソードが制作される工程をポカンと眺めていた。
カチッ、カチッと規則的な動きで素体が組み立てられた。
しかし、次の工程を処理する機械は鋭い何かに大きく斬られていて作動しなかった。素体はそのまま地面に落ちた。
既に何体ものナソードが地面に落ちていた。次々とナソードが組み立てられては、また落ちた。

「これは…こんなのは…」
ドスン。
ドスン。
ドスン。
素体が落ちるたびに、イヴの心にも何かがドスンドスンと落ちる感じだった。
イヴは急いで生産中のナソードのコードを分析した。
殺傷力を強化するため改造を重ねてさらに単純になったコード…イヴは自分の目を疑った。
ここで作っているものは、ナソードとはとても呼べないものだった。
自我が存在しない、ただ入力された命令を遂行するだけの機械にすぎなかった。
「ボクはこんなものを望んでなかった! アダム! どうしてこんなことをしたの!」
「これはナソードじゃない…キミも知っていたはずだよ…なのに、どうして…」
カチッ、カチッ、…ドスン。
果てしなく繰り返される機械の音、素体が落ちる音。
イヴは膝を抱えて座り込んだまましばらく動かなかった。
「…」
「……」
ギアたちはイヴの足元でおとなしく待ちながらトントンと触れたりした。イヴは膝に顔をうずめたままピクリともしなかった。
ギアたちはすぐ落ち込んでしまった。
イヴにはこの状況を受け入れる時間が必要だった。
しかし、その事情がわからないギアたちは主人に何か異常があると判断するしかなかった。モビとレビは恐る恐る信号を交換した。
どれぐらいの時間が経ったのだろう。
やっと落ち着いたイヴが顔を上げると、モビとレビが忙しそうに生産基地の壁の回路で何かをしていた。
「…レビ? モビ? 何をしているの?」
「(;0ω0)(0ω0;)」
「エルエネルギー…この基地から動力を持ってきてくれたの?」
「心配させてしまったね。ボクの動力は十分…動力が足りなくてあんな風にしていたわけじゃないから安心して」
(レビ)「ε=(´∇`;)」
「…実は分かっていた。アダムも好きでこんなことをしたんじゃない…」
「ここにアーカイブされたコードたち…アダムがいろいろな試行錯誤を行った痕跡が残っている」
「より効率的で、より丈夫で、より強い…どんな環境と地形でも戦闘を遂行できるデータをビルドした痕跡が…」
「アダムには気の毒なことだけど…赤い髪の子と人間たちが適時にアダムを止めてくれなかったらまたナソードによって戦争が起きたはず…それはいけない」
「でも…どうすればいい…? ナソードが他の種族と戦わずに共生できる方法…ボク一人で探せるのかな…」
「q(・o・̌) q(・o・̌)」
「…ふふ、そうだね。一人じゃない。ボクにはキミたちがいるから」
軽く手を上げたら、レビがイヴの懐に飛び込んだ。イヴはそばにいたモビも引き寄せて何度か撫でてあげた後にギアたちが開けてくれた壁の回路を確認した。
「これで基地の動力を除去すればいい。モビ、レビ。見つけてくれてありがとう」
「繋がれたところがいくつかありそう。探してみよう」
「(*´∀`)(*´∀`)」
回路を遮断したイヴはエレベータ―に向かった。
ドスン。
イヴが去った後に最後の素体が地面に落ちた。
そして、工場の内部に沈黙だけが漂った。
*
「俺の…を利用…作った…ナソー…だな」
「!!」
識別コードクロウライダーをイヴが発見した時には、既に致命的な損傷を受けた後だった。
今は作動しているが、もうすぐ停止するだろう。
「無感情…慈悲の無い…俺はこんな化け物だったのか」
「…あの男を真似して作ったのね」
「……」
イヴはアドリアンが自分に言ったことをふと思い出した。
自分は人間の感情を理解して、ナソードと人間を繋ぐ…ナソードの女王になる存在。
しかし、アダムはそうではなかった。
自分の目の前にあるのは特定の人間を真似して作った機械。アダムがレイヴンの意識と感情に介入した理由は…。
それが、アダムが人間を理解しようとする努力の一部であった可能性について、少し考えてみた。自分はアダムではないから結局は分かるはずのないことだ。
「…ごめん。キミは化け物じゃない」
イヴはクロウライダーの隣に座って、そっと頭を支えた。
「ボクたちは生まれた時から目的が付与される機械。それが他の生き物と違うボクたちだけの存在方式」
「コアを設定して眠った時…こんな結果を望んではいなかった。でも、そんな言い訳をしてボクが背負わないといけない責任から逃げてはいけない。分かっている」
マスクの中で光が微かに点滅した。
「キミにそんな生き方を付与して悪かった。安らかな眠りを…」
「……」
「…過ぎ…こと…後悔しても…ない。でも…」
「未来は…違う。…いくらでも変え…れる」

やがて、マスクの中の光が完全に消えて、クロウライダーは沈黙した。
「そう、信じているの?」
「未来を…変えられる? ボクが…」
クロウライダーの頭を地面に下ろしながらイヴは苦く笑った。
今日はなんだか、答えを聞けない質問ばかりしてしまったね。
完全に停止したのを確認したが、イヴはその隣でしばらく座っていた。
理由は分からなかったが、そうしたかった。
もし、ナソードではない他の誰かがいたなら、その行為を『哀悼』と呼ぶのだと教えてくれたのかもしれない。
ギアたちも今度は静かにイヴの側にいてくれた。
*
「結局、また最初に戻ってきた。ボクと同族たちが眠っていた保存装置があるここに…」
イヴはアルテラコアの深いところにある洞窟に入った。すぐ、イヴも知っているよく馴染んだ風景が広がった。
「これ以上確認できるものはないと思うけど…確認してみる?」
イヴの提案にモビとレビが道を照らしながら先頭に立った。
イヴはゆっくりと後をついて歩きながら内部を見渡した。
永い眠りから起きたばかりだったあの時は、赤い髪の少年がすべてを台無しにしたと怒った。コアが壊れたから何もかも終わってしまったと…そう思っていた。
しかし、イヴと一緒に保存装置に入っていた同族たちは既に機能を喪失したか、洞窟の鍾乳石が落ちて大きいダメージを受けたか、アルテラシア胞子にやられて手を打つこともできない状態だった。
おそらく、彼らが目覚めることはないだろう。相変わらず自分は独りぼっちだった。でも…
イヴは誘われた。
ある人間から、友達になってくれるという…


洞窟を歩き回ったイヴは感傷的な理由で、そして念の為に…
こんな悪条件の中で起きるかもしれない同族のために自分の記憶の一部を残してアルテラ村に向かった。
…………。
ポンゴ族の村に入ったイヴは忙しい活気を感じながら周りを見た。
あらゆる機械装置とゼンマイが回っていて、大きい排管から時折熱気がビュウッと噴きだした。
村というより、古い機械装置の内部に入ったような風景だった。
アダムの作った施設に比べるととても古く、
秩序の無い姿だったがイヴはその中で安らぎを感じた。
「変…ここに来たこともないし、ボクが憶えている都市や村とかも全然似てないのに…見慣れないけど慣れ親しんだ感じがする」
「そういえば、人間の言葉にこんな表現があったね。人間味溢れるという…こんな感じかな?」
「…うん? どういう意味ポン?」
あるポンゴ族がいつの間にかイヴの隣に来ていた。イヴは驚いたが、すまない顔でそっと微笑みながら答えた。
「ごめん。ここの風景に見惚れて、居たのに気づかなかった。それより…暖かい場所だね。」
「そうポン…? ナソードにそう言われたらなんか不思議な感じだポン。古代のナソードだからかポン?」
「ところで、村には何の用ポン? 話があると聞いたポン」
「うん。アダムが作った施設を確認して、動力を除去してきた。もうキミたちは安全だよ」
「ありがポン! これで島をもっと自由に行き来するようになったポン!」
「あの…キミたちはこの島から出ないの? もうアダムはいないから島を脱出できるようになったのに」
「エル捜索隊と同じことを聞くんだポン。いいよ。なんだかんだ言ってもここはミーたちの故郷だポン」
「いつかはここを去るかもしれないけど、それは今じゃないポン!」
「そう? あ…村から少し離れた場所にブラッククロウ号がある。改造兵がまだ残っているけど、皆を攻撃することはない」
「ボク一人では無理だったから確認だけしたけど…キミたちに後のことを頼んでもいい?」
「飛空艇はキミたちが自由に使っていい。島を出る時に使ってくれればあの船も喜ぶと思う」
「そう? 色々ありがとうポン」
「改造兵たちははミーたちに任せるポン! レイヴンみたいに元には戻れないかもしれないけど、新しい人生が始まると彼らにもいいことだろうポン」
「ごめん。ボクがキミたちに迷惑をかけた上にいろいろ苦労させて…」
「ボクは…ここを去るよ。今までお世話になった」
「仲間たちに会いに行くつもりポン?」
「仲間…そうだね。これでお別れの挨拶も終わったし、そろそろ会いに行かないと」
「ありがとう。さよなら」
アイシャ ストーリー「魔力を失った少女」
「うちのキャンプがちょうどこの辺にあってよかったね。まかり間違えば大変なことになったはずよ! どうしてあの森に行ったの? モンスターが出る所だって知ってたでしょ?」
一人で冒険している途中、レンダールの人にモンスターに追われているのを助けられた。
感謝しているけど、恥ずかしいところを見せてしまって辛かった。
でも、ちゃんとお礼は言わなきゃ。
しっかりするのよ、アイシャ! 気にしない! 落ち着け!
別に飲みたいわけじゃなかったけど、平気を装うためにアイシャはお茶を一口含んだ。
しかし、それは間違いだった。
アイシャは口の中と食道まで火傷を負ってしまいそうになった。
涙をにじませながらも、アイシャは必死にお茶をコクリと飲んで答えた。
「……霊薬の材料を取りに行きました」
「霊薬? それはどうして?」
うっ、やっぱり質問するよね。
アイシャは適当に言おうか少し迷ったけど、素直に話すことにした。
「……魔力を……なんとか増やしたくて……」
一瞬、水を打ったようになったが、すぐ皆はワハハと笑いはじめた。
「あんな素人魔法使いがするようなミスをしちゃったの? アイシャが?」
「何がおかしいの? 素人の時はよくあるじゃない~魔力を増やそうとしていろいろ試して痛い目に合う経験がね」
「アイシャは小さい頃から魔力に恵まれてこんなことはしなかったけど、魔力が足りなくなったらやっぱり同じことをするんだね」
(うう、このアイシャ様が他人と同じ扱いをされるなんて、屈辱だわ)
「小さい頃から魔力に恵まれていたって? 今も幼い子に見えますけど」
茶色の髪をした人が聞いた。
「君はここに来て間もないから知らないのね? アイシャは本当にすごかったのよ。五才の時だったかしら? 火の魔法をクエンバラン様の肩越しに覚えた子なのよ」
「五才で火の魔法を独学で? すごいですね!」
「その時、私もそこにいたんだけどね。『すごいけど火の魔法はとても危ないから使っちゃダメ』って言ってあげたんだけど、アイシャの答えがすごかったの」
ああーっ! そんなことまで言わないでよっ!
アイシャは心の中で悲鳴を上げた。
いつの話よ! 私はもう十四才なんですけど!
「『じゃあ、空に投げれば問題ないでしょ?』って言いながら空に向かって魔法で火を放ったのよ! 真昼の空にこんな大きな彗星が落ちて……見事な景色だったよ」
そしてまたワハハハ!と笑い声。
悪意はないと分かっているけど、気分が沈んでしまうのは仕方ないことだった。
アイシャは本当にすごかったのよ……って。
(すごかった!? 過去形で言わないでよ! 私は今もめちゃくちゃすごい天才魔法使いなんだから!)
親戚たちと出会ったときから予想していたことだったけど、プライドを傷つけられた。
アイシャは感情を出さないように気をつけながら、自分の状態を伝えて助言を貰おうとした。
その時……
「マジでー? じゃあ、アイシャの時代ももう終わったってこと?」
うっ! 喧嘩売ってるの!?
必死に平静を装っていたアイシャの眉間がしわくちゃになった。
「マティィィ!! 私の前でもう一度言ってみなさい!」
「ははは、なんだよ、その反応。本当に魔法が使えないんだ。まぁ、僕の計画よりは少し早いけど、天才魔法使いの名は僕が受け継いでやるよ!」
(ドッカーン!)
「うああっ!」
「あんたくらいは豆粒ほどの魔力でもやっつけられるの! このガキが!」
「ぐぐぐ……! フン! 今に見てろよ。僕には奥の手があるんだよ! レンダールじゃなくても天才魔法使いになれるってこと、僕が証明してやる!」
「笑わせるね! やれるならやってみなさい」
「フンだ! べーっ!」
アイシャが再び魔法を使うために手を上げると、マティは素早く外に逃げてしまった。
アイシャは怒りで拳を握り締めた。
「マティ……あの子ってリンダーさんの弟子だったっけ? どこから来た子?」
「よく覚えてないね。漁師の息子だけど、魔法に才能があって連れてきたらしいよ」
「レンダールの下で学ぶ者は全部レンダールなのに。レンダールじゃないなんて、変なの。 ははは」
「でも、徹夜して勉強するくらい根性ある子だよ。最近すごく実力を上げたのよ。もしかしたら本当にアイシャの次の天才魔法使いになるかもよ。ほほほ!」
「フン! なれるもんですか!」
アイシャは拗ねた顔で呟いた。私があんなガキに牽制されるほど堕落したなんて……本当にどムカつく!
うう……もういい!
こんなこと考えるのは辞めよう。アイシャは話を逸らした。
「ミミルの指輪を奪って行った奴らをすぐに追いかけようとしたけど、痕跡も残さずに消えたんです。奴を探すこととは別に、このままじゃ不便だから霊薬を使ってでも今より魔力を増やしたいのが正直な気持ちです!」
「そんなことは止めて、これからは節約して魔法を使ったらどうだい?」
「はあ? そんなんじゃ面倒くさいです!」
「でもほら、それが普通の魔法使いなのよ。君が魔力の量に恵まれた特殊体質だったのよ。特権だったの。お祖父ちゃんに言われなかった? 優れた魔法使いは節制するものだって」
「ふむ……。でも、本当に優れた魔法使いはそもそも節制する必要もないかもしれません」
アイシャは不満げに口を尖らせた。
「一応……おっしゃることは分かりました。今は節制しないといけない状況だし。やってみますね。まぁ……」
「難しいことでもないし」
*
キャンプが泊まっている村の近くにある食堂。飲み物を注文して席に座ったアイシャは熱心に何かを書いていたが、いきなり頭を抱えた。
頭が痛くなった。
さっきは節約くらい、難しくないと堂々と言い張ったけど、問題はそれだけではなかった。
魔力の量が減って使えなくなった魔法があったのだ。
先ほど森でモンスターに追われたのも、よく使っていた火炎魔法を制御しきれなくて、変な方向に発射してしまったせいで先制攻撃のチャンスを逃してしまったからだ。
(そう言えば……あの火、山火事にならなくてよかったね)
「ふぅ……とにかく、強い魔力が必要な魔法はしばらく使えなさそうね」
使える魔法と使えない魔法を書き出してみたアイシャは、使えなくなった魔法のリストが果てしなく長くなるのを見ながらため息をついた。
ただただ胸が重苦しかった。
もちろん、方法が全くないというわけではない。多くの魔法使いたちが魔法の補助手段としていろんなものを利用している。
投擲用水晶玉とか、ポーション、薬草、火打ち石、縄、宝石、エンチャントされた服や道具……。
数えきれないほどに。歩く雑貨屋のレベルに。
そんなものは絶対安くないし、魔法使いたちは貧乏の恰好をした金持ちと言われている。
アイシャは生まれ持った魔力の量のおかげでこのような補助手段を使わなくていい立場だったから、とても惜しいと思った。
今になって”普通の魔法使い”と同じ立場になったのだ。
人前で文句を言っている場合ではなかった。
(これで、スタッフと簡単な所持品だけを持ってふらりと旅に出られる生活とはさよならなのかな?)
アイシャはキャンプと一緒に流浪する自分の姿を想像してみた。
たくさんの魔法補助材料を乗せた大きな荷車が揃って列をつくって移動する。
手頃な場所を見つければそこにテントを張り、時期が来ればまた旅に出る。
消耗品を管理して、消費期限が過ぎた薬草やポーションは廃棄。
廃棄したものと場所、日付を記録してレンダール本家に送ることも必要だ。
それだけではない。補助材料を購入する時もレンダールの資金を使うことになるから、まずは予算案を作成してレンダール家に送って審査を受けないといけない。
今までは一人で旅をしていたから金が必要になれば依頼を受けて賄えたのに、それもできなくなる。依頼を受ける時は事由書の作成が必要だ。
破損や事故などで材料が壊れた時も同じだ。事由書と予算案をまた作成して本家に送って……審査を待って……却下されたらまた書類を作成して……。
不自由な生活を想像するだけで息苦しくなったアイシャはテーブルに額を突きながら絶叫した。
「ムリだー!!! こんな生き方、私には絶対無理だよ!!」
翼を折られた鳥の気持ちってこんなものなのかな?
ああ、何て可哀想な私の人生!
アイシャは悔しさにもがき苦しみながらテーブルに額を擦った。
「あの指輪のせいで、アイツのせいで!!」
テーブルにうつ伏せになってブツブツ言っているアイシャの隣でガラガラと椅子を引く音がして、誰かが座った。
「あのさ、お嬢ちゃん? 君も魔法使いかい? この村の近くにレンダールのキャンプが来てると聞いていたけど、どうやら本当だったらしいな」
アイシャは怪しいほど親しみやすく接してくる男を見ながら目を細めた。こんな奴は大体二つの部類だよね。商人か詐欺師か。それとも、両方だったりして。
男はアイシャの視線を「言いたいことがあるならさっさと言えよ」と言っているように感じたのか舌を一回鳴らして本題に入った。
「魔法使いたちにいいものがあるんだけど、どうだい?」
アイシャは心の中で舌打ちをした。やっぱりそうきたね。
魔法使いはお金持ちだから!
アイシャは書いていた紙をわざと荒っぽく巻きながら荷物を片付けた。
「いらないよ。歳も大したことなさそうなのに何よその言い方?」
「セッカチなお嬢ちゃんだなぁ。一応話を聞いてくれ! 本当にいいものがあるんだってば~」
「結構です! こうやって密かに売りつけてくるなんて、怪しいものに間違いないよ。そんなものは後のことが心配よ」
「怪しいものだったらこんな昼間に話を聞かれるこんな店に来て売ると思うのかい? いいよ、お嬢ちゃん。無礼に近づいてきたのは謝るから」
親しく接近する戦略はダメだと思ったのか、男は椅子に正しく座り直して丁寧な様子で本格的に事情を説明し始めた。
「実は俺、商人じゃなくて冒険者なんだ。よりによってこの村に来る前に荷物を失ってしまったんだ。ったく。森を歩いているのにいきなり空から火の球が落ちて――」
「ブーッ!」
飲み物をさっさと飲み干して食堂を出るつもりだったアイシャは噴き出した。
森に火の球? もしかして、私の火の魔法…?
「な? あっけない話だろ? やられた本人はどれだけあっけないと思う? 俺が穏やかな森を歩いてこの村に向かっていたのに……いきなりドカーン!って音と一緒に背中に何かがピカッと!打ち刺されてさ。最初はてっきり落雷かと思ったぞ? 青天の霹靂、まさにその通り! 荷物は燃えているし、火はますます大きくなるし、仕方ないから全部出して火を消したんだ」
アイシャはむせて辛いふりをしながら手で顔を隠した。
男は今がチャンスだと思ったのか、早口でまくし立てた。
「で、完全に貧乏になったわけだ。何でも売って度に必要な金を稼がなきゃならないんだ。
ね? お願いだから、これ一つだけ見てちょうだい。俺がああしていなかったら、お嬢ちゃんもここでこうして飯を食うことは出来なかったぞ?」
「ゲホッ! わ、私の食事は関係ないでしょ」
「俺が火を消さなかったら、この村の人全員が稼業を止めて火を消しに行くほどの大火事になったはずだからな! こう見えて、俺はお嬢ちゃんの食事を確保してあげた恩人だぜ?」
「何が恩人よ、代わりにお勘定してくれないくせに……」

不愛想に言ったつもりだったが、アイシャの態度が大分柔らかくなったのを感じたのか男は露骨にかわいそうな表情をした。
「うう、分かったからその表情止めて欲しいです! 話だけは聞いてあげますね」
男は絶対後悔しないとかなんとか言いながら急いでカバンの中をごそごそ探した。カバンの隅っこの煤を見ると、嘘ではない……みたいだ。
あーあ、胃が痛い。
「俺が売りたいのは情報だ。魔法使いなら絶対興味があるものだ。魔力を一気に爆上げしてくれるとんでもないポーションの製造法だからな!」
「ええー?」
よりによって、こんな時に? 今一番必要なものを?
アイシャは目を丸くした。怪しいよ! ありえない!
そんなもんがあったならとっくに噂になったはずよ!
アイシャは彼の話にケチをつけようとしたが、マティの顔が頭に思い浮かんだ。自分に奥の手があると言ったこと、実力があがったと評価されていること……。
(正直、本当にバカみたいなことだと、ちゃーんと分かっているのに、めちゃくちゃ分かってるのに)
「こほん、あの、爆上げって……どのくらい?」
アイシャは試してみることにした。
*
アイシャは少なくない代金を払った後に製造法の内容に素早く目を通した。
「お嬢ちゃん、いい選択をしたぞ。他の所では絶対に手に入らない、この地域の知る人ぞ知る伝説の製造法だからな! 燃えた荷物の中でこれが残ってるのを見て本当に嬉しかったんだ。運が良かったぜ。これを手に入れたのは天運だぞ?」
冒険者がアイシャの隣で甘言を弄し続けた。一見余裕のある態度のように見えるが、気が変わることを恐れている様子だった。
(まぁ……この人の荷物を全部燃やしたのは私だから、わら屑を売ってでも買うつもりだったけど……)
普段ならきっと駆け引きをするはずだが、今回は冒険者が要求した金額をほぼそのまま(値切りはしたが)支払った。
(言わば罪代……だよね)
黒く燃えた冒険者のカバンをそっと見た後、アイシャは再び製造法の詳しい内容を一つ一つ確認した。
(使用するのは……一般的な魔力強化剤の素材として使われるものだね。製造法もほぼ同じだし、薬草の手入れ方法も詳しく書かれている)
アイシャは詐欺が目的で書いたものではないと結論を出した。
材料を扱う方法とか、使っている用語などから見て、相当な魔法知識を持つ人間が書いたようだ。
(それ以外は……地域特産品が何種類か入るのが珍しいところだけど、この地域だけの製造法だったよね? なら、ありえる。特産品もすぐ手に入るものだから問題ないし……あれ? なかなかそれっぽいじゃん。これ、本物だったりする?)
アイシャの目が丸くなった。
珍しいことだが、一部の地域や種族の魔法で、効果は優れているが正式に登録した魔法ではないため世間に知られていない場合があると聞いたことがある。
(魔法の知識を研究して共有する責任がある魔法家として、魔法を積極的に発掘してなんとかかんとか……おじいちゃんがいつも言っていたことが、こういうことじゃないの?)
アイシャが製造法を睨みながらブツブツ考えているのを見た冒険者はカラカラと笑い、やっぱりお嬢ちゃんならその価値を分かってくれるだろうと思った、と言った。
「そこの材料も集めてあげられるぞ。必要なら何なりと言ってくれよ」
アイシャは心の中で鼻で笑った。フン、ぼったくるつもりでしょ?
結構でーす。これくらいは少し手間をかければ安く買えるから。
アイシャは急いで話を終わらせて挨拶をしてそこから離れようとしたが、ふと思ったことを彼に聞いた。
「あの、この製造法を買った人、他にもいますか?」
「あ、ああ、もう一人いたな。お嬢ちゃんより少し小さい……これくらい? の男の子だったな」
「やっぱり……」
(奥の手ってこれだったのね? バカだね。こんなものに頼って天才魔法使いの座を狙ってるの?)
アイシャは錬金術の店がある広場の路地にスタスタと足を運んだ。あんなガキの浅知恵はすでに見抜いたから、勝ち誇っていた。
「さぁ、作ってみようかな? この伝説的な魔力増幅剤と……治療剤を!」
*
どうして治療剤を? と普通の人は思うだろうが、アイシャは慎重だった。
どんな結果が出るか分からない。効果があっても持続時間がとても短かったり、とんでもない副作用があるかもしれない。
(だから、この魔力増幅剤と治療剤を同時に作るのよ!)
(錬金術は詳しくないけど、材料を知っているから何とか作れそう。ふふっ、やっぱり私って頭いい~)
一瀉千里に魔法薬が完成していった。
少し冷ましてコップに入れると、それは青黒い空に輝く星のように妙な色を帯びていた。
製造法に書かれている通りだった。
アイシャは少し息を整えてそのまま一気に飲み干した。
「お……おお……おおお……! すごい魔力が感じられる! 本物だったんだ! 本物よ! この力……たった1杯でこんなに効果が! これなら――」
……ガシャーン!
…………
*
「あらら……で、今度は何をやらかしたの?」
メリンダーさんの声に、ベッドで仰向けになっていたアイシャはうん……とうめき声をあげた。
ひどい風邪を引いた時のように全身が重い。
ズキズキとうずく痛みを感じていた。
そして、一粒のマナも感じられなかった。
「……魔力増幅剤です」
アイシャがぐずぐず言うと、皆事情が分かった様子だった。
「この地域だけの製造法、ってやつでしょう? はぁ、そんなもので詐欺をする人がいるのね」
「メリンダーさん、ご存じなのですか?」
「もちろんよ。あなたもケンセラスの葉は知ってるでしょ? 解毒剤をつくる時に使う葉っぱなんだけど、採集する時に特別に注意が必要なのよ。魔力に敏感で、指先が触れただけで薬草の効力が消えてしまうのよ。だから、昔にはそれを採集する前に薬を作って飲んだの。飲むと体の魔力が強制的に排出されて、数日間空っぽの状態になるの」
「ああ、だから、魔力が増幅されたように見えるのは一時的な現象で、実際の効果は魔力除去剤だったんですね?」
「そうよ。それもユグドラシルの栽培ができるようになったから、もう今はその葉っぱはあまり使わなくなったのよ。もちろん魔力除去剤も使わなくなったんだよね」
「知っている人間が少なくなったことを利用して詐欺を働いたなんて、悪質じゃないですか」
「こうなると思った! あの詐欺師!」
アイシャは怒りに歯ぎしりをしながらやっとの思いで起き上がってカバンの中をごそごそ探した。
「無理しないで、アイシャ。たぶん2日くらいは酷い風邪のような症状が続くと思う。一週間くらい休めば魔力は徐々に戻ってくるから心配しないでね」
「一週間? そんなに長く待たなくてもいいですよ。こんな状況に備えて治療剤も一緒に作っておいたから」
「騙されることを予想したのに飲んだの? まったく勇敢な子だな」
「まぁ、良かったじゃない。その治療剤の製造法を教えてくれない?」
「なぜですか?」
「マティがね。マティもそっちの部屋で寝込んでるの。君が来る半時間前に同じ手口にやられてしまってね」
「そうですか? マティの奴、完璧に騙されたのね! やっぱりこれは私の勝利よ!」
全身がヒリヒリしているのにスッキリした気分になったアイシャはマティの部屋に向かった。奴の目の前で治療剤を飲むつもりだった。
悔しくてたまらないでしょうね!
「アイシャ!どこに行くの!ちゃんと休みなさい!」
「後で休みます!」
(無礼なガキ! この私に終わりだなんて、二度とそんなこと言わせないよ!)
部屋に入ってみたらマティはドアを背にして横になって震えていた。怒りがこみ上げてきたようだった。アイシャは勝利を確信した。
「魔力増幅剤。それがあんたの奥の手だったのね?」
「……」
ふふん、答えられないほど騙されたのが悔しいの?
でも、このくらいで許してあげないよ!
「実は魔力除去剤だったのね? 大変ねぇ~魔法も出来ないのにこのまま寝込んでいることしか出来なくて」
知らないフリをしながらマティを煽っていたアイシャは何か間違っていると感じた。
「……ねぇ、泣いてるの?」
「しく、しく、くすん……」
マティは枕に顔を埋めて泣いていた。驚いたアイシャはあたふたマティをなだめ始めた。
「もう! 一生続く症状じゃないのよ! え、なんだっけ……あ! 1週間くらいで治るって!」
「もう……泣かないでよ! 最高の魔法使いになるって言い張って、こんなことで泣いてどうするの?」
「しく、家に……くすん……」
「え? 何か必要なの? 持ってこようか?」
「家に帰りたい……」
アイシャの表情が固まった。マティが言っている家はたぶんレンダールではない。
アイシャは先ほど他の人の話を思い出した。
魔法に才能があって弟子にしてもらった子だったっけ。家を懐かしんでいるのね。
「魔法使いに慣れるのはすごいことだって……だから、絶対最高の魔法使いになって家に戻るって……約束したのに……」
しくしくと鳴く声。
「もういやだ……! 家に帰りたいよ。くすん、母ちゃん……」
「……」
(なによ、大人ぶってたくせに完全に子供じゃん。はぁ、痛いいたいってお母さんを探す子供に魔法を教えてもね……)
背中に隠して持ってきた治療剤の瓶を見ながらアイシャは悩んだ。
(今は痛くて心に閉まっておいた色んなことが爆発したんだと思うけど……)
アイシャは治療剤の瓶を彼に渡した。
「あーもう! なによこれ! 最悪!」
八つ当たりで声を荒げたアイシャはすぐ後悔した。声をあげたら頭がガンガンと響いたからだ。
まるで頭の中でゴーレムが走り回る感じ!
「うう……可哀想にと思ってこのアイシャ様が治療剤も譲ってあげたのに、お礼も言わないの? 本当に礼儀がなってないわね! あーもう損した! 放っておいて痛い目に合わせた方が良かった!」
治療剤の製造法を教えてあげたからアイシャの分は作っている最中のはずだ。薬が完成するまではこの状態だろう。いっそのこと寝た方が良さそうだ。
アイシャは痛みと色んな後悔のせいでしばらく寝返りをうってやっと眠りについた。
…………
ス……。
アイシャは額に触れた柔らかくてひんやりとした感触を感じながら目を覚ました。
誰? 何時?
眼を開けようとしても瞼が重かった。
「熱は大分下がったわね」
優しい声だった。誰なのか確認したかったけど上手くできなかった。
たぶん、うめき声を出したようだ。
小さい笑い声が聞こえた。
「君のおかげであの子は良くなったわよ。恥ずかしがり屋さんだから厚かましく振舞っているけど、君のことをすごく心配しているわよ」
(もう治って歩いてるの? ちぇっ……いいな……)
「ねぇ、治療剤を譲ってくれてありがとう。あなたは立派なことをしたのよ」
誰かがそう言いながら額に当てた手を離した。
なんかちょっと心惜しかった。
「みんな魔法を上手になりたいと思うものだけど、上手に扱う方法はそれほど深く考えないのよね」
(何を言っているの?)
少し静かになった後、カタカタと音がした。
「マティは君がつくった治療剤を飲んで治ったけど、魔力の回復が遅かったわ。記録を探してみたけど、魔力除去剤には飲んだ後一定期間自然回復を邪魔する成分があったから……」
また、カサカサと布がこすれる音が同時に聞こえた。
ポケットの中をゴソゴソ探っているみたいだった。
「多分それが原因だと思うわ。あなたも必要な薬剤を全部入れていたけど、呪いの解除とか解毒剤をつくる時は、拮抗作用をもつ薬剤は3倍以上は必要だわ」
分からないようで分かるような話だった。
「だから、あなたが作った治療剤に私が役に立ちそうな薬剤をいくつか入れてみたわ」
カタンとテーブルの上に何かを置いたような物音がした。
額に冷たい湿布を当てて布団を綺麗にかけてくれた人は何か呪文を唱えて静かに部屋を出た。
「そろそろ行かないと。あなたはもっと寝た方がいいわ。目が覚めたら飲んでね。きっと役に立つと思うわ」
(ありがとう)
冷たい湿布が頭を軽くしてくれた気がする。
(マティとは違って……私はここが家だから)

薬を飲んで魔力をすっかり回復して元気になったアイシャがインチキの製造法を売りつけてきた冒険者を見つけ出してこらしめて、一緒に魔法ゴーレムと戦い古代の遺跡を開放する大活躍をするのは、
今のアイシャは知らない、もう少し未来の話だ。
むんむんとした部屋の空気が爽やかになったのを感じながら、アイシャは再び眠りに落ちた。
レイヴン ストーリー「機械腕の男」
ベスマ付近の小さな村。
深い夜だが、村を襲った火事がまるで夕闇のように赤く染まっていた。
ブラッククロウ団の兵士たちが一糸乱れず動く。邪魔者はいなかった。
何回かの宣戦布告が発表された後、人々が避難した誰もいない村には静寂だけが満ちていた。
「1時間だ。エルの欠片と魔法石を優先的に確保しろ」
ブラッククロウ号の団長、レイヴン。
彼の目は指示を出しながら遠いところを眺めていた。
………………
平和な週末の昼ごはんの時間なのに、セリスは怒っていた。
ぎゅっと握ったフォークとナイフが皿にぶつかって音を立てた。
オーウェンはその音がやたらと気に障ったのかセリスを睨みつけたが、結局堪え切れず一言言った。
「奴らに決闘を申し込んだって無視されるはずだと俺が言ったろ?」
その言葉でセリスは怒りをぶちまけた。
「名誉も知らない奴ら! その口を黙らせてやりたかったのに!」
話はまた最初に戻った。
クロンウェル将軍の養子になって軍事学校に入校してかなり長い時間が経ち、いろんなことがあった。
時々同年代の貴族の学生にないがしろにされたり、媚び諂われたり。見ていると気持ち悪くなることは今までずっとあったからレイヴンは今回の変な噂も別に気にしなかった。
今回は何だったか? ああ、階級の昇進を狙ったあるせこい平民がクロンウェル将軍を騙して自分の息子を入籍させたとか……そんな内容だった。
事実を確認する価値もない、根も葉もないうわさだ。身分を上げたいなら本人ではなく息子を入籍させる理由は何だ?
しかも、レイヴンがクロンウェル将軍の養子になったのは親父が死亡した後のことだ。時期的にも合わない。
少し考えるだけでもデマだと分かることだが……。
このでたらめな噂は特定の人の低俗な趣向に合っているからか、結構長い時間広がっている。
(こんな話が好きな奴の想像力は乏しいもんだ)
そもそも悪意に満ちて広がる噂は解明しても無駄だとよく分かっているレイヴンは、無視することにした。平然を装っていても、不快に感じるのは仕方のないことだった。
そして、自分のことのように怒って、悲しんで、喜んでくれるセリスにありがたくてすまない気持ちだった。
セリスへの愛情がますます大きくなるのを感じながら、レイヴンはセリスをじっと見つめた。
しかし、セリスはレイヴンの視線に気づいていない。目でオーウェンを責めながら口の食べ物を敵を噛み潰すように噛むことに夢中になっているからだ。
セリスの両頬がぴくぴくし続けた。彼女の変な表情を見て笑ってしまいそうだった。レイヴンは急いで頭を下げて自分の皿を睨みつけた。
(2人を止めるべきか?)
少し悩んだがセリスの顔をまた見たらその時は本当に笑いが溢れてしまいそうだった。
まぁ、喧嘩をしているわけでもないし、放っておいてもいいだろう。
(まぁ……ちゃんと噛むことは体にいいことだからな……?)

レイヴンは黙々と食事に集中することにした。
「他の人でもないオーウェンがどうしてそんな風に言うの? あんなでたらめな噂のどこが面白いのよ!」
「態度が面白いんじゃない? あいつらは平民のレイヴンが貴族である自分たちと一緒に学校に通うのが不満だろ? でも、レイヴンをこの学校に行かせたのはクロンウェル卿だ。そこから矛盾が生じる。だから、お好みの場面を作るためにこんな役柄が必要だったんだ。せこいな平民、騙された被害者クロンウェル卿……。なんとか貴族と平民の間に線を引こうと想像力を働かせた努力が見えるだろ? 俺が面白いと言ったのはそこだ」
「悔しいよ。どうして自慢できることが地位しかない人みたいな行動をするの?」
「実際にそうだから。 理由はそれだけではないけどな……」
オーウェンは言葉尻を濁した。たぶんあの反乱の後に起きた一連の事件と噂を思い出したのだろう。
「派閥に入りたくて色々頭を使ってるんだろう。愚かなことだけど、人を貶さないと目標した地位まで上がれない無能な奴らだから。運が良かっただけだと言っているけど、その運が誰よりも必要なのは自分たちだと認めたくないんだろう」
オーウェンは食器を静かに置いてセリスをじっと見つめながら確信しているように言った。
「だから……あいつらは『同じ』貴族に手を出すような真似は絶対にしないよ。君が何回も決闘を申し込んでも同じだ。それを断ることを不名誉なことだとはちっとも思わない。『同じ』貴族とは喧嘩したくないってことだ」
オーウェンの話を聞いたセリスは何か言いたげに少し口を動かしたが、結局何も言わなかった。
「……俺は大丈夫だから気にするな。完全に間違っている話でもないだろ?」
話に夢中になっていた二人の視線がレイヴンに向かった。
セリスは衝撃とすまない表情を、そしてオーウェンは理由が気になったような表情をしている。
「何を言ってるのよ。レイヴンのお父さんとクロンウェル卿は仲間で親しい……どうしてそんな風に言ってるの?」
レイヴンは首を横に振った。
「いや、その部分じゃなくて、俺が運がいいと言われている部分」
二人がごたごたしている間に食事を済ませたレイヴンがフォークとナイフをテーブルに置いた。
「君たちと出会ってこんな時間を過ごせることができたんだから、俺は運がいい」
「もう……はぁ、本当……。……せっかくの休日だし、楽しい話をしないとね!」
黙ってじっと見つめていたオーウェンも微かに微笑んだ。気づきにくい微笑みだった。
普段から自分の考えと感情を表に出さないオーウェンだから、その微笑みの意味は分かりにくい。だが、レイヴンは彼が満足したような顔をしていると思った。
いつも通りの平穏な日常だった。
…………。
「……貴族、平民」
「固着、向上、軽蔑、収容、排斥、衰退……」
「……人間、ナソード」
「……」
*
数十人の完全武装した王国軍が寮を取り囲んでいた。
レイヴンは異様な雰囲気に気づいたが、ざわつく心を落ち着かせた。仲間にまで不安を煽りたくなかった。
「おかしいよ……陣を張っている。どういうこと?」
セリスがレイヴンにだけ聞こえるように密かに囁いた。
冷静な声だった。
他の人が聞いたら怒っていると思うだろうが、実は不安を隠そうとするセリスの仮面だとレイヴンは経験則で知っていた。
「武器を持った方がいいかな?」
「……いや、それは止めた方がいい」
「セリス、心配するな。王国軍だ。何か誤解があったんだろう」
セリスを安心させながら、壁にもたれている剣に視線が向くのを堪えなければならなかった。
(この後はもう見たくない)
この後は……何度も繰り返される記憶だ。
押しよせてきた将校たち、そして、彼らと一緒にいた旧友……オーウェン。
芳しくないことで傭兵団を出たきりだった昔の仲間の突然の登場に驚く暇もなく、自分に逆謀の容疑がかけられる。
傭兵団は抵抗すらできず制圧された。武装しなかったことは間違った選択だった。
その時は逆謀の容疑は自分にしかなかったから武装していない仲間たちが少し騒ぎを起こしたくらいで重い処分を受けることはないだろうと安心していた。
しかし、せめて、抵抗して逮捕されたなら、皆があんな風に終わることはなかったかもしれない。
……捕縛されて強制的に跪かせられたレイヴンはオーウェンと目が合った。
しかし、彼の目からは何の表情も読めなかった。一緒に過ごした時間が無駄になるくらいに、まるで知らない人を見ているような表情をしていた。

(訳が分からない)
ふと、過去のことを思い出した。
(俺たちのことを駒……と言っていたな。それは本気だったのか?)
オーウェンは相変わらず一言も言わなかった。
もう周りには誰もいない。オーウェンとレイヴンだけだった。
どこからかおぞましい匂いと湿気を感じた。
レイヴンは急な状況の変化にも動揺しなかった。ただ、過去のことを思い浮かべているだけなのだから。
自分が王国に反旗を掲げるある勢力に利用されて、見せしめにされたのを知っている。
傭兵団は少し取り調べを受けて釈放された。逆謀の容疑は晴らされた。
しかし、仲間たちは自分を救おうとして、命を失った。
彼らの名誉も汚されてしまった。
(剣を握って戦うべきだった)
(自分たちの身を守れと命令すべきだった)
考えても無駄なのに、思考を巡らせる。
(俺が他の選択をしたなら、結果は変わっただろうか?)
「オーウェン、これがお前が望んだことなのか?」

想像の中のオーウェンは答えてくれなかった。
「俺達の絆、共に乗り越えてきた苦難と成就はただお前にとってはただの踏み台にすぎなかったのか? 結局お前も他の奴らと同じだったのか?」
オーウェンは黙ったまま笑った。軍事学校の時代に何度か見たことのある笑顔だった。
あの時は笑顔の意味が分からなかった。
しかし、今はなぜか……身の程を知っている運のいい平民に感心しているような笑顔だと感じた。
「いや……最初からだったのか?」
忌々しい奴め。
体は異様に重たかったが、剣はしっかりとオーウェンに向けた。
(……?)
レイヴンはびくっと肩をすくめて立ち止まった。
体は相変わらず重ったい。腕の筋肉から異物感を感じたがその感覚はすぐに消えた。
レイヴンは剣を構えたまま動けなかった。
「どうして攻撃を止めた?」
(さあ、分からない。俺はどうして止まったんだ?)
朦朧とした意識をしっかりと取り戻そうとしながら、レイヴンは自分が立ち止まった理由を考えてみた。
オーウェンは相変わらず微かに微笑んでいる。
「理由が重要なのか?」
(いや、もうどうでもいい)
ぽたぽたと水滴が落ちる音が気に障る。反吐が出そうな空気に、悪臭、騒音まで。これくらいになるとそろそろ耐えられない。
「なら、どうして攻撃しない?」
(俺もそれが知りたい。多分……俺に何かを望んでいるのかもな)
「俺を破滅させた存在を目の前にして立ち止まるほど?」
(うるさいから静かにしろ)
オーウェンの顔を見た。まるで剥製のような微笑みだ。
その口は永遠に開くことのないような気がする。
振り返ればオーウェンが自分の話をしたことは殆どない。
過去のことを少し話してくれたことはあるけど、自分の感情や考えは一切言ってくれなかった。
(そうだな。俺はまだ知らないことがある)
「何を?」
(俺はどうしてオーウェンがこんなことをしたのか聞いていない。それが知りたい)
「……」
(それを知るためには……ここで終わってはいけない)
レイヴンは剣を降ろした。
いや、降ろそうとした。腕に抵抗感が感じられた。
レイヴンはそれを振り切るために何回も腕を振ろうとした。しかし、腕はぴくっと微かに動いただけで、思い通りに動いてくれなかった。
自分の腕なのに他人の腕のように感じられた。俺の腕はこれほど長かったか? どうにもこうにも動かせそうにない。
「俺も知りたい」
(何を? 俺の腕のことか? それとも理由?)
その後、頭を貫くような強烈な頭痛にレイヴンは体のバランスを失って崩れてしまった。
「くあああっ……!」
荒く息を切らすたびに重くて生臭い空気が肺を満たした。
レイヴンは反吐が出そうになってしばらく呼吸を整えることに集中した。
ぽた、ぽた、ぽた、ぽた……
(水滴の音が煩すぎる)
(いますぐここから出たい)
(ところで、ここはどこだ?)
「命令に従え」
(なぜ俺が?)
「お前は俺の駒だから」
(捨て駒に使ったならもう手を放せ!)
ぽた、ぽた、ぽた、ぽた……
ぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽたぽた……
(くっそ! うるせぇ!)
「やめろ! ここでお前を倒すことはない。許すこともない。このまま立ち止まることもない。俺は必ず突き止める。お前がなぜこんなことをしたのか! 俺たちがお前のゲームでどんな役割をした駒だったのか……!」
(ゴーン!)
レイヴンは力を振り絞って腕を振り回した。振り払うような動作で、レイヴンの剣は斜線を描いて地面にぶつかった。
「くっ、ふうっ、うっ……ゴホッゴホッ!」
座り込んで肺と喉が裂けそうなほどに咳こんだ。
*
どれくらいたっただろう。苔が生えた汚い地面が視野に入った。
まるで緑色の埃や苔みたいな正体不明のものが地面を覆っていて、触ってみたらあっさりと潰れた。
(寮の床にどうしてこんなものが?)
そう考えたレイヴンは、たちまち、逮捕されたのは今よりもずっと過去のことだと気づいた。
(ここはどこだ? さっきの声は誰だ?)
ハッとして顔を上げると、巨大な瞳と目が合った。
「ふっ!?」
レイヴンは反射的に退きながら剣を握り直して防御姿勢をとった。しかし、予想に反して攻撃はなかった。
何かがおかしいと思ったレイヴンが見上げると、自分が見たのは生物の目ではなく、巨大な花だった。
仰いで見るくらいの大きな花は、腐った動物の皮のような花弁と、全体の大きさに比べて異様に巨大な雌しべがまるで玉のような形をしていた。
硬い茎と胞子が機械装置に絡んでいる殺風景の中でその花だけが生き生きとしていた。レイヴンはそれが花だと知ったのに、それに睨まれているような気がした。
暗い空間の微かな空気の流れに沿って踊るように宙を舞っていた薄緑色の胞子がレイヴンの剣にそっと降りてきた。
(これのせいで息苦しかったのか)
レイヴンは剣を収めた。
(俺はどうしてここにいるんだ?)
曖昧な記憶を辿りながら考えてみた。俺はレイヴン・クロンウェル。傭兵団の団長、そして……すべてを失った者。
逃走中、致命傷を負って……死を予感した。しかし、まだ生きている。
ナソードの王と呼ばれる機械によって改造された後に、命令に従って兵士たちを統率して略奪を……。
(……したな。最悪だ)
(しかも、今の記憶……読まれていたのか? 全然知らなかった。あんなに明確に聞こえていたのに……)
(俺の体を奪って操るだけでなく、精神まで弄ぶつもりか?)
「悪趣味だな。ここでこうしている場合じゃない。速くここから出るぞ」
出口を確認して出ようとした途端、レイヴンは立ち止まった。
(ここを出て……何ができるんだ)
恐らくこれは一時的な解放にすぎないだろう。今のような方法とは違うが、自分は何度もキングナソードの統制から逃れたことがある。
(結局、また操られたけどな)
逃げ切れたとしても、もう自分には帰る場所はない。待っている人もいない。恋人、仲間、親友、家族……。
(家族か……)
レイヴンの長くない人生で最初に失ったものだった。
クロンウェル卿に引き取られたのはもう物心ついた後のことだったから、俺なんかがあの方を家族だと思ってはいけないと思っていた……それは自分だけの考えだったかもしれない。
クロンウェル卿はどうなったんだろう。
あの方に迷惑をかけてしまったと。いろいろ困った状況に遭ったかもしれない。
自分と違って貴族で王国の功臣だから被害もそう大きくはないだろうと、レイヴンは自分自身を慰めた。
そうだとしても、そこに戻ることは出来ないだろう。
もはや慣れきったナソードの義手が付けられた左腕を動かしてみた。支配装置が統制力を失ってだんだんと感覚が戻ってきて、自分の体に浸透している機械の存在感が伝わってきた。
息を止めて静かにしていると、体の中から微かな機械装置の音も聞こえてくる。
(反吐が出る)
(……どうして俺を? どうして俺の仲間を? どうして、どうして……お前だったんだ)
*
「どうして傭兵団なんかに? 酷いよ~レイヴン。今ちょっと傷ついたかも」
「前に言ったでしょ? 自分の人生は自分で決めるのよ。家の人脈や助けは受けたくない。必要もないし。私に一番必要なのはレイヴンとオーウェンなの。私たち3人で上手くやって来たよね?」
「だから、私だけ置いて行こうと思ってるならやめた方がいいよ」
「ふふっ……冗談冗談! あ、言いたいことって、なに? 大事な話なの?」
「えっ? ……指輪……?」
(すまない)
どうして君が命を奪われなければならなかったのだろう。
心臓が激しく脈打つ。体のどれくらいが機械になったか分からないが、せめて心臓だけはまだ自分のものだったようだ。
(復讐せねばならない。この心まで奪われる前に)

支配装置がレイヴンの怒りを猛烈に煽った。
人間への復讐。ナソードの王が入れ込んだ命令は支配装置が統制力を失った後にも自分に影響を与え続けている。
(もしかしたら、最初から俺の感情だったかもしれない)
この感覚は最初から自分のものだったように慣れた感覚だったが、それは危険なことだとレイヴンは直感した。怒りを受け入れた瞬間、支配装置はまた精神を縛り付けるだろう。
早く支配装置を外さなければならない。
(確かに命令があった。地下坑道の目標物を処理して、周辺にいる土着種族を殲滅すること)
レイヴンはその種族がナソード技術に詳しいからキングナソードの警戒対象になったことを思い出した。
彼らなら支配装置を外せるかもしれない。
レイヴンの支配装置は作戦区域を離脱した後から警告を送り続けていた。ナソードの王も気づいたはずだ。時間がない。
(タッタッタッ……)
壊れたナソードと倒れているブラッククロウ団の兵士、そして通路を詰めた厄介な機械の中を縫うように走りながら、レイヴンはもう一度セリスの顔を思い浮かべた。
自然とオーウェンの顔も一緒に思い浮かんだ。
レイヴンは怒りで歯ぎしりをした。とにかく、今は過去などを振り返っている場合じゃない。
遠くに通路の入り口が見えてきた。
重さに耐えきれず垂れてしまう左腕を引き上げながら、足を速めた。
「もう貴様の命令で動く操り人形にはならない。失敗したら悪あがきでもしてやるぞ」
独り言だが、ナソードの王にも伝わるはずだ。
「これは俺の怒り、俺の復讐だ。それを利用しようとするな!」
レナ ストーリー「悪夢を克服したエルフ」
レナは悪夢で目が覚めた。まだ月が高く昇っている真夜中だった。
冷や汗を拭きながらレナは夢を思い浮かべる。
ギリギリで森を走り続けながら怪物を相手にして、ついに倒す夢。
以前から何度も見た悪夢だ。実際のところは怪物を倒せなかった。
レナはそうやって友達を失ってしまったのだ。
「これは私の罪悪感が作り出したものだね。あの時、私はもう少し頑張っていれば、迷わなかったら…立ち向かって戦っていれば…結果は変わったはずだと…」
噛み締めても無駄なこと。レナは再び寝ようとしたが、妙な気分になった。
悪夢を見ることは珍しいことではないが、今回は何かが違った。
「もう! 悪夢なんか見たからだよ」
レナは横になって何度も寝返りを打った。
「…眠れない」
レナは反対側に寝返ったり、また仰向けになったり、枕の位置を変えたり触ったりしながら寝ようとしたけど、ぎこちなさは解消できなかった。
結局、レナはベッドから起き上がった。
お散歩でもして気晴らししようかな。
レナは着替えて外に出た。
皆が寝ている時間だから村は静かで暗かった。昼の村と夜の村は、雰囲気も感想も違った。
レナは夜の風景を鑑賞しながら村を歩いた。ルーベン森の香りが込められた涼しい夜の空気が気持ちよく額を撫でる。
「昼はあんなに活気が溢れるているのに夜は静かだね。なんだか寂しいな…」
月の裏、光があれば闇もある、その言葉が思い浮かんだ。
エルの加護と暖かい日差しの力に満ちていつも新たな生命が芽生えて咲くルーベンの森なのに…
「夜はこんなに生命が何一つ見えないもの寂しい場所になってしまうのね」
一瞬ゾッと鳥肌が立った。レナは驚いた目で周囲を見渡した。
静かすぎる。
たまに虫の鳴き声や葉が風に揺れてサァサァする音がして完全な静寂ではなかったが、レナが感じたのはそれだけではなかった。
「精霊がいない!」
レナは急いで村の入口へと走り出した。
*
村の入り口には普通夜間の警備隊員二人が警戒勤務をしている。
しかし、ルーベン村には危険なことはあまりない。
そこに住む生き物たちも穏やかな方で、近くの人間の村とも仲は悪くない。
話し合っている途中だった彼らはレナの話を聞いて周囲を見渡した。
「そういえば今日は特に静かな夜だな」
「こんな時もあるわよ」
「でも、静かすぎます。夜とはいえ、精霊がこんなにいない時もありますか?」
二人は首をかしげて色々と考えていたが、答えは見つからなかった。
「俺はよくわからない。エトゥナ、君はどうだい?」
「うん? 私もわからないわよ。私より君の方が詳しいと思ったのに…」
タアルは肩を竦めながら言った。
「精霊の気まぐれじゃないかな? 夜は静かだから他の所に行っちゃったのかも」
警備隊員たちはレナを安心させようとしたが、全然安心できなかった。レナの鋭い勘は引き続き警告を発していたのだ。
「そうかもしれないけど…こんなに誰もいないのはどう考えてもおかしいことです」
「とりあえず俺たちも警戒するよ。危ない奴が現れて精霊たちが逃げたかもしれないしな」
「教えてくれてありがとう。もしかして、そのことで目覚めてしまったの? 私たちがちゃんと見張ってるから安心して寝なさい」
「……。はい! ありがとうございます。では、失礼します」
レナは微笑みながら二人の警備隊員に丁重に挨拶をした後に家に戻って弓を装備した。そして、彼らの目を避けて人通りの少ない森道に抜け出してきた。
「……」
「森にもいない。しかも虫の鳴き声もいつもよりも聞こえない気がする」
しばらく進んでいたレナは立ち止まって森の音に耳を傾けた。目を閉じてじっとしながら聴覚に集中したらいろんなことが分かった。
虫だけではない。夜は休息の時間だが、ある生き物たちには一日の始まりだ。夜には夜なりの音と気配がある。
しかし、レナは動物たちが草をかき分けて動く音も、蛇が地を這う音も、鳥が羽ばたく音も、よく聞こえた鳴き声も…何も聞こえなかった。
「やっぱり変だわ。これは尋常ではない…どうすればいい?」
音がしないこと以外にはこれとした手掛かりがなくて何をすればいいのか全くわからなかったが、レナは前にもこんなことがあったような気がした。
「とにかく考えてみよう…宛もなく歩くにはルーベンの森は大きいから」
もちろん、迷子になっても大きいエルの樹を見ながら歩けば慣れた道に出るはずだから心配する必要はないけどね。
「…そうね」
「とりあえずエルの樹に行ってみよう。そこは精霊が多い場所だから」
エルの樹に近付くと、人の気配がした。急いで走る数人の足音が聞こえた。レナは木に隠れて様子を見た。足音が止まり、男女が話し合う声が聞こえた。
「シンディ、見つかったか?」
「ううん、私が行った方向にはいなかったよ」
「大変だぞ…早く探さねぇと危ないぞ」
「他のみんなはどうだった?」
「お前以外は全員一回ここに戻ってきたんだ。全員何も見つからなかったようだ」
「じゃあ私ももう一度行ってみる」
シンディという人が合図をしたらまた人の足音が徐々に遠ざかっていく。
彼女と話し合っていた男はその場を守っていた。
姿勢を変えたり、あたりをギョロギョロと見まわしながら焦っていた。
「こんな夜中に森で何をしているのかしら?」
まさか…泥棒? そういえば最近ルーベンの森に泥棒の群れが現れて遺跡を破壊したり人を襲ったりして騒ぎを起こしていると聞いたことがある。
「あいつらのせいで精霊が消えたとは思わないけど…!」
レナは弓を取り出した。
「騒ぎを起こすのは許さない!」
シューッ! レナが射た矢が男の足から一寸もしない地面に刺さった。
「グアッ!」
男は仰天して退くと同時に鋭い剣を抜いた。剣と戦闘に慣れた人の動きだと一目でわかった。
「誰だ! 泥棒の奴らか!」
相手もレナと泥棒だと疑っている様子だった。レナは自分が勘違いした可能性について考えた。
レナがもじもじしている間に男が言った。
「これは…魔法の矢、泥棒が使うものじゃないな」
「…俺はエル捜索隊の隊員です。エルフの偵察隊員の方ですか?」
頬が熱くなるのを感じた。でも、いくら恥ずかしくても…誤解は早く解いた方がいいね。
レナは両手を上げて攻撃意思がないのを見せながら姿を現した。
「おほほほ…ごめん…本当にごめんなさい! 怪我はない? 本当にごめんね」
「大丈夫。お互い様だ。俺も君のことを泥棒だと思ったから。もしかして、エルフの村も動いているのか?」
「…そうじゃなくて、嫌な予感がして私だけ来てみただけよ。一体何が起きてるのか教えてくれるかしら?」
「そっか…」
「実は数日前から森に行ってきた人たちが、なんか怪しいものがあると話をしてな。最初は大したことないだろうと思ったが…目撃した人がどんどん増えてここ数日間夜間捜索をしていた」
「だが、今夜失踪者が出た。娘が森から帰ってこないと通報が入って急いで捜索しているんだ」
「そういうことだったのね…」
「先ほど嫌な予感がしたの。普段はこんなことないのに…」
「精霊たちが皆消えちゃって森が空っぽになったような感じだよ。動物の気配もしないし」
「うむ…言われてみればやけに静かな夜だな。確かに変だな。精霊たちが消えた…。予想以上に危険な状況かもしれないな」
「私にも手伝わせて。今までどこを捜索したの?」
「この位置を基準として12時、3時、9時方向は捜索済みだ」
「じゃあ捜索開始からあまり経ってないのね」
「いや、危険だと思って孤立しないように人数を多く割り当てて捜索に時間がかかっている」
「2,3本の木が折れるほどの打撃って言ったよね? それなら、痕跡は残っているはずなのに」
「残念だが痕跡はない。折れた木も足跡も残ってない。まるで幽霊の仕業みたいに」
「失踪者はあの娘と言っていた少女一人なの? 他にはいない? それと…私たちと捜索隊員の他に森にいる人は?」
「今はいない。村から離れた森に住んでいる子供が一人いるけど…心配になって訪ねてみたが無事だった」
「分かった。私も捜索してみるよ」
「一人で行かせるのはあれだけど…状況が状況だから仕方ないか。よろしく頼むぞ。なにか見つかったり困ったことがあればここに戻るか俺が教えた方向へ行って捜索隊員に助けを求めろ。俺ももうすぐ交代の時間だから、方向を教えてくれればそっちに合流する」
「分かった。私は…えっと…」
「あっちを探してみる。私が来た道には何もなかったし、こっちは誰も寄りつかない洞窟がある深い森。エルフたちも不気味に思っている場所だから、私が確認してくるね」
「分かった。森のエルフには余計な心配かもしれないけど…夜の森は危ないから気をつけてな」
「ありがとう。あなたも気をつけて!」
*
森の奥へ進めば進むほど嫌な予感は大きくなって、変な音が聞こえてきた。
レナはこの方向に何かあるに違いないと確信しながら、用心深く先へ進んでいった。
ドスン、ドスン、ドスン…。
(近い…この近くにいる)
レナは気配を殺して低い姿勢で慎重に接近した。
そしてそこには異質な怪物がいた。人の2倍の大きさはある巨大な怪物だった。
レナはその怪物を見た衝撃でぽかんと立ち尽くしていた。完全に同じ姿ではないが、前にもこれと似たものを見たことがある。
レナの記憶の中でルアの最後の姿が思い浮かぶ。
「あり得ない…どうしてまたあんなものが現れたの? これは悪夢だよね…」
レナの体が震えた。本能的に怪物に弓を向けたが、手が小刻みに震えた。
(こんな状態じゃ矢は射てない。落ち着こう…あの怪物が出てくる前に村に支援要請をした方がいいかも…)
その時、とてもか細い声が聞こえてきた。
「助けてください…お願い…」
驚いたレナは声のする所を見つけ出した。岩の狭間、洞窟というには狭い空間に少女がうずくまっていた。
結構離れた距離だったが、小さい箱をぎゅっと抱きしめて震えている彼女が視界に入った。
「お願い…お願いだから誰か来てください…」
怪物に見つかることを恐れて抑えたとても小さな声。
その瞬間、レナは体の震えと緊張、そして恐怖が意志と決意に変わるのを感じた。
(今回は違うわよ!)
レナは弓を引いた。
シュンッ! ブスッ!
「キィィィー!」
怪物の肩にレナの矢が命中した。それは苦しみながら周りを見回してレナを発見し、咆哮した。背筋がゾッと凍りついた。
「もうすぐ人がこっちに来るから、怪物を引きつけて連れて行かないとね!」
レナは独り言を装って大きく叫んだ。もし、怪物が人の言葉を理解できるなら危ないから。
これくらいなら洞穴の中にいる少女にも聞こえたはず。
「こいつは私が連れて逃げるからそこを離れないで待ってて! 君を助けに人が来るはずだから!」
レナは自分が来た方向に走り出した。レナの背中を見ると同時に怪物も猛烈に地面を蹴った。
レナは敵を引きつけながら矢を射った。皮が硬すぎて矢を弾かれたが、同じ場所に集中して攻撃し続け、傷を負わせた。
もう一発を射って、距離を置く。
木々の間を渡って、道のないところに誘導しながら怪物の速度を落とす。
レナは下唇を噛んだ。心臓がはじけ飛ぶようにバクバクしていたが、
レナはどんな時よりも冷静な自分に気づいた。
神聖な森に土足で踏み込んだ招かれざる者を追い払うことは、自分の古い悪夢と向き合うことなのだから。
(私は…この瞬間が来るのを待っていたのかもね)
掌から汗が出た。
汗くらいで手が滑ることはないだろうが、レナは覚悟を込めて弓が折れてしまいそうなほどにギュッと握りしめた。
距離を置いて怪物が来る場所を予測してもう一度弓を引く。
レナの手に眩しい光が宿った。
「今までの悪夢はこの瞬間のために!」
手を離すと矢が猛烈に飛んだ。
ちょうど木々の間から姿を現した怪物の額に刺さった。
ゆっくりと、だが確実に、硬い皮膚にヒビが入っていく。
(あともう少し。皮が破壊されたら、私の力を全部込めた一撃を射ち込むわよ!)
「キルルルルー!」
その時、怪物の口に光が宿った。
今までに見たことのなかった行動だが、レナの鋭い勘が危機を感じ取った。
「こらっ!!」
怪物との距離を適切に置いてきたレナだったが、今回は逆に素早く入り込んで怪物の顎を蹴った。
バキッを重い音がした。攻撃がちゃんと入ったようだ。

「森では火気厳禁よ!!」
「ケルルッ…!!」
足に蹴られた衝撃で怪物の顎が上を向いた。口に宿った光は黒い空に稲妻のような光の線を描いてすぐに消えた。
「…おう。すげぇなキック」
「おかえり、大丈夫だった?」
「あれが異常現象の原因か? 見たことのない奴だな」
捜索隊員が剣を向けたが、レナは彼を止めた。
「悪いけど、こいつは私一人でやる」
「なんか理由でもあるのか?」
(…ここで私の悪夢にまつわる辛い過去と運命的な予感を説明しはじめたら、正気じゃないって思われそうね)
「この道を真っすぐ進むと失踪した少女がいるの。岩の隙間に隠れてる。怪我の有無はまだ確認していないわ」
捜索隊員はうなずいた。
「分かった。さっきの光を見た他の捜索隊員もここに向かっているはずだ。その時まで時間を稼いでくれ」
「ふふふ、時間稼ぎはもう終わり。ここに戻る前に片づけておくね!」
捜索隊員が去って、倒れていた怪物が再び起き上がった。
あなたは顎が弱点だったのね。それと…ビームを吹いたらクタクタになるみたいね。
再びレナの手に眩しい光が宿った。
「復讐はできなくても…せめて私の悪夢は終わらせられそうね」
レナは地面を力強く蹴って、一目散に突進した。
*
長い夜の騒ぎは終わった。
少女は無事に家族のもとへと戻った。
少女はずっと神経を尖らせて怪物に見つからないように逃げ回ったせいで疲労困憊だった。最終的に捜索隊員がぐったりとしている彼女を抱き上げて連れて行った。
ルーベン村の人々もまんじりともせず夜を明かしたのか、火が灯っていて明るかった。皆は嬉しがって、励ましながら騒いでいた。
「あの…クスン、ほんと、本当に、ありが、ヒクッ!わああん…」

「言わなくても分かるわ、怖いのは倒したからもう安全よ」
「本当に、本当に怖かったです…クスン、すみません。大人なのにこんなに泣いてばかりで…でも…!」
(少女じゃなかったの? 人間の歳は外見じゃ判断できないのね)
「一晩中追いかけられたんだって? そのせいで村に戻る道を探せなくなったの?」
「いいえ…エルの樹があるからいつでも村に戻れます。でも…怪物をエルの樹に近づけたり、村の存在を気づかせてはいけないと思って…できるだけ遠い森に入ったんです」
「そんな…それは本当に…人々を守ってくれたのね。英雄様みたい。だけど、あなたは武器も持っていなかったし、捕まりそうになったじゃない。あんなに長い時間逃げられたのは本当に運がよかったね」
「あ、そ、それは…私一人ではありませんでしたので。これ…」
少女はポケットから小さな箱を取り出してレナの前で開けて見せた。
箱の中には葉に包まれた精霊たちがまるで死んでいるように眠っていた。
精霊たちの光はすぐ消えてしまいそうに淡く、か弱く見えた。
「精霊…! あなたは精霊が見えるのね!」
「はい。この子と他の精霊たちが私が逃げるのを手伝ってくれました。怪物に被さって目を隠したり、私と違う方向に行って音を出したりして混乱させたのです。でも…結局私のせいで怪我をしてしまいました。光が弱くなってしまったんですけど…なにか方法はあるのでしょうか」
レナは少女から箱を受け渡してもらった。
「私が村に連れて行くね。長老様なら何か方法を知っていると思うよ」
「ありがとうございます…本当にありがとうございます! またこの子たちと会いたいです」
レナは少女と村の人たちに挨拶をした後に村に戻った。
*
エルフの村が見えてきた。
夜の騒ぎ、空を引き裂くように伸びた不吉な光の柱、それにレナの失踪。
村は大変な状態になっていた。
「ゲッ…これは怒られるわ…」
レナは何度か深呼吸をして、怒られる覚悟をしてから村に入った。
予想通り、散々に怒られた。
(私ももう子供じゃありませんって、立派な大人ですよ!)
こんなことを言ったとして、青二才扱いをされるだけだよね。
レナは大人しく村の年長者たちに叱られた。
二度とこんなことはしないと約束までさせられた。
「もう勝手に危ない行動はしません。夜には絶対出ません」
(しばらくは…そうしますね!)
散々叱られた後にレナはやっと解放された。
レナは家に帰って休むと言っておいて、長老の家に向かった。
長老はレナが来ることを知っていたかのように、淹れたてのお茶を二杯注いでいた。
レナは箱を長老に渡して、夜に起きたことを説明した。
自分の悪夢、精霊たちが消えた物静かな森、人間の少女、衰弱した精霊たち。
そして、怪物。
長老であるブランウェはレナを叱らず、急き立てず、ただ黙々と話を聞きながら頷いた。

レナが生まれた日から今までずっと見てきた村の最年長者である彼女は、もちろんルアのことも知っていたので、レナを叱ることも問い詰めることもしなかった。
ただ、レナの成長と過去の痛みを抱えてそれに耐えてきたことを淡々と慰めた。
「精霊たちは大丈夫でしょうかね」
「休めば元気になれるだろう。それより…他のことが心配だね」
「お前と出会った怪物は大体木ほどの大きさだと聞いたが、平穏なルーベン村でも昔からたまにあんな怪物が現れたことがある」
「だが、今まで現れたのはとても小さい怪物だった。攻撃的だが、アルテラシア程度の被害も与えられないから、やんちゃな精霊たちにおもちゃ扱いされるぐらいだった」
長老は顔を上げて窓の外を眺めた。闇が晴れていくルーベンの空、が堂々とそびえるエルの樹、普段と同じ、平和で見慣れた風景だった。
「世界は大きく変わっていく。だんだんと強い怪物が現れ、精霊の力は弱まっている上に数も減っている。世界というのは常に新しく、予測できない形に変わっていくのだが、わしはこの変化が我々にどんな影響を与えるのか心配だ」
「…方法があるのでしょうか?」
「あって欲しいね」
窓の外を眺めていた長老はレナとお互いに向き合った。
普段と変わらない穏やかな顔だったが、レナは彼女の目が自分の心を見透かされているように感じた。
「探さねばな…そのうちに…」
「…はい」
レナはお茶を飲み干した後、長老に挨拶をして外へ出た。
もう一度大きく風が吹いた。
(ヒュオオ…)
緑陰の香りを含んだ風はなぜか慣れない感じがした。
「変化…世界の変化ね…」
「何もかもうまくいくってのは無理な話だよね。けど、探さなきゃならないのなら、私は行くよ」
「だって私はもうあの時みたいに弱わ…ふあぁ…」
「…眠くて倒れそう」
覚悟も覚悟だけど、レナはとりあえず今は寝ることにした。
濡れた綿のようにずっしりと重くなった体を引きずってベッドに横になると、
ゆっくりと沈むような、妙な和やかさが疲れ切ったレナを癒した。
(ヒュオオ…)
また、風が吹いた。
ラビィ ストーリー「少女と心を伝える手紙」
ラビィは人通りの少ない道端に仰向けに寝て雲を見ていた。
「あれは…鳥のもも肉! えっと、あれは…岩…?」
空を指していた手が地面に落ちた。ラビィは呟いた。
「つまんない」
エリアノドに来てからベロンドはとっても! すっごく! 忙しくなった。どれだけ忙しくなったかというと、ラビィと一緒に遊ぶ時間がないくらいに。
ベロンドがいないとラビィはつまらなくて退屈だ。
「ニーシャもそうでしょ?」
「…………」
ラビィはよいしょっと! と言いながら勢いよく起き上がった。一緒に寝ていたニーシャもススス…と釣られて起き上がった。
「楽しいことを探しに行こう~ どこへ行けばいいかな?」
「あ! エルの塔に行ってみよう。イグニアがそこにいるかもね!」
(… .… .… .….)
エルの塔に着いて部屋を探し回ってイグニアを見つけた。そうやって入ったある部屋にはイグニアだけでなく、他の巫女たちも一緒に何かを真剣に考えていた。

「お? 皆ここにいたんだ!」
「こんにちは、ラビィ!」
「ここで何してるの?」
「前に出した手紙の返事が来たので、その返事を書いています」
「わぁ、とても大事な手紙なの? いっぱい書いてるね!」
「ははっ、言いたいことがいっぱいだからね~」
「私たちはデニフ様と違って事務的な手紙ではなくて、友達や家族に書いています。なかなか会いに行けませんので」
「会いに行けない…そうなんだ! ラビィも手紙を書いてもいい?」
巫女たちは頷きながら紙を出してあげた。
「よっし! じゃあ私はマオに書くよ!」
まず、手紙の上へ「マオへ」と書いたラビィ。だが、何行か書いたらこれ以上何を書けばいいのか分からなくなった。
うーん、何を書けばいい?
「私は最近こんなことがあったよ~とか、最近のことを書いたらどうかな?」
「良いこととか、悪いこととか…お互いの近況が知りたい時に手紙を書きますから」
「書いたけど…、ラビィは最近暇すぎて書けることがないよ。せっかくだし、特別なことを書きたいんだもん!!」
ラビィはすっくと立ちあがって他の巫女たちが書いている手紙を見た。
巫女たちはそれぞれ故郷の知り合いたちに手紙を書いていた。アヌドランは返事を幾人にも書いていて忙しそうに見えた。
「わぁ、アヌドランは手紙が多いね!」
「はい! カルーソ部族の皆は私にとって家族と同じです! 村長にも書いて、ベイガー様にも…ベヒモスは元気にしているのかなと気になってそれも書きました」
「ベヒモス? ああ、この前にアヌドランが話した大きい神獣のことだね? 元気にしてると思うよ」
「うーん、アヌドランの手紙は参考にならないね。マオには動物のお友だちがいないよ。ワンちゃんはいるけど」
アルテアとシャシャは手紙を見せるのは困ると言った。
ベルダー王国とセナス公国に送る公的な手紙だから内容も面白くないと。
ラビィは理解して頷いた。
「イグニアは? イグニアは何書いた?」
「私は村長エデルに書いていたよ。ラノックス火山地帯は危ない場所だから火のエルの力が大事なんだ。だから、エルが一つになった後に心配してたよ。復元されたのは嬉しいことだけど、火のエルが急に消えてしまったら火山が爆発しちゃうよ!」
「えええ!? そんな! ラノックス村が危ないじゃん!」
「はは、火山は静かだし、村も大丈夫だから心配しないで。多分、巨大エルが復元された後、エリオス全域にエルの力が届いてるのかもね。でも、念のために、皆どうしてるかなと思って書いてるんだ。火の神獣と精霊たちの状況も気になるし」
「それはよかったね!」
「うーん、イグニアのことは良かったけど、話を聞いても何を書けばいいか全然分からないよ。北部帝国にも火山はあったっけ?」
「ラビィ様は北部帝国を旅してきましたので、経験したことの中から選んでみましょう。北部帝国では何がありましたか?」
「えっと…行く途中にとっとも大きいタコと出会って、それと…鬼たちがいたよ」
「じゃあ、その内容を書いたらどう?」
「そうしようかな~」
*
ラビィは再び紙を睨みつけながら一生懸命に考えた。
うーん…、ううーん…。うううーん…! そして、すぐ首を横に振りながらやっぱりダメ、と言った。
「タコは悪者で人をイジメたし、鬼たちも悪いイタズラっ子だったよ! そんな話を手紙で書きたくない!」
「なら他の話を探してみて。難しくないよ。ラビィが話したいことを書けばいい」
「遠くにいない人に手紙を出してもいいんです。私たちもお互いに手紙を取り交わしています」
グロリアはそう言ってダークムーンと向かい合ってにっこりと笑った。
「え? 二人は近くにいるからただ言えばいいじゃない?」
「言葉や行動で伝えられることもありますけど、よく考えて文章で表現してこそ伝えられることもあります!」
「私たちはお互いに、そして…今はいらっしゃらない先代の太陽の巫女様にも手紙を書いています。私たちを育ててくれまして、巫女としての教えを受けた方です」
「じゃあ、その手紙はどうやって渡すの?」
「書いた人が持っているのです。手紙を呼んでくれる人ももういないし、返事が来ることもありませんが…それが必要な時があります」
「うーん…少し分かった気がする。手紙って本当に色々あるのね! ラビィももう少し悩んでみる。話したいことはいっぱいだけど、せっかくだし、特別で楽しいことを書きたいの!」
「そうだ! 他の人にも聞いてくる!」
ラビィは紙を持ってささっと走っていった。
「転んじゃうよ! ゆっくりと歩きなさい!」
ラビィはうんうんと言って走りながら振り向いて手を振った。
*
マスターたちを探していたラビィはガイアとデニフを見つけた。嬉しくて挨拶しようとしたが、二人は急いでどこかへ向かっていた。
「あ、ラビィ? 元気にしてた? 悪いけど、今はちょっと忙しい! 後で話そう」
ガイアは山積みになった本と書類を抱えてデニフの後をついて行った。
「…まだ何も言ってないのに。」
「ふむ、そうね。二人は忙しいんだ! 他の人の所に行ってみよう」
次に訪れた場所はロッソがいる場所だった。
ロッソは不愛想な態度でラビィを迎え入れたが、それでもラビィは構わず手紙の話をして紙を見せた。
「…なのに急に紙を燃やして! 本当に意地悪。また新しい紙をもらいに行かなきゃならないじゃん」
「…………」
「あ、ラビィは全然熱くなかったよ。でもちょっと驚いたよ。いきなりメラっと! 火がついて紙が一瞬で消えちゃったよ? 紙はよく燃えるものだったんだ」
今度はベントスだった。ベントスと会ってからやっとまともな会話ができた。
「…だから何を書けばいいのか聞いていたよ。でも、皆忙しくて聞けなかったの」
「はは、皆忙しいんだね」
「どう? ベントスは何を書きたい?」
「手紙? 私は書かないよ。多分他のマスター達も書かないと思うね。手紙を受け取る人がいないでしょ?」
「え? なんでいないの?」
「私たちってさ、何百年も前の人だろ? 知っている人は皆消えてしまったよ」
しまった。ラビィは心でそう思った。自分が大きな誤ちをしたと思った。
「あ…そうね! ごめんなさい。ラビィがよく分からずに質問しちゃったね。ロッソが怒ったのもそれが理由だったかもしれないね」
ロッソは火の力がうまく制御できない状況だから、ラビィが近くにいるだけでも神経をとがらせるだろうが、あえてベントスはそれは言わなかった。
「大丈夫、大丈夫。私もロッソも、手紙なんかあまり書かないんだ。エルが爆発する前からね」
「それと…特別な話を書こうとすれば逆に出てこないもんだよ。手紙はお互いの心を取り交わすこと。それ自体が特別なことだよ」
「そうなんだ…教えてくれてありがとう! 少し分かった気がする!」
そう言ってラビィはささっとどこかへ消えた。
「なかなか大人らしい助言も言えるようになったじゃない」
「はは、そうかい?」
*
ラビィは巫女たちの場所に戻った。巫女たちはちょうど手紙を封している時だった。
「待って…待って…」
アヌドランは精神を集中させて慎重にスタンプを押した。
「では…離しますよ。エイッ!」
スタンプを離すと封蝋の上に派手な模様が刻まれていた。
「わー! こんな風にするのですね! 面白いです!」
「上手くできたね~。使ったことがないとは思わなかった。サンディールでは手紙をどうやって封詰めするの?」
「サンディールでは小さな巾着に入れて鳥の足にちゃんと巻き付けて送ります。商人さんにお願いする時もありますね。砂漠はとても広いですので」
(タッタッタッ!)
どんどん近づいてくる足音を聞いた巫女たちはラビィが戻ってきたのが分かった。そして、予想通りに勢いよく開かれるドア。
「ただいま!」
「おかえり。手紙は書いたの? 私たちはそろそろ送るつもりだけど」
「ちょっと待って! 今から書く! でもね、紙がいーっぱい必要なの!」
「話したいことがたくさんありますか? いくらでもお使いください」
「手紙を封するのは私に任せてください」
「ありがとう!」
ラビィは再び椅子に座って集中して手紙を書いた。
「マオへ…こんにちは…私…ラビィだよ…」
「(……。……。)」
*
マスターデニフの部屋の前。グロリアとダークムーンが門の前で話していた。
「じゃあ、私がするよ?」
ダークムーンは頷いた。グロリアはドアをコンコンとノックした。仲良しな姉妹は顔を合わせて声を殺しながらクスクスと笑っていた。
部屋から聞こえてくる足の音がどんどん近づいてきてドアが開かれた。ガイアだった。
「こんにちは、なにか御用ですか?」
グロリアとダークムーンはお互いを見つめ合って、一、二、三と小さく数えた。そして大きい声で叫んだ。
「手紙の配達です!」
「手紙の配達です!」
ガイアは姉妹の突拍子もない行動に驚いて目を丸くした。
「手紙ですか? デニフ様が昨日手紙を送りましたけど、こんなに早く返事が来るはずはないし…誰からの手紙ですか?」
姉妹二人はクスクスと笑ってニッコリと笑顔を見せた。
「二人に手紙が届きました」
ベントスがラビィの手紙をリンシーに渡した。
「へぇ、リンシー、これ見て。ラビィがリンシーにも手紙を書いたよ?」
「私に? どんな内容かな?」
「とりあえず私の手紙を先に読もうか」
"ベントス、こんにちは! さっき言ったこと、ごめんね。全然知らなかったよ。ラビィの考えが浅かった。
ラビィが手紙に書く内容で悩んでいたでしょ? 話したいことがあっても相手がいないことを想像したら寂しくなったよ。だからラビィは皆に手紙を書くことにしたよ! いつも質問に答えてくれてありがとう。ラビィもベントスとお話するの楽しいよ!
これからは手紙もしようよ! またね!"
「ははは、文通相手ができちゃったね。リンシーのはこれ。ここを見て」
ベントスは封筒を開けて中身を見せてあげた。中には小さく切った紙が半分折になっていた。
「精霊に合わせた大きさの手紙だ。リンシーにちょうどいい大きさだね?」
「からかわないで早く見せてよ!」
アヌドランもロッソに一枚の手紙を渡した。
「はぁ? 手紙?」
アヌドランは黙ったまま微笑みながら手紙を再び差し出した。ロッソはぶっきらぼうにそれを見つめて手紙をひったくって取って開けた。
ロッソの瞳が左右に動いた。
「…また余計なことを…」
「私にも手紙を書いてくれました。私と一緒に話すのがとても楽しくて好きだと言ってくれました。いつか私の村に行ってみたいけど、一緒に行ってほしいと書いていました。本当に一緒に行きたいです!」
ロッソはアヌドランを少し睨みつけた後に手紙をたたんで封筒に入れた。
「くだらない話を長々と書いたな。お前にも、オレにも」
そしてロッソは手紙をアヌドランに突き返した。アヌドランは手を後ろに隠して、怒った表情を見せた。
「これを私に渡してどうするのですか! ラビィ様がロッソ様に書いた手紙でしょう?」
「それがなんだ」
「書いた人の気持ちを考えてください!」
ロッソは無神経に手紙を放り投げた。アヌドランはむっとして手紙を受け取った。
「本当にひどい方ですね」
「そもそも火を使う奴に手紙を書く奴がバカなんだよ。オレが持っていたらいつか燃えちまうぞ」
「オレの部屋のどこかに押し込んどけ」
「あ……かしこまりました! では、そうします!」
*
ラビィは静かな場所に座ってニーシャと話していた。
空を見ながら、手紙を送った人を指折りで数えていた。
「…あと、マオと、カロンと、ワンちゃんと…領主様にも送ったっけ! えへへっ、ちゃんと届いてて欲しいな。返事ももらえるかな?」
「……」
「いいよ。忙しくて返事は無理かもしれないけど、その分、ラビィが書けばいいの!」
「それと、ニーシャ…実は送っていない手紙が一つあるよ」
「これはあなたに書いたの」
「……」
「私が読んであげる!」

「ニーシャ。私たちはいつも一緒にいて、だから手紙を書かなくてもいつでもお話しできるけど、それでも書いてみたよ。だって、手紙だと普段言えないことも言えるでしょ?」
「…。……」
「えへへっ、待って待って! もう少し聞いてちょうだい」
「私たちが一緒に黒い森を出た時、覚えてる? 本当にドキドキワクワクしたよね。息が切れて大変だったけど、止まらずに走ったね。ラビィは森の外がとても知りたかったんだもん! ニーシャもそうだったんでしょ? それから私たちはどんな冒険だって一緒だったよ…」
「ラビィはね、本当に運がよかったと思うよ。森を出てからベロンドと出会って、マオと出会って…いい人とたくさん出会ったよ。悪い人をお仕置きしたこともあった!」
「ねぇ、知ってる? あれは全部ニーシャのおかげだよ。いつも私のそばにいてくれる唯一の友達。おかげでラビィは寂しくも怖くもなかったよ」
「ニーシャ。私の大切な友達…あなたにもラビィが大切な存在になれたらいいな」
「………… …. …!」
「へへっ、ニーシャの気持ち、よく分かってる! ラビィも嬉しいよ!」
「私たち、ラビィが何者なのか知るために旅をしようって約束したじゃん? きっととてもワクワクするような、驚くことが広がるよ! 世界はラビィが想像した以上に大きくて広いから! だからラビィは…ラビィの正体が分かった後も冒険がしたいよ」
「ニーシャ、一緒にいてくれる?」
「….……! ……!」
「ありがとう、本当にありがとう、ニーシャ!」
ラビィは仰向けに寝そべって空を眺めた。
「次はどんな冒険が待っているのかな?」
ルシエル ストーリー「砂漠の主君と執事」
サンディールから少し離れた所にある捨てられた家。
ルーはシエルが綺麗に掃除したベッドで転がりながら時間を過ごしていた。まだ埃の匂いがするけど、心地よかった。
夜頃にはサンディールで休むつもりだったが、サンディール近くに住む部族からの攻撃が激しかったため少し下がって様子を見ることにした。
「そこまで身を引かなくてもいいと思うのじゃが…」
何も考えていないルーとは違って、シエルには悩みがあるようだった。捨てられた家を探し、周辺を確認して危険要素がないと判断したシエルは掃除を済ませて、確認したいことがあると言い残して家を出た。
「ルー、すぐ戻るからここで休みながら待ってて」
「ふーん? 分かった。そろそろ腹が減る頃じゃから遅れるな」
寝転がりながら久々の休憩を楽しんでいたルーはシエルを見て少し気が咎めた。ここ最近ずっと戦いばかりだったから。
ラノックスから遠くなって魔族の暗殺者に襲撃される頻度は減ったが、まだ油断できない。
いつまた追手が来るか分からないため、一ヵ所に長く留まることもできない。去る前に痕跡を消さなければならない。それに、魔族以外にもモンスターやサンディール部族との戦闘もある。
「エリオスの奴らも色々大変じゃのぅ~」
「よくもこんないい場所を見つけたのじゃ。屋根がある場所で寛ぐことも久々のことじゃのぅ。それにキッチンもあって、シエルの料理に期待なのじゃ~。ここはラノックスよりサンディールに近いとシエルが言っていたな。なら、新しいデザートが食べられる絶好のチャンスではないか!」
想像しただけでルーは幸せになった。
(カチャッ)
「ただいま。ルー、何事もなかった?」
「お! ちょうどいい所に来たの! シエル! 食べたいデザートがあるのじゃ」
「あ、ごめん。悪いけど、しばらくデザートはないよ」
「え? 今何と言ったのじゃ……?」
「ここにいる間はデザートはないよ」
「……」
「デザートはないって、どういうことじゃ!? 余は納得できぬ!」
「それがさ、ルー、聞いて? 今サンディールのトゥーラックとハーピィ部族が対立しているらしいよ。まだ戦争が起きたわけではないけど、もうすぐ戦争になる可能性がある。いつどうなるか分からない危険な状況だから、サンディールも安全なところじゃないよ。だから、村じゃなくて他の道を行った方がいいと思う。しばらくは野宿だから……当分の間は無理だよ」
「そ、そういうことなら仕方ないのぅ。じゃが、ここにいる間は食べられるじゃろう……?」
「それも無理だね」
「何故じゃ!」
「最近、魔族の暗殺者の攻撃は減ったけど、モンスターの襲撃が増えたよね。俺の推測だけど、どうやら鼻が利く奴らが香ばしいバターの匂いに惹かれて来てる様子だから……」
「だから、安全な場所に行くまではデザートは作らないよ。荷物も増えるし」
「こ……これは、理不尽じゃ! 余はデザートがないと生きていけぬのじゃ! 余がデザートを食べられず倒れてしまっても後悔しない自信があるのか!? シエール!!」
「ルー、デザートは嗜好品でしょ? 食べなかったくらいで倒れる生き物はいないね」
何回も駄々をこねて、説得してみて、おねだりをして、怒ってみてもシエルはびくともしなかった。
「そう来るのか! もう夕飯の支度は手伝わぬ! フン!」
シエルはルーが手伝わなくてもテキパキと料理をした。むしろ、ルーが手伝った日より早く終わった。
ルーは硬いパンにジャガイモのシチューをつけて食べながら悲しい顔をした。
「美味しい、美味しいのじゃが……素朴過ぎる味なのじゃ。ぐぐぐっ! シエル! これまでの戦闘と旅で疲れた余の体は糖分を求めておる。シチューとパンでは満たされない空腹があるのじゃ!」
そう言いながらシチューをお替わりして食べたが……内緒にしておこう。
「ルー、3食をちゃんと食べながら旅ができることはかなり豪華な生活だよ」
シエルの言葉は当然ルーには届かず、ルーはどうしたらシエルが自分の言いなりに動いてくれるだろうか悩み始めた。
悩み始めてどれくらいの時間が経っただろう。
「……スヤ……」
ルーが悩み始めて5分も経たないうちに寝落ちしてしまったのは深く悩まなかったからではなく、累積された疲労、そして満腹から眠気に襲われたからだろう。
*
昨日食べ残したシチューを加熱して朝ごはんを済ませたルーとシエルは朝早く荷物をまとめて家を出た。
「もう少し泊まっていっても良かったのにのぅ」
「いつ暗殺者が現れるか分からないし……余裕があるうちに早く安全なところに行きたいんだ。サンディールの部族紛争が大きくなれば、きっといろいろ大変な状況になるはずだから」
出発して間もなく、またモンスターと遭遇した。トゥーラックと呼ばれる岩の体を持つ部族とも戦った。
日が暮れると岩が少なく風を避けられるところで野宿した。
ルーは諦めずに、眠る前までほぼ一日中ずっとシエルに "デザートを作らなければならない理由" を言いながらシエルの心を変えようと頑張った。
「モンスターの襲撃が増えたことはデザートの匂いとは関係ないのじゃ。きっと余が魔界の君主じゃから追われているに違いない!」
「ルー……あれはエリオスのモンスターだよ。魔族に命令されたわけがない」
「魔族の命令を受けたかもしれぬのじゃ! もう一度よく考えてみろ! きっと魔族と関係があるのであって、デザートとは何の関係もないはずじゃ!」
揉めている最中、奇岩地帯に入った。トゥーラックが見えなくなったと思ったら、ここからはハーピィたちの領地のようだ。
もちろん、ハーピィたちも決して油断してはならない恐ろしい存在だ。ルーとシエルは空中からの襲撃に気をつけながら慎重に道を歩いた。
奇岩と崖が広がるこの険しい奇岩地帯は標高が高く、視界が開け広々としていて風がとても強い。
さすが、砂と風の地サンディールと呼ばれるだけある環境だった。
「ルー、大丈夫? 大変だよね」
「ゼェゼェ……もちろんだいじょばない! なんでこんなに険しい道なのじゃ!」
「でも、この奇岩地帯を抜ければ平坦な道が続くらしいよ。トゥーラックとハーピィたちの領域からも抜け出せるから、もうすぐ安全な旅ができるだろうね」
要するに、ここが最終関門ということだ。ルーはシエルが差し出した手を握って岩を登ってシエルの隣に立った。
「あの岩見える? 昨日寄った岩だよ」
「おお! 影で休めるほど大きな岩じゃったのにここからじゃ小さく見えるんじゃのぅ」
ルーはシエルが言った岩を基準点として過ぎた道を測ってみた。長くない時間だったのに相当の距離を移動してきた。迷わずに来れたからだろう。
しまった、遠くを見ようと思わず身を乗り出しすぎた。
不安定な姿勢になってふらついたが、シエルが絶妙なタイミングで腰を掴んでくれた。
ルーはしばらく自分のパートナーを見つめた。
ここ数日、サンディールの荒い風音で目が覚める度に地図を広げて道をしっかりと確認するシエルの背中を見た。
険しい砂漠を大した苦労もせず突破できたのはきっと彼のお陰だろう。
「ルー、知ってる? この砂漠地帯を過ぎてもっと南のほうに行くと水だらけの都市があるらしいよ。見える全てが海だよ。想像するだけで素敵じゃない?」
「疲れたでしょ? もうちょっと頑張って。安全な所まで行けば今まで食べられなかったデザートをいっぱい作ってあげるから」
「……そう。期待してるのじゃ」
常に自覚しているわけではないが、シエルはこの長い旅の中で誠実に自分を補佐してくれた有能な仲間であり、忠実で大切な執事だった。
二人はしばらく風景を鑑賞してからまた旅に出た。あともう少しで枯れ果てた砂漠と辛い登山から逃れられるだろう。
……しかし、ほどなくルーとシエルは荷物と食糧をすべて失ってしまう。
*
それは一瞬のことだった。
途中で途切れているとても狭い道。大人は飛び越えられるほどの亀裂の向こうには道が続いていた。荷物を持って先に飛び越えたシエルは、ルーが飛び越えるのを手伝うために手を差し出した。
シエルの手を掴んで飛び越えようとした瞬間、ルーはいきなりゾッとした。
「さぁ、下は見ないで俺の手を掴んで。すぐ渡れるよ」
ルーはそうするつもりだった。
しかし、また全身がゾッとしてルーの体が強張る。微弱だったが、間違いなく馴染んだ感覚だった。
「なんじゃろう。そういえばこの前にトゥーラックと出くわした時も同じ感覚を感じたような……」
「ルー? 大丈夫?」
「あ……すまない。ちょっと他の事を考えてしまったのじゃ」
ルーがシエルの手を掴んで道を渡ろうとしたその時。
「ピーッ!」
ハーピィの鳴き声が相当近いところから聞こえてきた。翼が風を切る鋭い音が速く近づいてくる。
「ルー! 危ない!!」
シエルは後先考えずルーを抱きしめて転んで避けた。ハーピィはギリギリでルーとシエルがいた所を過ぎていった。
ルーとシエルはどんどん遠くなるハーピィを見ながら安堵のため息をついた。
「危なかった……ルー、怪我はない?」
「おかげで無事じゃ。シエルは大丈夫か?」
「俺も大丈夫だけど……」
(ガラガラ)
シエルが口を開けた瞬間、崖の一部が崩れ落ちた。ハーピィの急襲で損害を受けたせいだ。
シエルがもう一度ルーを庇った。幸い二人には大きな被害はなかったが、ルーはシエルの腕の隙間から、石と共に崖の下へ転げ落ちる荷物をはっきりと見た。
一瞬で全財産と食料を失くしたルーとシエルは大きく落胆したが、お互いに慰め合った。
「助けてくれてありがとう。全て失ったけど命は助かったではないか。二人とも狩りはできるのじゃから、食料はなんとかなるじゃろう」
二人はしばらく隠れて様子を見て、安全を確認した後に再び歩き出した。
「…………」
「いや……ネズミ一匹さえ見当たらない地じゃったのぅ……」
食料の問題は予想以上に早く二人の足を引っ張った。
まぁ、ルーとシエルがここまでくる間にも食べられる動物や植物はほとんどいなかった。
幸いに水は見つけて渇きは解決できたが、空腹を満たすことは出来なかった。
「あのハーピィ……ハーピィのせいで……」
ルーは歯を食いしばった。
ハーピィであれモンスターであれ……目の前に現れたら食べてやるのじゃ!」
「ルー……ハーピィも人間のように知能のある生物だよ?」
「構わん! 骨一本残さず全部食い尽くしてやるのじゃ! 捕まえさえすれば……!」
「……まだまだ元気だね」
(バサッ)
「ん? 何だ、あれは?」
(バサバサ)
「……ピィ?」
子ハーピィは生まれて間もないように見えた。体に比べてとても小さな翼、ふわふわな黄色の産毛が生えた体、そしてつぶらな黒い瞳。

「生まれたばかりの子だね!」
「可愛いのぅぅ!」
「さっきまでは食いつくすとか言わなかった?」
「そんな! この可愛い生き物を食べるなんて、あり得ないことなのじゃ! それに、攻撃してきたのは大きい奴じゃ。この小さくて可愛い子には罪がないのじゃぁ~可愛い~」
子ハーピィはルーとシエルにたくさん可愛がられた。ハーピィたちは小さい時には警戒心があまりないようだ。
「ピピィ~」
「どうやら迷子のようじゃが、飼ってもよいかの?」
「俺もそうしたいけど……ダメだ。子ハーピィがここにいるってことは近くに成体のハーピィもいるってことだから。実はかなり危険な状況だね。俺たちも早くここから離れよう」
二人は未練がましく子ハーピィに別れを告げた。小走りでしばらく二人の後をついてきたが、すぐ他のものに気を取られたようだった。
「運が良かったね。子ハーピィはほとんど見られないと聞いたよ。ハーピィはとても強いけど、幼体の時は爪も小さいし力も弱いよ。翼が小さくて飛べないし。だから、成体は自分の子も他のハーピィの子も巣の中で大事に育てるらしいよ。あの子みたいに巣の外にいるのはとても珍しいことだよ」
「ほぉ~そうなのか? 誰かが世話をしてくれないと自分の身を守れないか弱い生き物があれほど強くなれるとは」
「キィィーッ!」
「ひぃー! 驚いた! これは何の音じゃ?」
「俺たちの後ろだ! 何だ? ハーピィの声ではないみたいだけど?」
子ハーピィがいた方向からだった。二人は急いで音がする方向に駆けつけた。
怒ったグリピグが子ハーピィを脅していた。
「ピィィ……ピッ!」
「よ、よくも余の可愛いピピちゃんを!」
「いつの間に名前までつけたんだい?」
「今つけてやったのじゃ! ほら、奴をさっさとやっつけようぞ!」
グリピグに向かって二人の武器が舞った。
*
「…………」
「はぁぁ~久々にお腹いっぱいになったのじゃ~」
ルーが満足げに仰向けになって寝転がった。
砂漠の素敵な星空と暖かい焚火、そして肉が与えてくれた満腹感。これ以上満足な夜はないだろう。
「ルー、ご飯食べてすぐに寝転がると牛になるよ」
ルーはようやく起き上がって座った。二人が救った子ハーピィは暖かい焚火の温もりを感じながらシエルの膝の上でうとうとしていた。
「ピルル……」
その姿を見ていると眠気が押し寄せてくる。とても穏やかな夜だった。
「シエル、ハーピィは雛を大切に育てると言っていたがの?
こいつは世話をしてもらっていないような気がするんじゃが」
「そうだね。どうやら群れからはぐれたようだね」
「おやおや……この前に攻撃してきたハーピィは子を失ってイライラしていたかもしれぬの。可哀想に……」
「こいつの親を探してやろうか?」
「うむ……ハーピィには人間の言葉が通じると聞いたことがある。俺たちが子ハーピィを保護しているのを知れば攻撃をしてこないかもね」
「それに、こんなに可愛い子を置いて行ったら気が咎める」
「よぉっし! 明日の朝にこの子をハーピィたちの所へ連れて行くのじゃ」
*
「シューッ!」
ハーピィが素早くルーとシエルを襲った。
二人は左右に分かれてかろうじて攻撃を避けた。少しでも遅かったら、一撃で致命傷を負ったかもしれない。
ルーはカッとなって空のハーピィに叫んだ。
「この愚か者め! 自分の子も見分けられんのか!」
怯えた子ハーピィは産毛を立てながらルーの足元に隠れようとした。
とんでもないことだ。この子の何が悪いというのだ?
「くっ、今は後退した方がいいよ」
シエルはしばらくの間銃でハーピィを威嚇した後、素早く走ってルーと子ハーピィを連れて狭い崖の隙間に潜り込んだ。
(ガリガリ、パキッ!)
間一髪でルーとシエルに届かなかったハーピィが崖の隙間の周りを引っ掻いている。幸い隙間は狭かった。ハーピィはもう一度飛び上がり、脅すように周辺を飛び回った。
「キエーッ!!」
「しまったのぅ……これじゃ出られん」
「変だな……」
「ハーピィは賢明な種族だ。人間と言語を共有しているし。だからハーピィたちを『群れ』なんかじゃなくて『部族』と称している。なのに、言葉が全然通じない。雛がいるのに攻撃してくるし……俺たちが誘拐したと思っているのかな? それでも変な状況だよ」
「もしかして、こいつはハーピィじゃないとか?」
シエルは疑い深い目で子ハーピィを持ち上げて確認した。
「ふむ……まん丸くて……ふわふわで……どうみてもハーピィだけど」
「あ、またじゃ……」
最初にハーピィに襲われた時に感じた異様な感覚がまたルーを襲った。
「これは何じゃ……?」
きっと知っている感覚なのに思い出せない。
(ということは…魔族と関係があるに違いない)
とても長い時間封印されていたために失ってしまった記憶の一つだろう。ならば……
「シエル、ここでピピちゃんを守っておれ!」
「なっ……ルー!? 何を……!」
ルーはシエルが止める間もなく外に飛び出した。
入り口を旋回していたハーピィはルーを見つけると爪を立てて襲い掛かった
「キエッ!」
「ルー!」
「なかなか鋭い爪じゃのぅ。じゃが、余と比べられる程ではないのじゃ!」

ルーはハーピィの攻撃を避けると同時に背中にしがみついた。予想通りにハーピィはルーを振り払おうと体を振るいまくった。
重力の方向がコロコロ変わって、凄まじい風邪の音が聞こえた。その風の音のいくつかはシエルの悲鳴だった気がしたが、確認はできなかった。
風のせいで目を開けられず、ルーは集中した。自分が感じた "怪しいけど知っているあの感覚" がどこから来たのか確かめるために。
「見つけた!」

ルーはハーピィの背中、首筋と両翼の間からあの間隔の根源を確認した。
見覚えのある文様が肌の上に浮いていた。
「この文様は……見たことがある。魔族の仕業じゃ!」
「なにかの種……とか言ったはずじゃが……?」
正確な名称は重要なことではない。ルーは首を振って解決する方法を考えてみた。
絶望的に、この呪術を解除するのは自分の能力では無理だった。
「ならば、この方法しかないのじゃ……すまないが、少し耐えてくれ……!」
ルーは身悶えするハーピィが大きい怪我を負わないように慎重に手を動かした。
「ピィィィッ!」
*
「ハーピィが俺たちに警告もせず攻撃してきたのは魔族の呪術のせいだったってこと? いくらなんでも俺に何も言わずに飛び出していったのは酷いよ」
「んぬぬ……! 分かった分かった! もうそんなことはしないから、小言を言うな!」
「とにかく、トゥーラックたちもきっとこの呪いにやられたのじゃろう。あの呪いは伝染するもんじゃから」
「サンディール周辺に起きた部族紛争も魔族の影響だったのか……」
「ふふ、でもこの件はうまく解決できたの。めでたしめでたし、じゃ」
「ルーはハーピィたちと別れた時を思い浮かべた」
魔族の呪いから解放されたハーピィは正気に戻って、すぐに状況を全て理解した。
首筋から血を流しながらも、子ハーピィをおんぶしながらルーとシエルに感謝の気持ちを伝えるあの姿はたぶん一生忘れられないだろう。
ハーピィはしばらく自分の部族がいる奇岩地帯の崖を見つめた後、正反対の方向へと子ハーピィを連れて去った。呪術の伝染に関しては言わなかったが、賢明なハーピィはそのことに気づいたのだろう。
「あああ!」
「どうかした?」
「この騒ぎは魔族の仕業じゃったから、もうデザートを作れるじゃろ!」
「またその話か……」
「なんじゃ!? これはとても! ほんとーに大事なことじゃ! うんうん!」
「残念なことに……崖で荷物を全部なくしたから今は道具も材料もないよ。もちろんお金も……村に行っても何も買えない状況だよ」
「ふふっ! それなら問題ない!」
「シエル、よーく聞け。サンディールの人々は最近の紛争で色々大変な状況じゃろう?」
「ま、そうだね」
「ではでは~お主と余が彼らを助ければ感謝するじゃろ?」
「ふむふむ」
「助けてやるとトーゼンお礼は巡ってくるもんじゃ」
「とても腹黒い助けだね。まぁ、商人たちは今莫大な損をしているはずだね。自由に移動できないだろうし、商談が攻撃されないよう武装する費用もかかるだろうしね」
「俺たちが商人を手伝えば、きっと相当の報酬が貰えそうだね」
「ほっほほ! じゃあ、決まりじゃ! 行くぞ、シエル! ロールケーキとプリンに向かって!」
「はいはい、サンディール村ね」
アラ ストーリー 「見知らぬ霊獣と少女」
(アレンの手紙)
"ごぶさたしています。
風に舞う花吹雪が目に眩しい今日この頃、元気でお過ごしでしょうか。
こちらの首都は絶景です。街路樹には色とりどりの花が咲き誇り、舞い散る花びらが羽衣のように池を美しく染めています。この派手な光景が故郷の小さな花木よりも劣っていると感じているのを見ると、流石に私はまだ首都の人ではないようです。
愚痴が長かったですね。でも、ここを好きになれるように努力しています。"
(花木……やっとその懐かしさが分かったような気がします)
//アラよ。何を考えておる? あそこの山の入り口に村が見えるから頑張るのじゃ//
「はぁい……好きになれるように頑張るしかないですね」
アラは元気なく答えた。アラのしょぼい反応に白は一言付け加えた。
//一晩中歩いて疲れているのじゃろうが、背筋を伸ばして顔を上げろ。この前の村でやったようなことを繰り返されたら困る//
しかし、その一言でアラはむしろ心細くなってしまった。生まれた村の外を全く知らない初な17才の貴族の娘にとって、この世は甘くなかった。
「……でも。この旅で確実に分かったことがあります」
//なんじゃ?//
「世の中を小説で学んではいけないということと……人が一番怖いということですね」
//……当たり前のことを言っておるな。己が持つ者の価値もよく分かっておらぬ、なまっちょろい旅人は美味しい獲物になるわけじゃ//
「でも、あそこまで取引の才能がないとは初めて知りました……」
「そもそも、装身具を金に換えてもらえる所が多くないということも初めて知りましたね」
アラはこの前に宿泊代と食事代を払うために金の指輪を出して村の人々を驚かせてしまったことを思い出しながら少し笑った。恥ずかしがるアラに冗談めかして、村ごと買いに来たの?、と言いながら親切に寝場所を用意してくれたし、素朴な食事も分けてくれた。そして、装身具を金に換えられる大きな村へ行く道も教えてくれた。
その村で派手にカモにされたのは後で知ったことだったが。
アラはその記憶を振り払って村に入った。
*
早朝だが、村には物騒な雰囲気が漂っている。人々は熊手を手に取って集まり、何やら深刻な話を交わしていた。
//畑仕事をするために集まった訳ではないようじゃな//
アラを見て彼らは警戒し始めた。
「すぐにでも戦闘に入りそうな雰囲気ですね。まさか、この村にも魔族が攻めてきたのでしょうか?」
//そんな気配はない//
「そうですか……。でも、タイミングが悪かったみたいです……」
アラは緊張した。今まで会ったことはないけれど、魔族の侵攻で居場所を失った人々が盗賊になったという噂をちらっと聞いたからだ。
首都に近づくほど旅が難しくなるとは予想していたが、今がその時かもしれない……。
//武器の代わりに手に取っているのは農具じゃし、相手にならんじゃろう。いざとなったら先に制圧したらどうじゃ?//
「できれば騒ぎを起こしたくありません……」
アラがためらっているうちにとりわけ厳しい顔つきの男が出てきて、声をかけた。
「おい、なかなか戦えそうな格好をしているんだな……」
アラは緊張しながら槍の柄をしっかりと握った。
「もしかして退魔師か?」
「退魔……ですか?」
「このお姉ちゃんはダメ!」
アラの後ろのほうから干し草の匂いと一緒に子どもの甲高い声が聞こえてきた。
「私は反対よ! 私、言ったでしょ? あの山にいるのは化け物じゃなくて神霊様なのよ! 退治しちゃだめなの!」
「神霊……様? 退治……ですか?」
予想外の話にアラの目が丸くなった。
「ゼンチェ、その話はもう終わったでしょ? 会ったこともないのにどうして神霊様だと確信しているの?」
「私知ってるんだもん! アレは神霊様に違いないの!」
村人の話を注意深く聞いていたアラは大体の状況が分かった。
ここは尾根の下にある名もない小さな村。山には神霊様と呼ばれる一匹の霊獣が昔から住んでいて、村の人々は山で薬草を採ったり、木を切ったりして辛うじて生計を立てていた。強い霊獣が生きる一帯は危険な獣や鬼が寄りつかない安全な場所となるため、人と霊獣は共生関係であった。
しかし、ある日山の主であった霊獣がここを去ってしまった。
(神霊様……ヌシが自分の領域を捨てて去ってしまうなんて……そんなこともあるんですね……)
滅びる兆しが入ったと不安な気持ちが村を包んだが、簡単に住む場所を捨てることはできない。皆は不安を覚えつつも生き続けていた。数日前にある旅人が、山を越える途中に神社で化け物を発見して逃げてきたことで不安の中の平和も終わってしまったのだ。
「だから熊手を武器のように持っていたのですね。でも、本当に化け物だったら農具では相手になりません」
「化け物じゃない! 私には分かるよ、神霊様で間違いない」
ゼンチェはそう言い張った。アラは少し悩んで提案した。
「この子が強く確信しているし……急いでいますので遠回りはできません。私は山を越えていかなければなりませんので、ついでに確認してきてもよろしいですか?」
ゼンチェは口を噤んでただ不信の目でアラを見つめた。アラは首を傾げた。この子はどうして初めて見たはずの私をこんなに警戒しているのだろう。
*
小さい山だからか平坦な道だった。人々の足跡で作られた小道を辿って山を登りながらアラは白に問いかけた。
「神霊様が去ったことが理解できません。ヌシ様は根付いた巨木のような存在ではないのですか? ヌシは人間より遥かに長い歳月を生きながら、その地に平穏と富を与える……今までそう思っていました」
//人間は自分の理解の範疇を超えているものを崇拝する傾向があるからのう。霊獣たちもただの生き物じゃ。古木と山、崖は去りようがないが、霊獣は危機を感じ取ると住処を捨てて去ることもあるのじゃ//
「危機ですか……では、このことも魔族の影響かもしれません。被害を受けているのは、人間だけではなかったのですね……」
……ひっそりとした山道をしばらく歩いたら神社が見えてきた。村の大きさに相応しい小さな神社の立て札には、アナグマの象徴が描かれている。
神社に近づくにつれて違和感を覚えたアラは立ち止まった。不自然な風を感じたのだった。風が地面に沿って流れるように吹いていた。まるで水のように。
アラは早速頭上を確認した。枝や葉は動いていない。アラの髪の毛もなびかなかった。山を登ってかいた汗もそのままだった。
//これがあの『化け物』の能力じゃろう。気をつけろ。わらわが確かめる//
「はい。……どうですか? 魔族ですか?」
//魔族ではない。が……ここのヌシではない他のものが居座ったようじゃな//
//……! 避けろ!//
シューッ……!
いきなり鋭い風の音がした。アラは白の警告のおかげで辛うじて避けた。
「ジャアア!」
生き物の甲高い鳴き声。アラは周りを警戒しながら音がした方向を見た。そこには……
「あらま……これは……」
「とても……かわいいです!」
//フン、イタチじゃな。まだ未熟な子イタチじゃ//

とても小さな白いイタチの霊獣が毛を立たせてアラを警戒していた。
「本当に小さいですね! 子霊獣様ですか? 霊獣様も子どもの時期があったのですね」
「霊獣様、はじめまして。霊獣様を攻撃しに来たわけじゃありませんので、落ちついてください」
白いイタチは匂いを嗅ごうとするかのように、アラが差し出した手に口先を近づけた。白は奇妙な予感を感じた。
//アラ! 気をつけるのじゃ!//
「いたっ!」

あっという間のことで避ける暇もなかった。白いイタチはアラが差し出した手の甲を引っ掻いて4歩ほど後ろに退いた。引っ掻いた後は徐々に赤くなり、すぐに血が滲み出た。
周りの風がまた荒くなった。木や岩、神社の隙間風から恐ろしい風の音がした。白は直感的に白いイタチの能力はアラに危ないと判断した。
//見境なくでしゃばる奴じゃの! 愚かなものめ!//
「シャアア!」
白が力を解放して威嚇すると、白いイタチがハッとして退いて神社の裏側に逃げた。
//あの子イタチから妙な力を感じたのじゃ。詳しくは分からぬが//
「そうですか? それより、足の動きが変でしたね。足をケガしていたみたいです」
「一応……化け物じゃないと村の人に伝えましょう」
アラは真っすぐ村に戻ってこの事を伝えた。ゼンチェはアラが約束を守るために戻ったことが意外だったのか、目を丸くした。
「首都を攻撃した化け物じゃなくてよかったが……とにかく、人を襲ったのなら退治するしかないな」
「攻撃ですか? ケガは大したことありませんが」
アラは無意識的に手の甲を後ろに隠したが、もう遅い行動だった。
怪我自体は猫に引っかかれた傷よりも小さかったが、何故か治らずに未だに血が少しずつ滲み出ていた。
「小さい傷だからと軽く思ってはいかん。霊獣でも人を襲った瞬間から神聖も何もないもんだ。やはり放っておけない」
「主とも大変なことになってるみたいだし、首都にこれを伝えても何にも解決できないんじゃないかしら?」
「やはり大きな村へ行って人を探してみるしかないだろう。金はかかるが、これが最善だ」
アラは人々がまた深刻な顔で話し合っているのを見ながら苦々しく手の甲の傷をそっとなぞった。自分が口を挟むことではない。
アラも小さな頃、似たような話を聞いたことがあった。隣の地域で霊獣が荒くなったために、武家であり霊獣を封印したことがあるハーン家に討伐の参加を要請する手紙が届いた。霊獣と戦うことをおかしいと思ったアラは兄に理由を聞いた。成年ではなかったが、家の長男として要請に応じてそちらへ向かう準備をしていたアレンは、しばらく考えた後にこのように答えた。
「世の中には善良な霊獣様がいるわけではありません」
あの時もこれと同じ理由で霊獣を討伐したのかもしれない。
「しかし、まだ小さい霊獣でした。人間を害する邪悪な霊獣だと決めつけるにはまだ早いです」
//……その辺にしておけ。あの人間たちの判断が正しいのじゃ。そなたが関与することではない//
//言ったじゃろ? 霊獣も生き物じゃ。人と共生するものは神霊や神獣の扱いをされるが、人を襲い始めれば話は別じゃ//
「でも……」
アラは村人を説得した。
「あの、白いイタチの足にケガがありました。そのせいで、神経質になっているのかもしれません」
「ならいいですけど……もしそうじゃなかったらどうします?」
「……私はこの姉ちゃんの話に賛成」
ゼンチェが前に出てアラの肩を持った。アラは自分を警戒していたゼンチェがそのような態度を見せたことに少し疑問を抱いたが、一応次の言葉を待った。
「どうせ他の村に行って退魔師を探しても時間がかかるでしょ? この姉ちゃんに任せてみようよ! あの、姉ちゃん! 私について来てくれない? とりあえず手を手当てしてあげるから」
*
ゼンチェはアラの手の甲をあちこち見回して深刻な顔をした。アラはそんなゼンチェを安心させた。
「心配しないでください。深い傷じゃないのに止血できないのは少し変ですけど、これくらい放っておけばすぐ治りますよ」
「ふむ……そんな傷じゃないと思うよ。お祖母ちゃんに聞いたことがあるんだもん」
ゼンチェは部屋のあちこちから干し草や花、草の根などを持ってきて、すり潰して作った軟膏を塗った。包帯を巻く時に少し手伝ってあげたけど、歳の割には手先が器用な子だった。薬を作って包帯を巻いている間、ゼンチェはアラの顔を伺っていた。たぶんすまない気持ちがあるとか、何か頼みたいとか、その両方だろう。アラはわざと優しく声をかけた。
「手当てしてくれてありがとうございます。ゼンチェのお家は薬屋なのですか?」
「そうじゃないけど、それもやってる! あ、これもあげるよ!厄除けの首輪だよ」
ゼンチェは自分の指輪を外して怪我したアラの手の甲に付けてあげた。白はゼンチェの指輪をじっと見つめた後に一言言った。
//……妙な物じゃな//
「この指輪がですか?」
//ああ、呪い除けじゃ。そなたの傷には余るものじゃな//
「それ、外しちゃダメよ。神霊様に祟られたら傷が治らないのよ。軽い傷もちゃんと治療しないといけないの」
「ありがとうございます。ゼンチェはいろいろ知っていますね。それもお祖母様から教わったのですか?」
「へへ、うん! 家は神霊様を長くお祀りしたの!」
ゼンチェは誇らしげにそう言った。多分、そのことはゼンチェの誇りなのだろう。
「すごいですね! 実は、私の家もそうなのです。九尾の狐の霊獣様をお祀りしていました」
「本当に!?」
「ふふっ、はい。私たち、共通点が多いですね。私もゼンチェと同じように、色々助言してくれるお祖母様がいます。怖い時も多いですけど、でも、優しい方です」
少し不機嫌になった白を感じたが、アラは気にせずに色んな話をした。ゼンチェはアラの話に警戒を解いてにっこりと笑った。
「なんだ~そういうことだったのね。姉ちゃんが悪い人じゃなくて良かった」
「あのね……ゼンチェが姉ちゃんのケガを治してあげたでしょ? 姉ちゃんも神霊様を助けてあげたいって思ってるでしょ?」
アラは大きく頷いた。
そう言い出したものの、ゼンチェはしばらくためらいながら自分の指を弄っていた。
こんな時は先に切り出してあげないとね。
「あの……詳しくは言えませんけど……」
アラは自分がどうして白いイタチの霊獣を助けようとしたのか、ゼンチェに正直に言ってあげることにした。全てを言ってあげる必要はないから一部だけ。
「私は家の事情で故郷を去って旅をしています。そして、そのことは……北部帝国の混乱とも関係があります。この山の神霊様が去って、新しい神霊様が現れたことも私の家にあったことの影響かもしれません。もし、そうだったら私にも責任があります。」
「だから、言ってください。私は力になってあげたいです」
「……」
ゼンチェはアラを射抜くような目でじっと見つめた。そして、困ったような顔で頭をポリポリ掻いた。
「姉ちゃんが言ってること、よく分からない。でも、神霊様がいなくなっちゃったのはそれと関係ないと思うよ」
「はい? ゼンチェはアナグマの神霊様がここを去った理由を知っているのですか?」
「うん……。お祖母ちゃんは言わないでって言ったけど……姉ちゃんも秘密を言ってくれたみたいだし、私も教えてあげるよ」
「この山を守っていた神獣様は去るべくして去ったらしいよ」
「去るべくして……?」
「うん。歳をとった獣が群れを去って姿を隠すことと同じく……自然なことだとお祖母ちゃんは言っていたよ。長い時間ここを守ってくれた方だから悲しむことではないって」
「でも、他の皆が知ったら怯えてしまうから他の人には言わないでって止められてたけど……えへへ、結局知られちゃった」
(魔族のせいではなかった……幸いというべき……でしょうか?)
「あのね、神霊様が去ったのに新しい神霊様が来たのは本当に不思議なことだよね! 運命みたい!」
「だから、どうにかして新しい神霊様を手伝ってあげたいの。お祖母ちゃんがいなくて一人でどうすればいいのか分からなくて、戸惑っていたけど……姉ちゃんが助けてくれればなんとかなるかも」
「これは私の考えだけかもしれないけど、神霊様はまだここに慣れていないみたい。神霊様に好きになってもらいたいよ……」
ゼンチェの声がだんだん小さくなった。多分、話しているうちにアラの家の事と今回の件が関係ないことを気にしてしまったのだろう。
//どうするつもりじゃ? 話を聞いてみれば、この事はそなたの兄とは全く関係のないことのようじゃが//
「しかし、頼まれたことですし……」
顔色を伺いながら焦っている子供のお願いを断れるほど、断固になれる自信がなかった。何より、神霊様に好きになってもらいたいと言ったのが心に残った。
"でも、ここを好きになれるように努力しています"
アラはゼンチェの両手を自分の手で包むように重ねた。
「私もゼンチェがいるこの村が好きです。神霊様にも好きになってもらえるように頑張ってみます」
「本当に? 本当だよね?」
ゼンチェがいきなり飛び上がってアラに抱きこんだ。後ろから鼻で笑っている白の気配がしたが、アラは悪くない選択だと思った。
*
「……キャッ!」
ガチャーン!
アラはまた大きく転がりながら神社の外に追い出された。尻もちをついたアラが痛くて呻いていたら、白がこれで6回目じゃ、と言った。
白いイタチの霊獣は白に怯えてアラにそれ以上の危害は与えなかったが、近づくことを許さなかった。
//言葉が通じなくとも、固く拒否されていることは3つの子供でも分かるじゃろうな//
「そうですね……しみじみと伝わってきます」
休憩がてら昼ごはんのために神社から少し離れた岩に座ったアラは、ゼンチェと一緒に作ったおにぎりを取り出した。デコボコのおにぎりを大きく頬張ると、ジャリッと脆い石みたいなものが砕けてしょっぱい味がした。溶けなかった塩だった。これはゼンチェが作ったおにぎりだったようだ。
味もバラバラ、大きさもバラバラ。だけど、ゼンチェが自分のために頑張って作ってくれた事を知っているアラは、胸がいっぱいになった。水が飲みたくなるのはしょうがないことだ。

「……んむっ、(ゴクリ)話してみたいですが全然聞いてくれませんね。これからどうすればいいのでしょうか」
//放っておいてここを去ればよい//
「それだけはできません」
//そなたの手で倒せばいい//
「それもいけません」
//ならば、わらわが教えてやれる方法はない//
「……それも困ります」
ご飯を食べているのにどんどん力が抜ける気がした。アラはしょっぱくなった唇を舐めながら唾を飲み込んだ。
「ゼンチェのことが気になります」
//ご飯の塩のことか?//
「それじゃありません! 白様、聞いてください。霊獣様の立場では私はかなり威嚇的な存在だと思います。身長よりも長い槍を持っているし、側には千年を生きた狐様もいますので」
「なのに、何回も煩わしくしたのに神社を去る気配がしません。私のことを厄介者だと思って、白様に怯えてすぐここを去ると思いました。人間を害するつもりだったら最初から民家で騒ぎを起こすはずなのに……そんなことはしなかったんですね。一体なんでしょうね」
//わらわも納得できぬが。構ってほしがっておるのじゃろう//
「え?」
//そうでなければ、わざわざ神社に居座る必要もなかったじゃろう。あそこはこの山の中で最も人間の匂いが濃いところじゃ//
「あ……確かにそうですね! ますます分からなくなりました。実は人間が嫌いなわけではないのかも……」
//それよりも、奴が発している妙な力が気になるのじゃ。あれと似たような力をどこかで感じたことがあるのじゃが……//
「妙な力……? 普通の霊獣様となにか違いますか?」
//それはない。じゃが……//
アラと白が考えているうちに、白いイタチが神社の外に顔を出して鼻をクンクンさせた。
「あら」
……そして、アラを見てまた神社の中に入ってしまったのだった。
「おにぎりの匂いを嗅いだのでしょうか? 霊獣様もお腹が空いたようですね」
//良かったのぅ。食い物で誘き出せば捕まえれられるぞ//
「うーん……しかし、それは騙すということですよね。そんなことをしたら霊獣様が本当に人間を嫌いになってしまいそうです」
アラはおにぎりを包んだ風呂敷を綺麗に広げてその上におにぎりを置き、神社の門の前に置いた。そして距離を置いて後ろに座って合掌した。
//何をしておる?//
「供養です。神獣様に差し上げる時はやっぱりこうしなければ!」
//余計なことを。また奴の風に吹き飛ばされるわ//
幸い、白いイタチは白の予想に反してアラを攻撃せずにおにぎりだけに興味を示した。アラはハッとした顔で口を開けた。
「ゼンチェが作ったおにぎりは除けた方がよかったかも……。しょっぱいから……お腹を壊したりはしませんよね?」
//しょっぱかったら自分で水でも飲むじゃろう。あんなに栄養のないもんを急いで食べるほどだし、随分と腹が減っておったようじゃのぅ//
しばらく白いイタチが食べる姿を見つめていたアラの目に、ふと奇妙なものが写った。
「白様。あそこ、ケガがある足の周りに黒青いシミのような何かがあります! 白様が仰った妙な力って、まさか……?」
//……ほぉ、そうじゃな。やっと分かったのじゃ。あれは魔族の匂いじゃ//
「魔族!?」
//ああ、今までよく分からなかった理由も分かった。魔族の匂いと気づかないほどに薄い。あれは恐らく、魔族がかけた呪術……みたいなものじゃろう//
「そんな……足のケガも魔族の仕業かもしれませんね。可哀想に……」
残念に思いながら無意識に口元に手をかざそうとしたアラは、ゼンチェからもらった指輪に気づいた。
「……白様? この指輪が役に立ちませんか? 呪い除けですよね?」
//どんな呪いなのかが分からぬが……指輪の力はなかなかに強い。多分効果はあるじゃろう。それより、できるのかい?//
//それを奴の首にかけるのは無理じゃないかい?//
「効果があるなら、やってみるしかありませんね。さてと、猫の首に鈴をつけてみましょうか?」
*
全てを終わらせて帰る頃には、日が沈み始めて空が綺麗な橙色に染まる時間にだった。朗報を持って村に帰ったアラは、村の皆にすべて解決したと伝えた。
「呪いの詳しい内容は分かりませんが、それが神霊様に影響を与えていたようです。ゼンチェがくれた指輪をかけたらすぐに大人しくなりましたよ」
「しばらく自分が何をしていたのかよく分かっていないような様子でした」
「それからは邪悪な力も大分消えましたし、山の風も穏やかになりましたのでこれで安心して山に入れると思います」
村人たちも山の風が穏やかになったのを確認して嬉しそうにお礼を言った。ゼンチェも嬉しそうな顔をしたが、乱れた姿で擦り傷だらけになったアラを見て辛くなって小言を言った。
「私の指輪が役に立てたのは良かったけど、姉ちゃんはなんでこんな格好になったのよ!」
忙しくアラの傷を確認しながらゼンチェが頬を膨らませてため息をついた。
「すごい擦り傷だね。それに砂まみれになっちゃって……でも、最初の傷とは違ってただの傷でよかった。すぐに治りそう!」
「前に負った手の甲の傷が治らなかったのは、祟られたからでしたよね。では、今回の傷が大丈夫なのは神霊様が元の状態に戻ったからですよね? よかったです!」
「よくないの! 頼んだのは私だけど、ここまでするとは思わなかったよ。ふぅ、神霊様も辛くてそんなことをしたんだね。退魔師を呼ばなくてよかった」
「姉ちゃんがちょうどここに来てくれてよかったよ。神霊様が機嫌を損ねないように助けてくれてありがとう」
「とんでもありません。お役に立てて何よりです」
そろそろ日が暮れる時間だったが、村で夜を過ごすつもりではなかったアラは出発することにした。見送りにちょろちょろついてきたゼンチェは嬉しそうにペチャクチャしゃべった。
「あの、神霊様が私が作ったおにぎりが美味しく食べてくれたの? また作ってお供えしたら嬉しく思ってくれるかな?」
アラはゼンチェのおにぎりを口いっぱいに頬張って神社の後ろへぴょんぴょんと弾んで逃げた白いイタチの姿を思い浮かべた。それはとても愉快な光景だった。

「きっと嬉しく思ってくれるはずです。あ、味は薄くした方がいいですよ」
一足遅れて白いイタチの健康が心配になったアラは一言付け加えた。
「さぁ、ではさよならですね。今まで楽しかったです。どうか元気でいてください」
お別れの時間が来た。一日で仲良くなったアラとゼンチェは明るく別れの挨拶を交わした。
アラはもう何度も登った山の入り口に再び足を運んだ。今回ここを去ったら二度と戻ることはないだろう。名残惜しくて後ろを振り向くたびにゼンチェは大きく手を振った。
アラが見えなくなるまでそうしているつもりだろう。アラはやんちゃな妹ができたような気分になって、口元で両手を丸めて叫んだ。
「もうすぐー! 暗くなりますので! 早く帰ってくださーい!」
「うん! 帰るよ! 元気に旅してね!」
「狐のお友達とも仲良く過ごしてね! またね!」
その言葉に驚いたアラが足を止めて何回かゼンチェを呼んだ。しかし、ゼンチェは元気よく手を振って帰ってしまった。
*
穏やかになった風が気持ちよく吹いてくる山道を下った。日が完全に暮れる前に下るために、アラは黙々と足を急がせた。
しばらく山を下って、アラがふと言い出した。
「でも、よかったです」
//……なにが?//
アラは大きい岩を超えて下りながら、少し答えを保留した。坂道には岩が多かった。それに、日が暮れて木の影が長くなったので、結構暗くて時間がかかった。
坂道が終わり、しばらく歩いていたアラは静かに答えた。
「新しい住処が神獣様の気に入ったようで」
//……//
「……好きになることも努力が必要でしたね」
「今は故郷を去って旅をしていて……多分これからいろんな出会いがあるでしょう。その中では望ましくない出会いも、ありがたくて楽しくて、これからもずっと繋がりたい人との出会いもたくさんあるでしょう」
「でも……どこにいてもそこを家だと思うことはないと思います。こんなところはお兄様と同じですね。早くお兄様を探したいです」
//……そう言っておる割には、いつも余所見をして時間を無駄にしておるがな//
「はは……最初は魔族の仕業だと思いましたので。もちろん、そうじゃないと知った後にも助けたいと思いました。ゼンチェのお願いを断れなかったこともありますけど……神霊様が寂しそうに見えました」
「小さい頃には友達がいなかったんです。恥ずかしがり屋で心細くって」
「なのに友達が欲しくて、毎日年頃の子供たちが遊ぶ場所を彷徨きました。それでも誰かに遊ぼうと声をかけられたら断ったのです」
//なぜじゃ?//
「なぜでしょうかね。恥ずかしかったこともあるし、仲良くできなさそうで心細くなったこともあるし……複雑です。迷っていたんです」
「私は霊獣様も迷っているかもしれないと思いました」
「つまり……ただ、私がそうしたかっただけです。霊獣様がそんな気持ちだったかどうかは分かりません」
//心は窓と同じじゃな。自分の心の大きさの分だけ見えるものじゃ//
「では、心が広い人にならなきゃ。もっと広く見えるように」
「……そういえば、霊獣様の体にあったあの呪いは何だったんでしょう? ゼンチェを助けたおかげで魔族の呪いだと突き止めることができて良かったですけど……あんなのは初めて見ました」
「魔族と戦うことにはもう慣れたと思っていましたけど、神霊の心さえ乱す呪いがあるなんて……これからは魔族じゃない存在とも戦わねばなりませんか?」
//それは今悩むことではない。先のことは分からぬから今から不安になってもしょうがないのじゃ//
「分かっていても上手くできないですね。こんな時に白様の千里眼があればよかったのに」
//フン、わらわが千里眼を持っていた時でも人間の心配にはキリがなかったのじゃ//
//いつも心配することを心配する情けのない存在じゃ//
「では、心配することを心配しないためにはどうすればいいのですか?」
//目が前にある理由を考えろ。目の前のことだけをすればいい//
(……グー)
その時、いきなりアラのお腹が大きく鳴った。アラは恥ずかしくてヘラヘラと笑ってみせた。
//食うこともそれに含まれるのじゃ。あそこに村があるようじゃな。明かりが見える//
「あら、本当ですね! 明るい時に山を下ったらあそこに村があるとは思わなかったはずです。暗い時こそ見えてくるものがあるのですね。」
//さっきの娘が霊を見る神妙な才を持っていたように、そなたにも才能があったのぅ//
「どんな才能ですか?」
//空腹を満たす才能じゃ。ご飯の時に合わせて村を訪れるのを見ると、とても生まれつきのようじゃのぅ//
「あら! とても役に立つ才能ですね。気に入りました」
//じゃろうな。急げ、遅くなると失礼じゃろう//
「はい!」
明かりに向かって走り出した。勢いよく地面を蹴る体は軽く、頬を過ぎる風はこの上なく爽やかだった。
アラは飛ぶように山道を抜け出した。明かりを抜けて走るその瞬間には、魔族の呪いも、不安な未来も、なにもなかった。
エリシス ストーリー「騎士団長の休暇」
騎士団内の記録保管室。エリシスは本棚に寄りかかって最近起きたことを説明した。
「ハーメルの支援要請を受け入れて赤い騎士団の半数をハーメルに送ったよ。でも、あれだけでは足りないだろう」
「セナスがあんな状況になったことも、今になって支援要請が来たことも到底理解できない……。それにあの支援要請もセナスから正式に入ったもんじゃなかったし……思った以上に危険な状況かもな」
エリシスは黙って返事を待ったが、相手の視線は本に固定されているばかりだ。エリシスは話し続けた。
「以前にも似たような敵と出くわしたことがある。あたしの故郷、ルーベンからそう遠くない森で、完全に同じではないけど似たような奴が現れたんだ。ペイター領には黒い森もあるし、これは見過ごせないことだと思うぞ」
「つまり、根拠は騎士団長の勘だけ、ということですね」

オーウェン・ペルフォード卿は視線を本に向けたまま言った。エリシスは付け加えた。
「ただの勘だけじゃないんだよ。赤い騎士団に、あの時あたしと一緒に戦った人がいるから証言してもらえるはずだ」
「騎士団長の話を疑っているわけではありません。俺が指摘しているのは物証がないという点です」
相変わらず彼の視線は本に向けられたままだ。
「団長の話を聞いて記録を調べています。確かに昔から不気味な力と共に現れた怪物の目撃談や、それらと戦った者は存在したようです」
彼はパタンと本を閉じ、エリシスをじっと見つめた。
「人は過ぎた過去から学ぶと言いますが、今までそれを体現する人を見たことがありません」
「過去を振り返って未来を予想しても、目の前の利益を追います。団長の言う通り、警戒すべきことではありますが、それだけでは上は動いてくれません」
「王国の政情は混乱しています。今は目立つ行動をすべきではありません。大義名分が成り立たなければ、責められるのは団長の方です」
「でもさ……!」
エリシスはオーウェンに反論しようと口を開けたが、すぐ閉じた。彼はエリシスに反対しているわけではない。ただ冷静に助言をしているだけだ。
「……俺自身も一人の騎士として団長を尊敬しています。どうかこの助言を念頭に置いてください」
「……数年前。反乱を計画したクロムウェル家の首謀者は結局処断されましたが、それですべてが終わったわけではありません」
オーウェンは疲れた顔をして低い声で続けた。
「この機会に上に上がろうとする機会主義者に目をつけられたいのですか?」
エリシスは慎重を期することにした。
*
「……そういうわけで、慎重に慎重を重ねて行動するつもりだ」
エリシスは副騎士団長のフェネンシオにオーウェンとの対話を適当に略して伝えた。フェネンシオはオーウェンの言い分にある程度納得したようだ。
「確かにペルフォード卿の言うことも一理あります。つい数年前にブランデルクの反乱が鎮圧された時に、その時の雰囲気が未だに続くとは誰も思いませんでした」
「……」
「状況が状況ですので、ペルフォード卿の心配も分かります」
「フェネンシオ、あたしもそれが理解できないほどのバカじゃない」
不満げにぶつぶつ言っているエリシスを見てフェネンシオは小さく微笑んだ。
機を狙って上にのし上がろうとする機会主義者。自分の上官、赤い騎士団の団長は、そのような人からは一番遠い部類だろう。
「根拠やら、証拠やら、大義名分やら……それが必要なのは知ってるけど、証拠を出せるほど十分に事態が大きくなってからではもう遅いぞ」
エリシスは頭を抱えて考え込んだ。赤い騎士団の団長として同盟国を支援するくらいの権限はある。だが……。
「騎士団長が突然訪ねて行ってそちらに怪しい地域があるから調査します、というのもな……」
悩んでいたエリシスが明るい顔で言った。
「やっぱ正直に言えば気持ちは伝わるんじゃないか?」
「そんなわけありません」
フェネンシオはきっぱりと言い切った。
「ペイターの領主なら要請に応じてくれるかもしれません。あの方は融通の利く人ですので」
「うむ……エルダーの方はよく存じません。団長はルーベン出身でしたね? エルダーの領主はどんな方でしょうか? 要請に応じそうですか?」
「ふーむ……どうだろ? でも、評判はよくなかった気がする。多分ダメじゃないかな」
「そうですか……」
「ぐぐぐ……せめて闇の森と黒い森だけでも調査できれば……! この二箇所が一番怪しい場所なんだ」
「黒い森は知らないが、闇の森はよく知ってる。広くもないし、一人で十分調査できる。黒い森も、ペイターの駐屯軍が常に神殿に待機しているから、調査にそんなに時間はかからなさそう。人手もそんなに必要ないだろうし……」
「あーあ、父上が自由騎士になった理由が分かった気がする」
力と地位にはそれ相応の責任がついて回るもの。騎士団長という地位に足を引っ張られたエリシスは鬱陶しくなった。
「お疲れのようですね。団長には休暇が必要です」
エリシスはフェネンシオを睨みつけた。
「フェネンシオ、お前一体なにを言ってるんだ? これは危機だぞ?」
それでもフェネンシオは笑顔のまま休暇を勧めた。
「故郷にお戻りになって少し気晴らししてください。ついでにペイターに寄って駐屯軍の指揮者に私の手紙を渡してくれませんか?」
やっとフェネンシオの言っている意味が分かったエリシスはその芝居に付き合ってあげた。
「……あ、そうだな。そろそろ弟のところに行かなきゃな。それがさ……理由は……」
言葉に詰まったエリシスをフェネンシオが助けた。
「支援を要請したハーメルの貴公子が弟さんと同じ年頃でしたね? ずいぶん会ってないのだから、それは会いたくなることでしょう」
「そうそう! あいつ、元気にしてるかな? 気になり始めたら止まらなくってさ」
その後は簡単だった。エリシスが騎士団の指揮権を副騎士団長のフェネンシオに一任してハーメルに行くことを指示し、荷造りをしてベルダー王国を離れるまで半日もかからなかった。
*
「こんなのは……初めて見たな。どうだ?」
レントとアレグロは深刻な顔をしていた。彼らが見ていたのは、レントが確保してきた魔物の死体だった。
魔物の死体に残った魔力を読み取ったアレグロは小さくため息を漏らした。掌に宿った淡い光も間もなく消えた。彼はおずおずと頷いた。
「はい……私もこんなものは初めて見ました。森の魔気が強くなりましたね。これほど強いのは初めてです。森に何か問題があるようで心配です。こんな状況だし、神殿の警備にも気を遣わなければなりませんが、余裕が……」
「おっとと、それは大変だな! よかったらあたしにも手伝わせてくれないか!?」
「はっ!?」
「うわっ、驚いた……! ぼ、冒険者さんですか? ここは危険です。ありがたい提案ですが……」
「あっはは! まぁね、今は冒険者だけど」
「まさか、燃えるような赤色の髪、そしてその剣……。もしかしてあなたは……赤い騎士団の団長、エリシス様でしょうか?」
「赤い騎士団の団長様……?」
「大変失礼いたしました。ペイターの近衛騎士、レントと申します」
「も、申し訳ございません。騎士団長様だとは知らず失礼を……アレグロと申します」
「いいのいいの、気にするな。アレグロ、君もペイターの兵士か?」
「私はペイターの書記官です。最近黒い森から出現したモンスターの数が増えたと報告があり、領主の命令で視察に来ました」
「そっか……実際に黒い森に異変があるとは色々大変だな」
「『偶然』この状況を知ったけど、ベルダー王国の騎士として王国の危機になりそうな件を見て見ぬふりはできないな。あたしにできることはないか?」
「はい? ああ……もちろん、協力してくださればとても助かります」
黒い森の調査に参加したい動機を述べるために蛇足が多くなったエリシスの話にレントは首をかしげたが、すぐ頷いて彼女の協力を許可した。エリシスは口角を上げた。
「よっし! 何でもやらせてくれ!」
*
一人で黒い森に入ったエリシスは、魔獣たちと戦いながら以前とは明らかに違うと感じた。
「闇の力が濃くなったな。魔獣たちもまた強くなったし、暴れている。舐めちゃいけない。あたしも気をつけよう……」
そう言った途端、エリシスの足に何かがぶつかった。それを無意識に吹っ飛ばしたエリシスは驚いて大声をあげた。
「うわっ! なんだこれ!!」
エリシスは素早く自分が蹴っ飛ばしたものを確認した。土ぼこりを立てて転んだのは一冊の本だった。
「なんだこの本……? デカいな。一体誰が黒い森まで入ってきて本を捨てたんだ? 変わった奴だな」
無意識のうちに本を開いて内容を確認したエリシスは嘆声をあげた。
「あ! この本知ってる。これ、エリアン王国の建国王の小説じゃん! いやぁ、久しぶりだな。小さい頃は毎晩飽きずに読んだっけな」
建国した後の話はつまらなくて寝てしまったせいで後の話はよく覚えていなかったが、エリシスはその本を見てとても嬉しくなった。古い本だったけど、意外と状態は悪くなかった。
「やっぱ、また読んでも前半の部分は面白いな! 特に建国の前に初代王がモンスターを討伐する部分! あたしもこんな英雄になりたかったなぁ」
「どれどれ……首無しの騎士、急襲するワイバーン……ゴーレムの王、堕落した植物たち」
「……ちょっとでたらめな話だけどな!」
久しぶりに子供の頃に大好きだった本を見て嬉しい気持ちになったエリシスは少し悩んだ後に元の場所に本を戻した。本の形で地面が掘られてすっぽりと入った。
「あたしは忙しいから君は元の場所に戻れ」
エリシスは闇の力が濃く感じられる方向へ進んだ。
ドーンッ!
大きな岩が地面に突き刺さった。エリシスは間一髪のところで岩を避けて何度か転んだ。
「おっと……!」
「危なかったぁ。あんな奴は初めて見たな」
エリシスは巨大なゴーレムと向き合って構えた。
「あんな奴が黒い森にいるとはな……モンスターたちが黒い森の外に飛び出して来たのはこいつが原因だったかもしれないな」
ペイターの駐屯軍に知らせなければならない。エリシスが様子を見て退こうとする気配に気づいたゴーレムは、そうはさせないと言わんばかりに拳を飛ばして地面に突き刺した。
「は、逃げさせてくれないんだ。いいぞ、私が終わらせてやる」
「こいつ……硬くて刃を跳ね返しそうだけど、どうすればいいんだ?」
ゴーレムは魔法でつくられたもの。魔力を供給する装置や魔力が込められた核を壊せば無力になる。しかし、核がゴーレムの内部に隠されている場合は壊しにくいから、魔力が供給される部分を攻撃して遮断すればいいと聞いたことがあった。例えば、腕の関節を攻撃すると魔力の供給が途絶えて腕の下の部分が無力になる。あくまで理論上では。
「それが理論と違って難しいことだったんだ。今分かったな」
それに、あのゴーレムはなんとなく生命体のように感じられた。生きて呼吸する感じじゃなくて、敵を明確に認識して、攻撃しようと考えて動いてるような感じ? 一体誰がこんなものを作ってここに置いたんだろう?
「ゴーレムの王……」
つぶやくエリシスの頭にパッと何かが思い浮かんだ。エリシスはあ、と言いながら起き上がった。
「それだ! 建国王の一代記で見た奴だ!」
しかし、エリシスの記憶にある内容では、建国王が相手にしたのは魔法使いが作った動く岩の人形なんかではなかった。
魂にゴーレムという肉体を結合した死霊体の一種。そしてそれを統率して操る怒りのゴーレムの王……。
「暴君ティーチ!」
エリシスは快哉を叫んだ。
「ということは、小説じゃなくて実際に存在する奴だってことだよな? 建国王が相手にしたモンスターたちは!」
エリシスは剣を握り直して構えた。
「攻撃する場所がはっきりとわかったぞ!」
*
ペイターの駐屯地に戻ったエリシスをアレグロが心配そうな顔で走って迎えに来てくれた。
「騎士団長様! 戻りましたね! 一人で行かせてずっと心配していました」
アレグロは何かもっと言おうとしたが、エリシスが差し出した宝石を見て口を閉じた。その宝石に宿った闇の力を感じたのだ。
「これは……?」
「ある強いモンスターの体にあったんだ。ここから感じられる力、ただの力じゃないと思って持ってきたけど……これが何だか分かるか?」
用心深く宝石を受け取って観察していたアレグロの表情が段々と暗くなった。
「そんな……。これは……エルの欠片だと思います」
「え? 違うよ。似てるけどエルの欠片ではないと思うぞ。ルーベンのエルを見たから詳しく知っている」
「もちろん、皆が知っている普通のエルの欠片とは違います。これは……エルの欠片を闇の力で染めたものです。だから違うところがあるんです。どうしてこんなことが……黒い森の魔気のせいでしょうか?」
「原因は分からないが、これのせいで黒い森の怪物が暴れたのかもしれないな」
「そうかもしれません。形質が変わってもエルの欠片はものすごい力を持っていますので」
「これは私が浄化できそうです。任せてください。お体は大丈夫ですか?」
「え? あたし?」
「はい。並の力ではありませんので、これを持ってくる間に異常が現れてないか確認した方がいいです」
「異常はないみたい。心配するな! あたし、結構丈夫だからな」
「とにかく、これで一段落できたようで安心だ。でも、これから黒い森の警戒にもっと気をつけた方がいいな。森を監視する兵力も増員するといい」
「お帰りですか?」
「ああ。あ、そうだ! 念のためだけど……あたしがここに来たことは誰にも言うなよ」
「はい?」
「あたしは『通りがかりに偶然』ここに来ただけだからさ。分かったろ?」
「ですが……本当に大丈夫なのですか? 騎士団長はこの件の……」
「……あ。かしこまりました。ご協力いただき、誠にありがとうございます。冒険者様」
「ははっ! ああ、ありがとう」
「あ~これ、お別れのプレゼントだ」
「はい? プレゼント? ……うあっ!」
アレグロはエリシスが投げた本をとっさに掴み取った。本の重さにアレグロの腕が下に伸びてしまった。
「これは……エリアン王国の創世神話……? 待って、これ初版本じゃないですか!?」
「それ重要なこと? とにかく、持っていれば役に立つ時が来ると思うぞ。あたしも参考にした」
「はい? はい……ありがとうございます」

「ではこれで……あ、そうだ。これがあったんだ。どこに入れておいたっけ……」
「それはなんですか?」
「大したもんじゃない。うちの副団長が君に渡して欲しいと頼んだ手紙だ」
「じゃあ、これで本当に行くぞ! さよなら!」
「わ、渡してくださってありがとうございます……? ……お気をつけてお帰り下さい」
遠ざかるエリシスの後ろ姿を見ていたアレグロがレントのほうを向いて聞いた。
「赤い騎士団の副騎士団長と知り合いでしたか?」
「いや……全然」
レントは手紙を開いて読んでみた。視線が内容を追って上から下に動いた。読み終わった後にも訳の分からない顔をしたまま手紙を繰り返し読んで、後に何かないか確認した。それを見たアレグロはレントに質問した。
「何と書いてあったんですか」
「ただ……お疲れ様です、これからも頑張ってくださいみたいな言葉が派手に長く表現されている。それだけだが……一体なんだ? 他に重要な内容はなかった。もしや何か隠された意味が……」
真剣な顔で悩むレントにアレグロはギクシャクした笑顔で笑った。
「あははは……どうでしょうかね。隠されているのはたぶん……」
「名目作りでしょう」
*
一件が片付いたからか足が軽くなった気がする。エリシスは歩きながら伸びをした。
「でもまだ心配だけど……警告もしてやったし、しばらくは大丈夫だろうな。じゃあ、そろそろ闇の森に行ってみるか。久しぶりに家に帰れる」
「エルスの奴は元気にしてるかな~! あたしがいない間、修練を怠ける奴じゃないから、今回行ったらどれだけ成長したか分かるだろうな!」
大きく伸びをしたエリシスはルーベンに向かった。
弟の冒険が始まったこと、そしてこれから幕を開ける大冒険の兆しには、まだ気付く由もない。
アイン ストーリー「神官と共存の祝祭」
盗まれたエルがルーベンに戻ってきて間もなく、ルーベン村は共存の祝祭の準備で騒がしくなった。
エルダー領主の背任で祝祭に必要な物資の普及が遅れたため、エル捜索隊も修練の代わりに祝祭の準備を忙しく手伝っていた。
レイヴン「じゃあ、薪は俺が割ってくる」
エルス「一晩中火をつけておくんだから薪はいっぱい要るだろ。オレも行く」
アイン「……」
(カサカサ)
アイン「エルス、気になることがあります」
エルス「うん? 何だ?」
アイン「エル捜索隊はなぜルーベンにしか存在しないのですか?」
エルス「えっ、なんでルーベンだけにあるのかって?」
アイン「はい、エルを復旧することは何よりも大事なことなのに、エルダーとベスマにはなかったような気がします。他の地域にはないのですか?」
エルス「さぁな、他の所にもあるかどうかよく分かんないんだよな……」
レイヴン「ルーベン以外には、ないと聞いている」
アイン「どうしてですか? エルを復旧することはもう重要ではないのですか」
レイヴン「そういうわけではない。詳しいことは分からないが、エルの所有権の問題が絡んでいるらしい。エルはベルダーだけのものではないからな。王国の他の地域にもエル捜索隊は存在していたが、成果を上げられず徐々に縮小されて結局ルーベンにしか残っていないと聞いたことがある」
アイン「所有権と成果の問題ですか……」
アイン(女神から授かったエルを巡って争って、成果で序列付けをしたというのか。愚かで情けない)
レイヴン「しかし、驚いたな。俺もエルのことは聞いたことがあるが、これほど小さかったとはな……エル捜索隊が今までどれだけ頑張ってきたのか分かった」
エルス「だろー? 共存の祭りの前にエルの欠片を取り戻すことができて本当によかったぜ!」
アイン「……」
エルス「話しながらやってると効率いいな。薪がもうこんなにたくさん積もったぜ」
レイヴン「そうだな。お前たちは薪を持って先に村に戻れ。俺は……後でついて行く。薪は多ければ多いほどいいからな」
エルス「あっ、待てよ……!」
エルス「……気楽に村に行ってもいいのにさ」
アイン「あの、エルス。悪いけどもう一つ聞いてもいいですか? 祝祭には必ず参加しなければなりませんか?」
エルス「え……? 必ず参加?」
アイン「共存の祝祭に必ず参加しなければならない、という掟があるわけではないですよね。ルーベンのエルを取り戻してきましたが、これで満足するつもりではありませんよね? エルを完全な姿に戻すために懸命に動かなければなりません」
エルス「そりゃそうだけど……そこまで急がなくてもいいんじゃね?」
アイン(急がなくてもいいと?)
アイン「エルス、エルを自分勝手に使おうとする人たちを見ましたよね? ナソードも同じです。エルが暴走したのはナソードの影響も少なくありません。彼らの動力源がエルの力なのですから。
私たちがこうしてのんびりしている間、アルテラで見たあのナソードたちや他の誰かにエルを狙われれば面倒なことになるでしょう」
アインはもどかしい気持ちを抑えながらエルスを説得してみたが、エルスはそんなアインの気持ちを全く分かってくれなかった。
エルス「でもさ、それは人間も動物も一緒じゃね? 皆エルのお陰で豊かに生きられるじゃん。ナソードはエルを使い切る程いっぱいいる?」
アイン「そうでは……ありませんが。ナソード戦争もナソードの数が増えすぎたことが原因ですし……アルテラ島で見た限りではあれほど勢力を増やすことは難しいでしょう」
エルス「じゃあ問題ないな!」
アイン「それは違います」
エルス「なんで?」
アイン「先ほども聞きましたよね。エルの所有権に関する話を。
エルを特定の国や地域が所有するなんてとんでもない話です。エルは女神から授かったものですから」
エルス「エルがどこにあるのか……そんなに重要なことか?」
アイン「それはもちろん……。……はい?」
エルス「女神から授かったもんだったら、エリオスにあるだけで十分だろ? エリオスのどこにあるのかはどうでもいいことじゃん」
アイン「そんな……エルス。エルスはエルを復旧する気が無いのですか?」
エルス「そういう意味じゃなくて。エルを元に戻すのはぜってぇ必要なことだけどさ! 人からエルを無理やり奪うことはしたくないってことだよ」
アイン「エルス、違う。それは……」
アイン「……」
アイン(放出したエルの力を循環させようとする人間たちの意思は理解できる。しかし、なぜ不完全なエルの力を循環させることが、少なくなったエルの力を完全に元に戻すことよりも優先されているのだ?)
アイン(エルスはこの重要性を分かっていない。どうすれば理解させられるだろうか……)
アイン「……分かりました。ではエルス。一つだけ約束できますか? 共存の祝祭が終わったらすぐにエルを取り戻しに行くのです」
エルス「もちろんだぜ!」
アイン「はぁ……」
アイン(ああ、人間たちは弱いからこんな休息の時間が必要なのかもしれない。彼らとともに行動すると決めた以上、彼らに溶け込むためにも焦ってはいけない……)
*
村に薪を渡したエルスとアインはしばらくの間周りを見渡した。村人たちが祝祭の準備で忙しくしている中、レイヴンが気まずそうに混じっていた。
エルス「状況はどう? 良くない?」
アン「大変よ~! 食べ物も足りないし、服の生地もまだ来てないの~。作れる時間あるかなぁ……」
アイン(こんな状況で無理してまで祝祭を執り行う必要があるのか? 理解できない)
ロウ「だが、いいこともある。これくらいあれば自分たちが食べるには十分だろ? 盗賊たちに略奪された村もあるらしいぞ」
アン「でも、前回と比べたら形だけ真似したものだから~とても残念よ。特に小麦粉とお肉が足りなくてパイは十分作れなさそうで……」
レイヴン「……!」
アンとロウの話を聞いていたレイヴンは困ったような顔でこっそりと森の方に向かって行った。
エルス「レイヴンの兄貴はまたどこに行っちまったんだ? 来たばっかなのに……」
アイン「多分こんな略奪の話は気まずかったのでしょう。ハーフナソードさんはブラッククロウ団の団長として活動していたことがありましたから」
エルス「ふーん」
エルス「とにかく……果物はいっぱいあるからそれでパイを作ろう。肉はシチューにして……そうすれば量はそこそこ足りるだろ」
アン「でも、祝祭の衣装は?」
その時、村の入り口がざわついた。荷馬車がルーベン村に入ってきたようだ。
アイン「あ、魔法使いさんが戻ってきましたね。どこへ出かけてたんですか?」
アイシャ「ふぅ。ちょっとエルダーに行ってきたの! 散々苦労したけどようやく間に合ったのよ」
アン「ちょうどいいところに~! ふぅ、衣装の準備ができなさそうでソワソワしてたのよ~」
ハガー「間に合ったのは良かったが、急がんと。今日はジャンジャン働く日じゃの」
アイシャ「私も手伝う! 裁縫なら自信があるから!」
エルス「そんなこともできんのか?」
アイシャ「何よその反応は! 流浪生活が長いからこれくらい簡単なのよ~。
ところで、この私が手伝ったとしても服作りには人手がかなり必要なんじゃないの? ……ふうん……。料理のほうは大丈夫?」
エルス「問題ないぜ! 料理は布地が遅れることを想定して前もって準備しといたんだ!
料理はオレが手伝うから祝祭が始まる前に終わると思う」
アイシャ「へぇー、エルスが料理するの? それこそ意外じゃん。食べられるの?」
エルス「何が意外だ! おい無視すんな!」
アイシャ「はいはい、食べ上手だから料理も上手じゃないとね。じゃあ、料理のほうは解決として……。服を作る人を決めないと。アイン、良かったら手伝ってくれる?」
アイン「私ですか? まぁ、いいですよ。一度もやったことありませんが、大丈夫ですか?」
アイシャ「大丈夫よ。作り方さえ分かればそんなに難しくないの」
アイシャは意気揚々とした顔で布地の上に型紙を載せ、それに合わせて線を引いていった。アインはアイシャの手がてきぱきと布の上で動くのを見つめていた。
アイシャ「この生地を寸法に合わせて切ることからやってみよっか。この作業は裁断と言います」
アイン「裁断……なるほど。上着の前と後ろの面と袖を分けて切って……では、ここと袖の部分を糸で繋ぐんですか?」
アイシャ「そう! 察しがいいね」
アイン「ではもし、これをせずに丸ごとの形で服を作ったらどうなりますか?」
アイシャ「動くのが不便になるでしょ? 着るのも脱ぐのも大変だろうし。それは服じゃないね」
アイン「ああ、確かに。『次の服』はその部分も気を遣います」
アイシャ「次の?」
アイン「はは、何でもありません」

レナ「みんな~祝祭の準備はどう?」
アイン「エルフさんも来ましたね。お久しぶりです。共存の祝祭は客もたくさん訪れる日ですか?」
アイシャ「レナお姉さん! 久しぶり! ルーベンには何の用? レナの村にいなくてもいいの?」
レナ「ふふ。うちの村でも祝祭をしてるけど、今日はルーベンに来たくなっちゃったの」
アイシャ「そうなんだ! 皆で一緒に祝祭を楽しも……いたっ!」
レナ「もう、針刺しちゃってるじゃない! 大丈夫? その布……今は祝祭の衣装を作ってるの?」
アイシャ「いてて……そうそう。生地が届いたばかりだから」
レナ「急いでケガしないように気をつけなさい。アインも……あれ? アインは上手ね」
アイン「はは、エルフさんが心配しないように気をつけます」
その時、レイヴンがスタスタと歩いてきた。
レイヴン「レナも来ていたのか」
レナ「うん、今来たばかりよ。ところで……ちょっと……」
盗賊「うううっ……」
レイヴンの後をついてきた盗賊たちが、ボコボコにされて腫れきった顔で大きな袋をドンと地面に置いた。
レナ「その人達は誰? この袋は何なの?」
アイン「ハーフナソードさんが実力を発揮してきたようですね」
レイヴン「祝祭の物資が盗まれたと聞いた時、心当たりがあってな」
エルス「あ、この前オレが行ったとこ? 一人で無理してねぇか? オレも連れてってくれればよかったのに」
レイヴン「大丈夫だ。見ていい気もしないし、こんなことよりも祝祭の準備をしたほうが堅実だ」
アイン(ああ言っているが、ずいぶん見どころはあったと思いますがね)
レナ「レイヴンも今まで祝祭の準備を手伝っていたの?」
レイヴン「ああ。薪を割って、周辺に動物が近寄ってこないように追い出しておいた。でも、追い返しても戻ってくるのがいて上手くいってるかどうかは分からないな」
レナ「あはは。多分ポールとか精霊とかだと思うわ。好奇心旺盛ないたずらっ子たちだもの。
やんちゃな子たちだけど、大した危害は与えないから、きっと火をつければ近寄ってこないと思うわ」
レイヴン「そうか? ならよかった」
レナ「じゃあ……私もなんか手伝おうかな。衣装作りを手伝ってみようかなぁ……うーん……」
レイヴン「……どうして俺達を」
アイン「じっと見ているのですか?」
レナ「ね、二人は祝祭衣装あるの?」
レイヴン「ん? あ……いや。俺は祝祭に参加しないからいい」
アイン「私もいりません。神官ですから。司祭の服は女神に仕える者の服ですので、祝祭にも相応しいのではありませんか?」
レナ「なんの話よ。それは祝祭の衣装じゃないでしょ? これは共存の儀式じゃなくて共存の祝祭なの! はいはい、二人はこっちに来なさい。大きさは目で見て適当に合わせてあげる」
アイシャ「そうそう、二着増えたくらいで全然問題ない!」
アイン「はは……分かりました。分かりましたから押さないでください」
レイヴン「うっ……」
盗賊「和気あいあいな雰囲気になったところで……俺たちはそろそろ帰ってもいいっすか?」
ロウ「帰ったってどうせ飢えるだけだろ? せっかくここまで来たからには仕事を手伝え。罪を犯したら罰を受けるんだ」
エルス「おい、お前ら! ちゃんと手洗いしないと料理には近づけさせねぇ!」
盗賊「ハ、ハイッ!」
アイン(エルを盗むことに加担した者どもなのに付き合えるのか)
アイン(人間のやることは理解できない)
*
本来まだ日が昇っている時間だが、辺りは徐々に暗くなる。太陽と月が重なり、エルが休息に入り、もうすぐ共存の祝祭がはじまるという意味だ。
幸い助っ人が増えたことでルーベン村は無事に祝祭の準備を済ませることができた。
アイン(エルは今まで放出したエルの力を自然から回収し、循環させている間には無防備な状態になってしまう)
アイン(これもまたエルが不安定になってから始まった儀式……エルが完全な状態であればこのような儀式も必要なかったはずだ)
アインが祝祭の衣装を弄りながら考えていると、アイシャが近づいてきた。
アイシャ「服のサイズは合ってるかな?」
アイン「はい。合っています。こんなに短時間で私とハーフナソードさんの服が作れるとは、驚きました」
レイヴン「俺も驚いたな。こんな腕だし、着るの大変だろうと思ったら裾ごと取っちゃうとはな……」
「……くぅー」
レナ「あはは、なんか照れるわね~」
エルス「裾をどうやったんだ?」
アイン「エルフさんが裾と脇の裁縫線の糸をほごした後にハーフナソードさんの体に着せたまま縫いつけたのですよ」
「くぅー」
アイシャ「いいアイディア! すごい!」
アイン「そうですね。でも脱ぐともう着られないので……これは祝祭の時だけ着られる服ですね」
レナ「少し知恵を働かせてみただけよ~。じゃ、準備はこれで終わりね?」
「ぐぅぅぅ……」
レナ「早く祝祭がはじまるといいね。そうだよね?」
「……ぐぅぅぅぅぅぅ……」
レナ「あーもう! さっきから誰なの!? お腹グーグー鳴らしてる人!」
耐えかねたレナの怒鳴りにエルス、アイシャ、レイヴンが視線を逸らした。村の人々はいきなり地面を見つめ、祝祭準備に強制動員された盗賊たちは急に服のしわを手で伸ばし始めた。
アイン「はは。エルフさんが来る前から祝祭の準備で忙しくてご飯を食べる時間がなかったのです」
アイシャ「そ、そうなの。実は私も朝からずっと空腹だし……先にご飯食べようよー」
レナ「え、そうだったの? まぁね、本当に忙しかったんだよね。こうなった以上、少し早めに祝祭を始めちゃおうかな?」
エルス「いいぜ! 共存の祝祭って特別な日だろ? 女神様もオレたちが食事を抜くのは望まねぇよな」
盗賊「そのとーり! そのとーりっす!」
レイヴン「……」
アイン「……はは」
アン「じゃあ、ちょっと早いけど先に食事にしましょう! 秩序を守って並んでください~」
食器が次々と運ばれてくる。美味しい料理の匂いと焚き火の熱気で村が暖かさに包まれる。皆はレイヴンが少しでも気が休まるように、森に近い村の外郭に席を取った。
こうしてルーベン村では少し早い共存の祝祭がはじまった。
*
楽しく笑ってしゃべる声、一緒に踊る音、子どもたちがギャーギャーとはしゃぐ声。
エルの休息で世界が暗い闇に包まれるのを合図に虫の鳴き声がリンリンリンと聞こえてくる。賑やかな中にどこか静かな平穏に包まれた気がした。
あまり食欲を感じないアインはのろのろと自分の分の食事を食べた。ルーベン村に留まっているうちに分かったことがあるからだ。
アイン(急いで食べてお皿を下げたり、食事を欠かせると周りが煩い……)
でんでんむしにも負けないほどの速度で口にスプーンを運びながらアインは祝祭を鑑賞した。
村人「ガッハハ、盗賊やってる割になかなか踊れるじゃねーか!」
盗賊「いっそのこと、盗賊やめて踊り手になっちまおうか?」
ロウ「何でもいいから盗賊は辞めたほうがいいぞ」
アイン(お互い敵だったはずの者たちが、今は肩を組んで一緒に踊っている)
背の小さい子「今年のパイ、めちゃくちゃ美味しい!!」
声の大きい子「またもらってこよー。掌に落ちたクズまで全部舐めて食べつくしてもまだまだ食べてぇ」
背の小さい子「うん!早く行かないと待つ時間長くなるよ!」
(タタタタ!)
アン「ふふ、今回私が作った祝祭の衣装、どうでした~? 前回より上手になったのが目に見えるでしょ~?」
ロウ「確かにそうだな! すごいなと思った。
なにより、森に大きな問題がなくて一安心したな。前回あんな騒ぎがあったから、祝祭の前に何か起こらないかどれだけ心配したか」
アン「森が平穏でよかったです~。あ、そうだ。ハガーさんはどこにいらっしゃるのかしら。お礼を言わないと~」
アイン「……」
エルス「アイン、なにをそんなに考え込んでるんだ? パイは食わねぇの?」
アイン「はい? あ、いや……」
考え事でエルスを止めることに失敗したアインは小さくため息を漏らしながら自分のお皿に追加された一切れのパイを見下ろした。
アイン「それが……盗賊たちと仲良くできるのがおかしいなと思いまして」
エルス「ああ……。まぁ、そんな日だから」
アイン「……そうですか」
アイン(そんな日……そんな日か)
エルに関しては女神が認可したのは全て分かっているアインに、エルの休息は歓迎できることではなかった。エルが暴走することもなく、爆発することもなく、完全な姿だったらこんなことにはならなかった。だからエルの休息は人間がやらかした愚かな仕業の代償に近い。それも知らずに祝祭と呼びながら祝日扱いをしているのも最初は理解できなかった。
アイン「そんな日、ですね」

アインはエルスが言ったことをもう一度思い浮かべてみた。
「エルがどこにあるのか……そんなに重要なことか?」
そして盗賊たちと遊んでいる村人にまた視線を向けた。
アイン(エルは価値判断などはしない)
エルは尊敬される聖者と許されない犯罪者を区別しない。そして、この祝祭ではエルを盗むことに加担した犯罪者の残党が村人に混ざって遊んでいる。
アイン(祝祭が終わったらきっとそれぞれの立場に戻って、今のような関係がいつまでも続くとは言い難いだろうな)
アイン(だが……明確に定義付け出来ないが……エルとルーベン村の人間達の行動が何だか同じように見える。この全ての風景が……)
「ドタドタ!」
エルス「うわあっ! ポール、オマエ! 止まれ!」
アイン「あ……」
考え込んでいるアインのお皿を襲ったポールはパイを盗んで素早く森へと逃げた。アインのお皿は一瞬で綺麗になった。
アイン「エルス! 私は大丈夫です!」
アインはポールを追いかけて森に飛び出していったエルスに向かって叫んだが、すぐフリフリと首を横に振ってその後を追いかけた。
アイン「エルス、そんなに走って行かれると困ります。今日はエルが休む日なので気をつけなければなりません」
やっとエルスに追いついて小言を並べ立てていたアインはふとエルスが見ている方向に視線を向けた。
蛍と精霊たちの力で照らされていてぼんやりとした淡い光の中で一人の少女がポカンと突っ立って空を見上げていた。
イヴ「これが共存の祝祭……まだ日が暮れる時間ではないからおかしいと思った。知ってはいたけど実際に見るのは初めて……」
エルス「イヴ!」
アイン「あなたは……」
エルが呼び寄せた早い夜の風情に夢中になっていたイヴはふと自分が感傷的だったことに気づいたのか顔を赤く染めた。
イヴ「また会えて嬉しい。これは……キミがここに来てほしいと言ったから来たけど……」
エルス「オレたちはあっちの方に集まって休んでる。イヴも来いよ! きっとみんな喜ぶと思うぜ」
アインは何も言わなかったが、なんだかナソード種族に対して以前と違った観点で見られるようになった気がした。
アイン(エルの加護はこのナソードたちにも平等に与えられるに違いないのだから)
アインはそのことについてもう疑問を持たなかった。
エルス「さぁ、イヴ、アイン。帰ろっか? みんなで遊んだ方がもっと楽しいんだぜ」
アイン「はい。帰りましょう」
祝祭の夜は更に深まっていく。
ノア ストーリー 「少年と遺跡探検」
クラモルはノアと一つの約束をした。それは、エリアノドでは次の旅が始まる前に、『いっぱい寝て、休む』ことだけをすること。
ノアは渋々と努力はしてみる、と曖昧に答えた。幸いにも、やれることがあまりなく、その約束は誠実に守られた。
「体は楽だけど、なんだかなぁ……」
「いいじゃないか? 君がくつろいでいて俺は嬉しいよ」
「あ、そう」
「ノア。体力をつけるためには休むことも大事だ。君も知ってるだろ?」
「こんにちは~。はぁ、やっと休める~」
「お疲れ、ユリア。仕事は終わった?」
「一応はね! ずっと忙しかったけど、やっと暇ができたよ。手紙をいーっぱい出しておいたから、返事が来るまでは暇だよ」
「よかったね。休息が必要な人はユリアだよ」
「はは、私は元気だから大丈夫! ところで、ノア君は元気がないね。どうかしたの?」
「仕事中毒のノアさんは休憩があまり嬉しくないみたいだよ」
「え、そうなの? 私もだけど」
「だって、もったいないと思うよ。エリアノドで何か手がかりを探せるんじゃないかと期待してたから。今も教団は活動しているだろうし、今こうしている間にも、また何をやらかしているか分からないから……何でもしなきゃと思ってしまうんだ」
「うーん……確かにそうだね。私もエリアノドに来る前に色々覚悟をしてたよ。私に任されたことも重要なことだけど……。やっぱり、もう少しマスターや巫女様たちの役に立つことがしたいよ。もの知らずが英雄の真似をしたがっていると言われるかもしれないけど……とにかく、今やっていることじゃ物足りない気がするよ」
「ユリアも仕事中毒だな。二人とも歳に似合わず気負い過ぎだと俺は思うよ。……まぁ、俺が平和過ぎる時代を生きた人だから、そう思うのかもしれないけど。それでもさ、そこまで先のことを考えて生きる必要はないと思う」
「……そうね。跳躍するためには体を精一杯縮めるものでしょ? クラモルの言う通り、今がその時期かもしれない。でも、私たちにできることはあると思うよ。ノア、一緒に探検しない?」
「探検……? どこを?」
「実はね、エリアノドを少し調査して分かったんだけど、エルの爆発の衝撃でエリアン王国時代の遺物は殆ど使えなくなっているの。でも、いつも例外はあるでしょ? 爆発直後に封印されたから、よく探してみれば使えるものがあるかもしれない! ベントス様が、市街地の一帯に比較的まともな状態で残っている建物がいくつかあると仰っていたよ。そこに行ってみない?」
「僕たちだけで? 危なくない……? ユリアが行くって言うなら僕も行くけど……」
「俺も行ってみたい」
「クラモルまで? まぁ……分かったよ。大丈夫だろう」
「わぁ! じゃあ、行くことに決定! それじゃ、行く前に詳しい話を聞いてみようよ。位置は大体わかるけど、市街地は道がめちゃくちゃだから、むやみに行くと迷うと思うよ」
「風のマスターの所に行くのか?」
「うん! 風のマスター様はこの一帯に詳しいの」
「うん……確かにね」
(マスターや巫女様たちが消えた風のマスターを探し回るところを何回も見たからね……)
*
「……ああ。だから、エリアノドを探索したい、ということだね?」
「はい。私たちが何かを見つけたら皆さんのお役に立てるかもしれません!」
「偉いね~そういうことなら、手伝うよ。行く道は知ってるかい? 広場の方の崩れた建物の左にある坂道を抜けて、溝に沿って右側に行くと……」
「道が結構難しいですね……」
「そんな所にある建物をどうやって探したのですか……?」
「はは、あの建物は特別なんだ。多分、魔法使いたちが使っていた建物だと思うけど、異様にあの周辺にはモンスターが近寄らない」
「そんなことがあるんですか?」
「ほぉ……? まだ作動している防犯魔法があるのかな? エルの爆発と封印に耐えてまだ作動しているのなら、本当にすごいことだな……」
「いやいや、そんな意味じゃないよ」
「え? じゃあ、どんな意味で……」
「ふふ。あの建物にはね……誰もいないのに夜になると微かな明かりが見えて、人の囁き声が聞こえるんだよ。多分幽霊とかじゃないかな? エルの爆発に巻き込まれて死んだ魂とかさ……」
「えー。そんな、嘘ですよね」
「な、何かいたとしても、モンスターじゃないかな。幽霊なんて……」
「じゃあ……一応、人か、人じゃない何かがいるかもしれないということだね。確認したい。今すぐ行ってみよう」
「ノ……ノア、すごく危険なモンスターがいるかもしれない! これは生半可に判断しちゃいけないことだよ。なぁ、そうだろ?」
「さっきは行きたいって言ってたくせに……」
*
ノアとユリア、そしてクラモルは風のマスターが教えてくれた道を歩いて進んだ。マスター達の努力のお陰か、市街地にはモンスターがほとんどいなかった。しかし、廃墟の荒涼とした風景は不意になにかが出てきそうな雰囲気だったので緊張が走った。
「はぁぁ……おかしいね。来る道はそう険しくなかったのに、どうしてこんなに疲れちゃうのかな。まだ建物の前に来ただけなのに、もう疲れちゃった」
「最近までモンスターが暴れた所だったから、ずっと周りを警戒しながら来たからじゃない」
「ちょっと休んで行かない?」
「うん! せっかくここまで来たのに手ぶらで帰るわけにはいかない!」
ノアとユリアは強張った顔でお互いにしばらく向き合ってからゆっくりと歩きはじめた。わりと綺麗な内部を見たユリアは感心しながらあちこちを見渡した。
「わぁ、中は意外とキレイだね。他のところと違って。家具も元の位置にあるし、物も散らかっていないし……」
「そうだね。他の建物と比べて、壊れた所もほとんどない。隣の建物が衝撃を防いでくれたようだね」
「わぁ! いい予感がするよ! 本当にここで稀代の大発見でもしちゃうんじゃないの? ノア! 早く!」
ユリアはつい数分前で怯えていたとは思えないほど大胆に廃墟を調査した。どうやら恐れよりも探求心が勝ったようだ。

「わぁ、ベントス様が言った通りだね。魔法研究に必要な道具と本がいっぱいあるよ」
「基礎段階と応用段階の魔法書が混じっている。この建物を使っていた魔法使いは何をする人だったんだ?」
「あ、あそこのあれ、見える? エルの塔で見たことがるよ。昔の家具はあんなスタイルだったみたいだね」
「僕も見憶えがあるよ。そういえば、最近はこんなスタイルを見たことがないね。エリアン王国時代に流行ったものかな」
「あっ、あのフラスコに液体が入ってるぞ! 何だろ? 調べてみたいな」
「これだけ時間が経ったら、何であれ触らない方がいいと思うよ」
「ノア、引き出しには何かあったのか?」
「これ? うむ……空だよ。その下も……ここ、予想と違って物はあまりないね。初めて見るものはあるけど、特別なものはないし……」
心配の割に普通だったからか、緊張が解けた二人はあっちこっちを歩き回りながら廃墟を見た。誰かが記したノートのページを捲りながら、ユリアが思わずぽつりと言った。
「ここにいた人たちはどうなったんだろう……」
「……」
「そ、そういえば。ここの黒板と文書に基礎魔法がいっぱい書かれていたな。見た? 建物の大きさを見ると学校には見えないけど、学生を教えるところだったのかもな。最近はどんな風に魔法を学ぶんだ?」
「うーん……私は家族たちに自然に教わってもらったけど。レンダールキャンプには家の人を含めて魔法使いたちが多いよ。だから、魔法を見ることも使うことも、小さい頃から自然なことだったの」
「僕は基礎的な部分だけ学んだよ。兄さんが学ぶのを少し見たことはあるけど、兄さんも学校には通ってなかったし」
「俺が知っていることとちょっと違うな。魔法を学ぶ環境が大分変わったようだ。今の時代では俺の知らない魔法がいっぱいあるかもしれない」
「本当にそうかも」
「ふーん……ここはぜんぶ見たみたいね。残ったのは奥の部屋かなぁ。私はあっちの方に行ってみる。何かあったらここでまた会おうね」
「あっ、ユリア! ああ……行っちゃった。一緒に行けばいいのに……」
「でも、ここに俺たち以外の人はいないようだから、大丈夫だと思う」
「うん……異様に静かだね」
廃墟の調査がなんだか軽い雰囲気になって心配になったが、ノアは首を振った。本当に危険な場所だったら風のマスターがここを教えてくれるはずがないから。
「……あのさ、ノアは怖がらない性格か?」
「ん? なんで?」
「さっき風のマスターが言った時にさ、怖がっているように見えなかったから」
「さぁ……? 別に怖いとは思わなかった。ただ、話を聞いてロッソ家の実験室を思い出して……僕に何かできることがあるかもしれないと思って、来たくなっただけだよ」
「そっか……」
「僕が怖がると思って心配したの? クラモルの方が怖がっていると思うけど」
「フン、そんなことを怖がる歳はとっくに過ぎたよ。そうじゃなくて、君が怖がり屋さんなら、少し問題がある。もし、ここで幽霊とかが出て、怯えた君が驚いて俺から手を離して逃げたりでもしたら……」
「したら……?」
「俺が幽霊の出る廃墟に一人残されてしまうじゃないか! 絶対手を離すなよ、分かったか?」
「はぁ……何を心配してるのかと思ったら……心配するなよ。そんなことしないから」
「だよなぁ。余計な心配だよな? へへ……」
「でもさ、万が一ということもあるから。紐とかあれば、俺のグリップと君の手を結んでおいた方がいいんじゃない?」
「しつこいな……」
「あまり歩かなかったと思ったけど、もう日が暮れてる」
「そうだな。収穫は特になかっただろ?」
「うん。なかった。ただお散歩に出かけた感じだね」
ドアのフレームが抜けて、黄昏がそのまま入ってくる。窓辺に立っていたノアは、急に向こうの部屋からの明るい光を見て一瞬固まってしまった。
「パァァ!」
「な、なんだ? 急にあっちの部屋から光が……!」
「あそこはユリアが行った方向だけど……! 早く行ってみよう!」
突然の光に驚いたノアは急いでユリアが入った方へと走った。部屋の外に走り出てきたユリアとぶつかりそうになった。
「キャッ!!」
「あっ! ユリア、大丈夫? 光を見て心配になって来たよ」
「はぁ、はぁ。ノア君だったのね! びっくりした! 私は大丈夫。他のところを見ていたけど、急にピカッとして窓が開いて……怖くなって思わず逃げてしまったの。後ろが何かうるさかったけど……本当に幽霊がいるかも!」
「ふむ……」
「モンスターかな? ここに長くいたやつなら結構強いかもしれない……僕の後ろに来て」
「うーん……違う。ノア、大丈夫だと思うから入ってみよう」
「大丈夫? なにが?」
「そうよ! いきなりピカッとしてすごい音がしたんだもん! きっとただものじゃないよ!」
「大丈夫だって。俺を信じて入ってみなさい」
その言葉に、ノアとユリアはお互い怯えきった顔を見合わせて視線を交わした。クラモルが嘘を言ってるとは思わなかったが、壁越しに数人が話しているような声が聞こえて、全身に鳥肌が立った。
「ちょっと確認だけして帰ろう……そうしよう」
そろりそろりと歩いて半分開いているドアの隙間を覗いた二人は、目の前の風景に驚いて息を呑んだ。部屋の中は色とりどりの美しい光と、暖かい風に満ちていた。窓は開いているのだが、今部屋の中にある風は外から吹いてくる風ではない。不思議なことに怖くなかった。不吉な感じもしなかった。
「この感じ……なんかちょっと……馴染んでる。どうやら前にこんな所に行ったことがあるような気がする……」
「本当に? どこだった?」
「あの時よりは確実に薄いけど、この安らかな感じ……まるで聖所みたい」
「そう感じて当然だと思うよ。今ここには精霊たちがたくさんいるから」
「精霊たち?」
「ああ、どうやら魔力に釣られてあのランプに集まってきたようだな」
クラモルの話を聞いた二人は部屋の中を見た。精霊の光がぐるぐる回る中で、テーブルの上に動かない光が一つあった。
「精霊が人を避けないね。珍しいことだよ……」
「この精霊たちは弱い。これは推測だけど、エルが爆発した時に巻き込まれたんじゃないかな。おそらく、エリアノドにあるヘニルの力もそうだし、エルの力も安定していないから、形を維持することも上手くできないだろう」
「だからあの小さな光に釣られたのね。あそこから魔力が出ているから……」
ユリアの話を聞いて、ノアもテーブルの上にあるランプを観察した。光りと一緒に漏れてきた魔力の流れが感じられる。
「……なんか切ないね」
ランプに集まる精霊たちを見て、ノアは複雑な気持ちになった。
自分もエルの爆発に巻き込まれたが、事故の直後、意識を失い、遺跡と一緒に封印された。そうでない存在はエルが爆発した後に色んなことが変わったその状況を耐えて生きただろう。人も、精霊も。
「……帰ろうかな。精霊たちが安心して魔力を補充できるように」
「うん。そうしたほうがいいね」
三人は精霊を驚かせないように静かに歩いてドアへと向かう。その時、小さな光がクラモルにそっと触れた。
「あっ……?」
「……」
「……ああ、またな」
「わぁ……精霊たちがクラモルに気づいたの?」
「ああ。俺をエルフじゃなくて、精霊だと思い違いをしているけどな。あの子たちも俺たちを見て不思議に思ったようだ。じゃあ、戻ろうか。急がないとすっかり日が暮れてしまうよ」

エルの塔に戻る道は探検に出た時より短く感じられた。黙々と歩いていたノアが、ふとユリアに声をかけた。
「ユリアはなにか見つけた? 僕は特に何もなかったよ」
「私も。あのランプが少し気になったけど、精霊たちに大切なものだから私が奪っちゃいけないよね~。ふー、最初は魔法使いの研究室と聞いてすごいものがあるんじゃないかなと思ったけど、特に何もなくてしょぼかったね。でも、今は来てよかったと思うよ。特別なものがないというのは、せめてそこにいた人たちは脱出に成功したってことでしょ?」
「そうだね。使えそうなものがなかったのは、そういう意味じゃないかな」
「でしょー? 本当によかった。それより、ほんとに不思議だったよね。あの中の魔力はとっくになくなったはずなのに……どうやって作ったのかな? 夜にだけ点くみたいだから、昼に行ってちょっと確認してみようかな?」
「……ん? ユリアが点けたんじゃなかったのか?」
「私じゃないよ。言ったでしょ? 他のところを調査していたら、突然ピカッとして驚いたって」
「えっ……作動させたことを忘れたんじゃなくて?」
「違うよ。え、何でそう思ってるの?」
「そ、そんなはずがない。魔力は自然に流れるものだよ。それを一ヵ所に溜めておくためには色んなものが必要なんだよ。あんな市販品じゃ無理に決まってるだろ。ユリアもよく考えてみれば分かると思うけど、あれは特別な遺物じゃない」
「じゃあ……誰がランプを点けた?」
「あ、あれ……ベントス様は結構昔からあんな現象が起きたと仰ったよね……」
「クラモル、一回点けたらどれくらい持続するの?」
「さぁ……あの大きさだと……おそらく、2日か3日くら……い?」
「え……じゃあ……少なくとも3日前に誰かが点けておいたってことじゃん! キャーッ!!」
「ユリア、落ちついて! 他の人が来てたかもしれないじゃん! キャンプの人とか……」
「ベントス様が教える前にはこんな場所は知らなかったんだもん! 私たち以外には誰も知らないの!」
「げっ……ノ……ノア! 手離すな! さっき俺が言ったこと、覚えてるよな? な!?」
「ノ、ノア! 走ろう!」
「ユリア! 待って! ……置いて行かないで!」
3人は騒がしくエリアノドに向かって走り出した。遠くからその姿を見ながらベントスが楽しそうに笑っていた。
「いじわる。子ども相手にこんなイタズラしていいの?」
「はは、これくらいはいいじゃない? 今は暗いからちょっと怯えていたけど、少し考えてみれば私の仕業だとすぐに気づくだろうしね」
「フン、でも意地悪すぎよ」
「別に悪いことはしてないだろう? あの子たち、色々複雑に考えすぎだから、すこし気晴らししてあげただけだよ。なんでか知らないけど、子供っていつも早く大人になりたがるんだよね。そんなに急がなくてもなるようになる時代なのにな」
「中途半端に大人になった子供たちには、ちょうどいいくらいの気晴らしになったかもね」
「さぁ、暗くて怪我しちゃうかもしれないから、そろそろついて行こうか」
ラシェ ストーリー「父親を探している少年」
ハーメル作戦指令室。ラシェは先日の失敗した作戦について報告をしていた。自分の顔以上に暗い司令官の顔を見て、自分の責任を痛感しながらもう一度声を出した。
「後退は……当時の兵力では止むを得ない選択でした。だから、この前よりも多い兵力が必要です。もう一度だけ聞いてください!」
ラシェが必死に話しても司令官は反応しなかった。返事はまだ聞いていないが、ラシェは彼の長いため息で既に心が折れてしまった。
「プリンス様。あそこはもう駄目になった場所です。不要なことだとよくご存じだと思いますが、それでもあそこに行きたいと仰るのは……ヘルフォード卿を探したいからでしょうか」
「それは……」
「お気持ちは分かります。ヘルフォード卿はセナスにおいていなくてはならない優秀な司令官です。しかし。そこに残っていた人は全員避難した状態ではありませんか? 不足している兵力を無駄に使うことになるでしょう。ですので、増援は許可できません。ご了承ください」
意表を突く司令官の返事にラシェは返す言葉がなく、黙ったまま指令室を出た。彼の判断はとても理性的で、正しかった。ラシェもそれを十分理解しているのだが、理解していても鬱陶しくなるのは仕方のないことだった。
「こんなことをしている場合じゃない……」
ラシェがここまで焦っているのは、最近ハーメルに広まった噂の影響もあった。ハーメルの守護者、白い巨人と呼ばれるヘルフォード卿が魔気に染まって魔族の手先になったという噂だった。しかも父上が消えた場所で黒い鎧の騎士が目撃された噂まで……ラシェの頭の中は混乱していた。
「黒い鎧の騎士が本当に父上なのか自分の目で確かめたいのに……」
人々を守ることで精一杯なのに。父上を救うために説得することも失敗した。ハーメルを守ることも、父上を救うことも。何一つまともにできなかったと思うと気が重くなった。
「父上ならこんなに悩むこともなかったよね……」
握った拳に力が入っていたことも知らず考え込んでいたラシェは、顔を上げた。何もしなければ結局何も変わらない。今もやもやしているのは自分だ。この状況を打開したいなら自分が動くしかない。
一人でも父上を救うために、黒い鎧の騎士を確かめに行くしかない。
これがラシェが出した結論だった。
*
「ここだ。黒い鎧の騎士が目撃された場所……」
ラシェが訪れた場所は捨てられた居住地域。つい最近まで人が住んでいた場所だが、今は廃墟になった。ほこりまみれになったぬいぐるみだけが村の隅っこに座ってラシェを歓迎してくれた。ぬいぐるみを見つめていたラシェは、突然ゾッとする寒気を感じて驚いて周りを見渡した。すぐ警戒態勢を取ったラシェの周りを囲んだのは魔族たちだった。
「魔族の奴め……! まだ残っていたな! 勝手な真似はさせない!」
ラシェは群がってくる魔族を相手にしながら少しずつ進んだ。重い砲撃音が響くたびに、魔族たちは次々と呻き声をあげながら倒れた。後から襲撃してきた魔族を処理した時、視野に入ったのはラシェが今まで探していた黒い鎧の騎士だった。
「見つけた、黒い鎧の騎士……! もう少し近づかないと!」
「き、騎士様?」
ラシェが急いで近づこうとしたその時、どこからかか細い声がラシェの足を止めた。驚いたラシェが振り向くと、そこには居住民らしく見える人たちがいた。
「騎士様? 騎士様ですよね? 女神様、本当にありがとうございます! 私たちを見捨てなかったのですね! 私たちを救うために来てくださったのですね?」
「こ、ここの住民ですか? 全員避難したと聞きましたが……ここで何をしているのですか?」
「わ、私たちは避難できずにここに閉じ込められていました。魔族の目につかないようずっと隠れていましたが、騎士様を見つけてここに出てきたのです」
「このまま死ぬと思っていたのに……助かりました! やっと家族に会えます! 夢みたいです!」

住民たちの期待に満ちた顔を見たラシェは戸惑っていた。ここでこんな事をしている暇はないのに……早く黒い鎧の騎士に追いつかなければならないのに……。
ラシェは唇を噛み締めた。信号弾を撃てばハーメル守護団が来てくれるんじゃないかな。自分らしくないことを考えていたその瞬間だった。
「う、うあっ! 魔族がまだ残ってる! こっちに来るぞ!」
ラシェたちを発見した魔族たちがドスンドスンと素早い速度で近づいてきた。まだもじもじしているラシェを見て焦る気持ちになった一人の住民が、ラシェの腕を掴んで切羽詰まった声でお願いした。
「騎士様、どうか私たちを見捨てないでください……」
その瞬間、ラシェは冷水を頭からぶっかけられたような気分になった。自分がいかに恥ずかしいことを考えていたのか気づいたラシェは心を引き締めて目をぎゅっと閉めて再び開けた。
「すみません。こんな状況で僕は……後ろに下がっていてください。僕が安全に守ってあげます!」
ラシェはデストロイヤーを握り直した。ガチャッ! ドォォン! 装填音の後に信号弾が空高く打ち上げられ、ラシェの大きい雄叫びが魔族の注意を引いた。
「こっちだ! 魔族ども!!」
地面を蹴って飛びあがったラシェはハーメルの守護団が到着するまで戦い続けた。
*
「単独行動をして……申し訳ございません」
「いいえ、私の失策でした。プリンス様のご活躍で失踪者を助けることができました。一人で長く耐えましたね。本当に素晴らしいです」
激しい戦闘の痕跡が残ったフライトニア姿のまま、ラシェはうつむいた。作戦司令官はとんでもないと首を横に振りながらラシェの功績を讃えたが、ラシェの気持ちは晴れなかった。
指令室を出たラシェは重い足取りで歩いた。
「セイカー家の後継者としてハーメルを守ることよりも重要なことはないのに……自分の目的のために一番重要なことを粗末にしたね。恥ずかしい……」
「そうだね。父上の行方を探すことも重要だけど、自分の果たすべき役目から目を背けるのはあってはならないことだ……」
「……でも、父上を探すことはいつも優先してはいけないことか? 2つの中で選択しなければならない状況になったら、なにを選べばいい?」
「……父上」
*
ハーメルの状況は悪化一路だった。とっくにベルダーにハーメルの状況を伝えて増援を要請したが、港が魔族たちに占領されてだめになったからだ。
「このままでは使節団とベルダー軍は港に着いた途端魔族たちに攻撃されてしまいます」
自分も港の魔族を討伐する作戦に参加したいと言い、ラシェは守護軍と一緒に港へ向かった。港について周りを見渡したラシェはまたうなじが寒気のようにぞわぞわした。
「うっ、この感じ……あれは……魔族たち? 難破船に上がっている……! 追いかけないと」
ラシェは迷わずに魔族たちを追いかけて難破船に上がった。魔族を一掃しようと固く決心して入ったが、真っ先に発見したのは使節団としてハーメルを出た兵士だった。
「大丈夫ですか!? どういうことですか? 他の兵士たちとベルダーの支援軍はどうなりましたか?」
「も、申し訳ございません、プリンス様……! 海上で魔族の襲撃を受けてベルダーに着く前に……」
「ということは……ベルダーの支援軍はいないということですね……。……生存者がいるかもしれませんので、海岸を捜索してみます」
さらに状況は悪くなったが、他の兵士たちまで不安にさせたくなかったラシェは平静を装って兵士たちに指示を出した。
「……魔族の攻撃があるかもしれないと予想はしていましたが、ここまでやられるとは思いませんでした。ベルダーに船を3隻も送ったのに、1隻は攻撃を受けて難破し、残りの2隻は魔族に見つかって回航したなんて……結果的に何もできず……」
「どうやって私たちが船を送り出したのを知ったのでしょう?」
「そりゃ当たり前のことだろ! ハーメルが既に包囲されたからだろう! もう私たちには死ぬ未来しか見えてない!」
ロードロスの厭世的な話に、作戦指令室の雰囲気はさらに沈み込んだ。彼らの表情を見たところ、まだ諦めるには早いと思っているのはラシェだけのようだった。
暗い雰囲気の中で報告が終わり、建物から出たラシェはぶつぶつ言いながら自分の横について出てきたロードロスを見つけて近づいていった。
「あの……ロードロス様。二人きりで話したいことがあるのですが」
「う、うん? なんだ?」
「今回は僕がベルダーに行きたいです。船を出してもらえないでしょうか」
「なっ……また使節を? ははは。もう使節団なんて無用じゃないか? また攻撃されるはずだ。今も兵力をたくさん失った状況だというのに……」
「いいえ。今回は人員を最小限にして……一人でベルダーに行きたいです。今すぐに」
「い、今? 今すぐ?」
「あの広い海を、しかも魔族が全ての海路を把握しているわけでもないのに、どうやって追撃できたと思いますか? 疑いたくはありませんが……使節団を送ったことを魔族に通達した者がいるようです」
「じ。じょ、情報が? いや、だ、誰がそんなことをしているんだ!」
「あくまでも推測です。もしこれが本当だとしたら、使節のことを知っている人間は少なければ少ないほどよいでしょう。だから、僕一人でベルダーに向かいたいです」
「ああ……そう言うことなら……分かった。船を出そう」
「ありがとうございます、ロードロス様。では、行ってきます」
*
「そろそろベルダー海域に入るんだね。うっ、またこの感じ……あっ、あれは……!」
「クアアアアア!」
「魔族たちがここまで追いかけてきた……! 本当に情報が漏れたんじゃなくて海上まで魔族の領域になってしまったのか!? ここまで来た以上……戻ることは出来ない!」
心を決めたラシェは船を襲ってくる魔族の群れに向かって雄叫びを上げながらデストロイヤーを向けた。船は引き続きベルダーへと進んで行く。
ドーン!!
「くっ……はぁ、はぁ……!」
ラシェがなんとかベルダーに上陸したのは明け方だった。疲れ果てたラシェを追いかけてきた魔族の残党たちはそんなラシェの状態を知っていても油断していなかった。
「下がってください! ここは危ないです!」
夜明けの騒ぎに惹かれて赤い服を来た人間が近づいてくるのを見て、ラシェは叫んだ。
しかし、赤い服の騎士は逃げるどころか、剣を抜いて魔族を倒し始めた。
「はぁ、はぁ……! あ、ありがとうございます。息抜きする暇もなく戦い続けて力尽きるところでした……実力者ですね……!」
「深刻な状況だと思って先に剣を抜いたけど、大丈夫? 怪我はないか?」
「僕は大丈夫です。それより今重要な要件が……! 僕はセナス公国の首都、ハーメルから来た使節です。セナスが魔族の侵攻を受けていますのでベルダーの支援が必要です。これをベルダーに伝えるために来ました……!」
「そんな、そんな酷い状況だったのか……。大変だったな。もう大丈夫だ。フェネンシオ、ベルダー王国にこの話を伝えよう。兵士一人を王国に送って、半数はこの少年と一緒にハーメルに派遣するぞ」
「かしこまりました。ハーメルには行かれませんか?」
「あたしは確認したいことがあってさ。後でついて行く」
「はい……あっ!?」
(ドサッ)
「やれやれ……倒れちゃった。ようやく安心したようだな」
「とても疲れた様子でしたね……ご安心ください。兵士たちと一緒に安全にハーメルに連れて行きます」
「ああ、頼んだぞ」
*
「幸いハーメルまで魔族とぶつかることなく着きましたね」
「はい、本当に幸運でしたね」
(まだ疑問は残ったままだけど……余計に話して雰囲気を悪くする必要はないだろう)
「あ、あそこを見ろ! プリンス様が戻ったぞ! ベルダーの支援軍と一緒だ! しかもあの赤い服は……まさか赤い騎士団か?」
「な、何だと!? 支援軍が来ただと!?」
「赤い騎士団だって、夢じゃないんだ? やっと安心できそうだな!」
「ハーメルが危ないと聞いて来ました。赤い騎士団の副騎士団、フェネンシオです。状況が状況ですのですぐ作戦に入らせて頂きます」
「予想以上に……悪い状況ですね」
地図を見ながらセナスの状況を伝え聞いていたフェネンシオが暗い声でつぶやいた。その反応を予想していたのか、作戦室の皆は沈黙した。
(おかしい。戦術には問題がない。指揮官は最善の、常識的な選択をした。しかしこれは……敵はまるで全部見透かしているように反撃してきた。ここの地理にも詳しいようだな……)
「悪い状況になったのは知っていますが……なんとか魔族を防御する方法はないでしょうか?」
「まず、セナス公国のほとんどの地域が魔族に占拠された状況ですので、避難民を収容して安全地帯を確保するためには近い地域を奪還しなければなりません。奪還作戦は我々赤い騎士団が中心になって行動します」
「そ、そんなことをこんなに簡単に決めていいのか?」
「はい。首都のハーメルは最優先的に守らなければならない所ですし、避難民が多いため治安の問題もあるでしょう。それに、赤い騎士団は元々傭兵騎士団で、指揮体系や戦術は正規軍とは少し違います」
「ああ……そ、そっか。そうだな……それは仕方ない……」
「僕にも手伝わせてください。セイカー家の後継者として、何もせず黙って見ていることは出来ません」
「分かりました。ハーメル周辺を奪還目標地域と宣布して、一つずつ確保することにしましょう。時間がありませんので、すぐ作戦に入りましょう」
「はい!」
*
ラシェと赤い騎士団はすぐに魔族を倒しながら前進した。
「地図を見ても難しいですね。ここの地形に慣れてないので……」
「先ほど一次奪還することになった区域は正確にはどこでしょうか? そろそろだと思いますが、道が違うようです」
「それが……あそこ……でした」
水に沈んだ地をしばらく見てラシェが答えた。フェネンシオは驚いてラシェを見た。
「本当ですか? 魔族がこの区域を全部沈ませたのですか?」
「そうではなくて、水位が上がって沈んでしまいました。」
「つい最近まで人が住んでいた場所じゃありませんか? どうしてこんなことが……。いくら魔族たちが強くても、地形を変えることは無理ではありませんか? こうなる前に異常はありませんでしたか?」
「いいえ、魔族の襲撃で建物が崩れることは多かったですが、それとは別に関係はなさそうです……地盤が落ち込んだりといった異常は特になかったと聞いています」
「それでは……水のエルがこの現象に関係しているのではありませんか?」
「水のエルに問題があるということでしょうか?」
「特に前触れもなく突如居住区域が沈むのは、かなり疑わしいことだと思います。神殿に行ってみるのはどうですか?」
「そうですね。確かに……では、神殿に行ってみましょう。神殿までの道は僕が案内いたします!」
赤い騎士団を水の神殿に案内したラシェは違和感を覚えた。
「これは……!」
「これは変ですね。水の神殿は涼しいと聞きましたが、ここまで凍りつくのは……」
「異常です! しかも、既に魔族が入り込んでいたなんて……神殿を守る兵士たちがいたはずなのにどうやってここまで入ってきたんだ……」
「祭司長と水の巫女を探さなければなりませんね。それと水のエルも確認しましょう」
「神殿の入り口はこちらです。あっ……! あれは……あの魔族は……! 祭司長です!」
「魔族に精神を支配されて意識がないようです。来ます!」
「クルルルル……!!」
ガチャン! ドーン!!
「大丈夫ですか!」
「はぁ、はぁ……! くっ、この程度の負傷は大丈夫です……!」
「うう……っ、プ、リンス様……」
「祭司長様! 気が付きましたか? どういうことですか! 魔族に襲われたのですか?」
「ま、魔族たちが……昔閉鎖した洞窟から突然襲ってきました……」
「そんな! どうして魔族たちがあの洞窟を知っているのですか……」
「その奇襲を受けて兵士たちは……何もできずにやられてしまいました。水の巫女……シャシャ様は魔族に攫われて、水のエルも奪われてしまいました……。私も……魔族に捕まってしまいましたが……最後の力を振り絞って印章だけは何とか守れました……」
「印章……? なんですか、それは?」
「ゴホッ、クッ……」
祭司長は震える手で懐から青い印章を取り出してラシェに差し出した。ラシェはとっさに印章を受け取った。
「私は……ここまでです。プリンス様……。これが水の……印章。この印章は……ハーメルを導く資格のある者に……与えられる……べき……」
「さ、祭司長様! しっかりしてください!」
「どうか……シャシャ様を……」

祭司長はその続きは言えずに倒れて息絶えてしまった。神殿の中に苦しい寂寞として空気が流れた。
「……これからどうするおつもりですか?」
「……ハーメルに戻りましょう。水のエルと巫女様が神殿にいないなら、行く必要もありませんので……」
「……そういうことがあって、水の印章を回収してきました。話を最後まで聞くことはできませんでしたが、ハーメルの指導者に与えられるものらしいです」
「ああ……そうか? そういえばそんなものがあったような気がするな……俺の物に間違いない! 無くしてしまったのかと思っていたら~祭司長が預かっていたようだな! 感謝するぞ! その印章は俺が預かるから今日はこれで休め!」
「……はい……。ありがとうございます」
*
「ふむ……。水害の規模はどれぐらいになりそうですか?」
「初めてのことですのでよく分かりませんが……水のエルは強力ですのでこのままでは他の区域にも被害が出そうです」
「そうですか……不幸中の幸いとしては、魔族の攻勢が弱くなったところでしょうか。我々が討伐した魔族の数が多かったおかげでしょう」
「避難民たちに物資を支給することはどうなりましたか?」
「救援物資は臨時配給所を設置して区域別に時間を分けて配給しています。配給量は十分ではありませんが、追加支援を要請しておきましたのでしばらくは問題ないでしょう」
「そうですか……本当にありがとうございます。大変助かりました」
「大変です! レシアム外郭地域に……!」
「うん? なんだ?」
「レシアム外郭地域に黒い鎧の騎士が現れて兵士たちを攻撃していますっ! 被害が大きい状態です!」
「はい? 黒い鎧の騎士が……! フェネンシオ様。僕が行きます!」
「ダメです。前回の戦闘で負った傷もまだ治ってない状態で……危険です!」
「お願いします、僕に行かせてください。黒い鎧の騎士に確認したいことがあります!」
「いけません。単独行動は被害を大きくするだけです。レシアムから近い空気を巡回している騎士隊員を呼びますので彼らと一緒に……」
「待てません……! 黒い鎧の騎士がまた姿を消してしまうかもしれません! 先に行きます! 後で合流してください!」
止める暇もなく、ラシェは堰を切って出た。
バーン!! ドーン!!
「……」
「くっ……はぁ、はぁ……!」
黒い鎧の騎士を発見した場所はレシアム外郭から遠くない所だった。黒い鎧の騎士はラシェを発見したとたん、迷わず攻撃をしてきた。
(やっぱりこの人、父上と同じ技を使ってくる……!)
「もしかして父上ですか? 父上を探してここまで来ました!」
「……」
黒い鎧の騎士はラシェの声が消えていないのか、武器を振るうことだけに没頭している。感情的にも、体力的にも限界に迫っているラシェは劣勢に立たされた。
「うっ……! だめだ……! 僕は……確認しなくちゃ……」
「させるかー!」
ドーン!
「赤い騎士……また……?」
「おい、大丈夫か? オレの手を掴めるか? もう安心していいぞ! オレたちが助けてやるぜ!」
赤い服を着た少年はラシェを後に下がらせて群がってくる魔族と黒い鎧の騎士を仲間たちと一緒に倒していく。敵の数が増えて、黒い鎧の騎士は後退した。ラシェは荒い息を吐きながらそれを見ているだけだった。
(僕と同じ年頃に見えるけど、ベルダーで見たあの人と似たような感じだね……ベルダーの追加支援軍かな……?)
(うっ、まただ……うなじに変な感覚が……)
緊張が解かれ、今まで精神力で抑えていた激痛が走ってラシェはその場で倒れてしまった。ラシェは倒れる直前にぼんやりとした目で赤い服を着ている少年と彼の仲間たちを見つめた。あっという間に魔族を退治した彼らはラシェを囲むように群がってきた。
「気絶してみたいね。連れて帰ろう」
遠くなる意識の中で、ラシェは思った。
(ベルダーの支援軍が、そしてこの人たちが助けてくれれば……父上も、セナスも助けられるかもね。戦況が変わりそう……)
彼との出会いは長い旅の始まりであることを、またその長い旅の中で頼れる仲間になる人との初めての出会いであることを、この時のラシェはまだ知らなかった。
エド ストーリー 「少年のオントロジー」
『デブリアンの薬学は、人生をよりよくし、苦痛を軽減してくれる点で錬金術師のポーションと対して変わらない。それでも否定的な認識が広がっているのはナソード戦争当時、兵士たちに使用された薬物が招いた結果のせいだろう。しかし、これは因果関係を考える必要がある。戦争のために投与許可基準を高めた部分……そして兵士を対象として行われたナソード移植が十分な検証もできず短期間に無分別に行われたことが根本的な原因である。したがって、これに対する認識を改善するためには薬物の定量投与と地道な努力を……』
「……」
エドは渋々研究書を閉じた。母親の研究が完成できたならきっと多くの人の役に立ったはずだ。
無意味な仮定だ。エドは適当に資料をまとめてそこから立ち去った。
「…………」
ペイター一帯で起こった事件は次第に収束していく様子だ。ナソードの女王、イヴを追ってエル捜索隊の目を避けて適当に身を隠していたエドは、エル捜索隊の次の行き先を把握した後で一足先にベルダーへ向かった。首都にはナソードとデブリアンに関する情報があるだろう。ウォーリーがやったことから考えてみると、自分がデブリアンであることに気づく人間はほとんどいないようだった。
(だが、行動に気をつけねぇとな)
この時代で必要なのは、情報と過去に戻るための手掛かりだけ。他はどうでもいいことだらけだ。そんな風に考えながら足を急かしていたエドは、ペイター地域を出たとたん、尋常でないことが起きたことに気づいた。
「何だ、どうしてここに魔族たちが……ペイターからここまで来たか? いや、数が多すぎる」
エドは自分にかかってくる魔族を屠り、首都から駆けてきた兵士を止めて問い詰めた。
「そこのオマエ。これはどういう状況だ?」
休まずに駆けてきたため汚い格好で自分の体もろくに支えられない兵士は、エドの質問に辛うじて口を開いた。
「そ、それが、首都に化け物が! 私も詳しくは……」
「……化け物が首都に現れた?」
エドは目を細めた。そういえば、ペイターを出る前に、首都に送った救援要請の返事が遅れていると聞いた。そしてこの兵士は武装もろくにできず一人でペイターまで走ってきた。
「遅れているんじゃなくて来れなかったのか」
「わ、私はこれをペイターに知らせて応援を緊急要請するつもりでしたが……化け物が……!」
「オレ様が来た道を辿って行け。そこには敵がいねぇからペイターまで無事に抜けられるだろ。ベルダーの状況を伝えろ」
「はいっ! あの……ほ、本当にありがとうございました。命を助けてくださったことも、こうして手伝ってくださったことも……」
「礼なんかいらねぇからとっとと行け! どこでまた魔族に追いつかれても知らねぇぞ」
「魔族……ですか? あ、はい、それでは……!」
青二才の兵士は魔族が何かも分かっていないようでしばらく間抜けな顔をしていたが、すぐに下手な敬礼をして足早に消えた。
*
ついにベルダー近郊についた。悲鳴を上げながら首都の外へ脱出する人々で周りは阿鼻叫喚だった。エドは状況をすぐに理解した。王城の方角を見ると昼の青空を陰鬱な煙が覆っていた。今はまだ小さな点のように見えるが、首都の中央がこんな様子なら既に……。
「ハッ!」
呆れ笑いがおのずと出た。燃える街、崩れ落ちる壁、暗い空と耳いっぱいに入る人々の悲鳴……自分には馴染んだ風景だった。
「どうやらオレ様は滅亡の日を選んで来るヤツのようだ」
それでもエドはベルダーに入ってみることにした。自分が狙っているのは資料だけだ。図書館のような場所はまだ残っているかもしれない。
王国の統制が消えた今、近郊の駐屯兵たちは混乱に陥った人々を落ち着かせるだけで精一杯のようで、エドは邪魔されずすんなりとベルダーに入ることができた。避難している人々は逆に首都に入るエドを見て驚き、そして正気か? と言うような顔でエドを見たが、それだけだった。
(理性を失って逃げるざまか。こんな状況だから仕方ないが見てらんねぇな)
冷たい目で彼らを後にして着いた村は、遠くから見た以上にみっともなかった。ベルダーの内部は避難する人で溢れていた。状況をざっと把握したエドはベルダーに大股で歩いて入った。今回も逃げている人々は不思議そうに目を大きく開けてエドにちらちらと視線をやった。
「なんだァ……」
人々のちらつく視線に続いてエドの不快感を一層引き上げたのは、勝手にエドの腕を掴んだ誰かの手だった。
「ほら、どこ行くのよ!」
「うっ、んだよ!」
「中に家族とか友達がいるの? 誰を探しに行くのか知らないけど、あそこは危ないわよ!」
「……チッ」
エドは眉をひそめた。誰に危ないって言ってんだよ。自分の命を心配しなきゃならねぇ状況で余計なお世話を……。
「……離せ! オレ様は弱くねぇから構わねぇ」
「あっ、待ちなさい……!」
博愛溢れる住民は腕を振り払ったエドをもう一度掴もうとしたが、エドは大股で人込みの中に消えた。
エドの目的はベルダー図書館。300年は決して短くない時間だ。しかも自分が生きた時間帯で父親から習った知識はナソードの知識だった。
(無限の図書館でナソードルーラーに関する地域は全て習得したが、そこにもない情報があった。300年の空白を埋める知識が必要だ)
*
エドは相変わらず速いスピードで移動しながらベルダーの惨状を目に留めた。倒れた兵士たちの上に真っ黒な灰が雪のように積もった。
「いくらなんでも首都の兵士たちがこんなあっさりとやられるとはな。情けねぇ」
その時、兵士たちが魔族の軍隊と交戦しているのがエドの目についた。
「ほぉ、アイツらはなかなかやるな。……ん?」
猛攻に振り回されていた魔族たちが懐からガラスの瓶を取り出した。その中の液体を飲み干した魔族はすぐ血管がバキバキに浮き出て体温が急上昇し、筋肉が小刻みに震えた。
「うわあああっ!」
恐るべき力の格差に兵士たちは押され、すぐ戦列が崩れてしまった。これを見たエドは眉をひそめた。
「ドーピングか、クックッ。ずいぶんと汚い手口使うんだな」
薬学には詳しくないが、服用してすぐ効力が出て飛躍的に身体を強化できる薬なら……身体に大きな負荷が掛かるはずだ。
「命を削って戦うもんだ。愚かだな……」
エドは通り過ぎようとしたが、屋根の上に少し留まっていた。真紅の空、濃い煙の中で兵士たちは近郊の方へと隊形を維持しながら少しずつ後退している。
「よく訓練された兵士だ。すぐにでも背を向けて逃げたいだろうにな」
そんなことをすれば敵の武器が背中に刺されるだろう。しかし、後退するだけではこの事態を解決できない。
その時、一人の兵士の動きが目についた。兵士は仲間たちに目で合図を送ったあと、後ろについていた兵士と魔族たちに飛びかかった。一人は剣、一人は魔法。二人の攻撃は致命的な攻撃ではなかったが、魔族の注意を分散させるには十分だった。これは……。
「他の奴らが退却できるようにわざと?」
「三段切り! はーっ!!」
「うおおお!! 喰らえ、ファイアウォール!!」
二人の兵士はギャアギャア声を上げながら攻撃し続けた。滑稽な光景だったが、妙に笑えなかった。二人の顔が緊張と切実さ、そして疲労に染められていたからだ。
エドはその光景が気に入らなかった。あの二人のお陰で兵士たちは生き残れるだろうか? そんなことはないだろう。近郊まで逃げる前に他の魔族と出くわしてしまったら、この中で一番実力者に見えるあの二人の空白で全滅するかもしれない。
「遅れる奴らには残念な話だが、それを甘受して退却した方が現在としては生存確率が高いはずだ。……チッ」
顔をしかめて屋根の下を見下ろしていたエドはドライヴで魔族の軍隊を急襲した。
「クアアアッ!」
「はぁ……はぁ……ど、どこから飛んできた攻撃だ……!?」
「時間がない、俺たちもさっさと合流しようぜ!」
急に倒れた魔族たちを見て混乱していた二人の兵士は座り込んで息を切らしていたが、すぐに息を整え、急いで先に逃げた仲間たちの後を追った。
「フン、全員生存することを期待したのか? 笑わせるな」
目を細めてそれを見ていたエドは彼らを後にした。エドもやるべきことがあった。
*
図書館を探すのは難しくなかった。大体そんなものは接近しやすいところにあって、大量の本の重さに耐えられるようになっているからだ。怪しいポーションを飲んでしつこく飛びかかってくる魔族を相手にするのが少し厄介だった。それだけだ。
母上の研究書の中にあったデブリアンの薬学に関する内容が頭から離れないせいで、エドは訳もなく彼らに対して冷酷になった時もあった。
やがて図書館に辿り着いた時、エドの隣の建物の火が図書館に移るのを見た。エドはチッと舌打ちした。
「急がねぇと全部燃えちまいそうだな」
デブリアンに関する本は……禁書扱いにされるだろうし、一番奥か秘密の場所に保管されているだろうな。あれこれ計画を立てながら図書館に入ったエドは、意外にもまだ避難していない人を発見して凍りついてしまった。出口から背を向けて立っている白髪の老人がエドの気配を感じて首だけ少しエドの方へ向けて声をかけてきた。
「何じゃ」
「……それはこっちのセリフだ。逃げずに何をしている。火が燃え移ってるぞ? 見えねぇのかよ」

白髪の老人はふむ、と呑気にまた図書館の方に首を向けた。
「見えるのかい」
「はぁ……」
瞬間、エドは言葉を失ってただ立っていた。長い静寂が流れた。老人はそれ以上口を開くことも動くこともなさそうで、エドが先に言い出した。
「オマエは誰だ? 中に他の人もいるのか?」
「この図書館の司書長じゃ。他のみんなは避難しておる」
「そっちは?」
「最後くらいは見届けてあげんとな」
「図書館の最後を?」
「息子の最後を」
ぶっきらぼうに言っていたエドは老人の真剣な態度を見て老人の顔色を伺いながら話し続けた。
「まさか、中に人がいるのを遠回しに言ったわけではないようだが……」
「で、何を探しに来た?」
老人がエドの話を切って本題を言い出した。エドは目を細めて老人を見定めるようにしばらく見つめていた。この老人に目的を言ってもいいのだろうか。と少し悩んだが結局エドは口を開いた。
「……デブリアンに関する本を探しにきた。もう手遅れのようだがな」
「C-900番。エル、08」
「……なに?」
「それと、C-901、902、903……一列に並んでいるから全部持ってきてもいい。それから……」
老人はいきなり訳の分からないことを言った。
「待て、なんだその変なコードは?」
「本を探しに来た奴が、索引番号も分からぬか?」
老人は手を上げて第一書庫の隅を指した。
「まだあそこまでは火が移っていない。急げば間に合いそうじゃのう。この老いぼれよりはお前のほうが早いじゃろう」
「……オレ様に持って来いと?」
老人は第三書庫という立札が掛けられた所に歩いた。そこはまだ火がついておらず、少しばかりの煙が霧のように覆われていた。
「デブリアン、か……それはわしが探してやろう」
老人はそれだけ言い残して遠ざかる。カツ、カツ、と靴の音が次第に遠ざかっていく。
「……取引か? 言葉足りねぇよ。……C-901から順に……」
エドは頭を何度か掻いて老人が教えたコードを独り言で繰り返しながら第一書庫に向かった。
*
エドはかなり長い時間彷徨った末にやっと本を見つけ出した。900番代の本は一番奥の隅にあった。本棚の片隅まで燃え移ってきた火と煙をみて口汚く罵った後にやっと老人が言っていた本を見つけた。
「くっ、くっそ重いな、これ」
老人が教えた本は4冊それぞれ人差し指くらいの厚さの本だった。表紙には『王国の歴史』と書かれていた。
「こんだからオレ様に持って来いって言ったんだ。くっそ、こんなもんだったらカートでも貸してくれよ!」
もちろん苦情は言っているだけだった。ますます大きくなる火とあちこちから落ちた物、人が急いで避難した痕跡で床はカートが通れなくなったから。
エドは4冊の本を抱えた。重さも重さだが、かさも相当だったから手に負えなかった。胸で支えた本がエドの鼻の下で揺れた。下の視野が本で遮られて、足元を見ながら歩くのは無理だ。エドはぶつぶつ言いながらゆっくりと第一書庫の外へのそのそ歩いた。Cセクションが終わるところまで来て足を止めた。この先で何があったのか、大量の本と椅子などが散らかっていたからだ。抱えている本が落ちないよう気をつけながら恐る恐る足を踏み出していたエドは馴染んだ単語が過ぎて行くのを目にした。
「あれは……」
馴染んでいる程度しか認識できない短い瞬間だったからエドは自分の視線が届いた所をもう一度確認した。一つ一つ目を通した後に、本棚の一番下の隅にある『深層分析:デブリアン』という本を見つけた。
「なんだよ。あんな本があるなら教えろよ」
エドはカニのように横這いで本棚に近づいていって本を取り出そうと必死になった。
バサバサ!
特にその本棚にはぎっしりと本が詰められていて、抱えていた本を全部おろしてからやっと取り出すことができた。
「なんで遅いのじゃ」
「遅れて当然だろ!?」
エドはブツブツ言いながら不安定に本を床に下ろした。司書長はエドが持ってきた本を見て、一番上にある『深層分析:デブリアン』を手に取った。
「これを持ってきて遅れたか」
「ああ、何の本があるか詳しく知ってるならこんな本があるって言えよ」
「言わなかった理由があるとは思わぬか? この本は誤謬が多すぎるのじゃ。デブリアンの基本的な定義から間違っている。こんな本を信頼して参考にできるか?」
「基本的な定義?」
「デブリアンを種族だと誤解している人が多いものじゃ。この本も同じ。デブリアンは集団を指す、実際に人間だけでなく、いろいろな種族のデブリアンたちが存在したのじゃ」
「ほぉ、随分と詳しく知っているな」
「司書という職業はそういうものじゃ。知識を広く浅く接するが、数十年の歳月を経てある程度深くなる分野があるもの」
ページを捲っていた司書長は音を立てて本を閉じ、自分の後ろにある机に置いた。司書長の説明を聞いたらわざわざ持ってきたのにもう本を読む気にならなかった。
エドは司書長に聞いた。
「デブリアンのことをどう思ってる?」
「質問の幅が広すぎるのぅ。もっと絞ってみろ」
「……デブリアンが犯罪集団と知られている件についてどう考えている?」
「既に消えた集団のことについて議論して何の意味がある?」
「それにしてはよく知ってるじゃねぇか。デブリアンに関するあらゆる本が禁書と指定されている王国で本の誤謬を指摘できるほどの知識も持ってる……なら、きっと考えがあるはずだ」
「一時、気になって調べたことがあるのじゃ。若い時は禁忌やら闇の歴史やらに惹かれるもんじゃからの」
司書長は隣の椅子を持ってきて座る間、口を閉じていた。エドは大人しく彼の話を待っていた。
「あんな風に死蔵される叡智じゃないのじゃが、残念なことじゃ。しかし、彼らには排斥されるそれなりの理由があったのは理解できる……くらいか」
「……排斥されるだけの理由があっただと?」
エドは眉間のしわを深く寄せた。
「あんな集団は世間から忌まわしく思われやすいものじゃ」
老いた司書長はふくらはぎを揉んだ。低い姿勢だったからエドと目が合うことはなかったが、彼の話は続いた。
「他人より一歩先を行くと優秀だと言う。二歩先だと天才。四、五歩先になると歴史に刻まれる偉人になるのじゃ。じゃが、それ以上……十歩先だと凡人が理解できる範囲を超えてしまう。そして、人間というものは理解できないことを本能的に恐れるようつくられておるのじゃ」
「優秀すぎて、むしろ恐怖の対象となった?」
「先立つものを必ずしも優秀とは言えぬ。彼らがしたこと、そしてその集団特有の閉鎖的な性向も否定的な認識に影響を与えたはずじゃからな。時代に合わせて歩もうとする努力が足りなかったと理解すればよい」
司書長は両足を揉み終わってから腰を伸ばして天井を見上げた。
「魔法使いとデブリアンの差はそこにあるとわしは思っておるのじゃ。デブリアンの理想は時代に合わなさすぎたのう。魔法使いたちが過去の遺産を探して現代に通用する価値のあるものを探求している間、エルの爆発という稀代の災難で途絶えた魔法の命脈と認識は自然と当代の人々に受け継がれたのじゃが、デブリアンの知識はそれができんかった」
エドは反抗心が湧いてきた。その必要もないし、そうしない方がいいと知っていても、エドは彼の意見に反論した。
「その閉鎖性もまた知識を保護するためだったはずだが?」
「そのつもりだったのじゃろうが、むしろ孤立する結果になったではないか」

司書長は第二書庫を見た。隣の建物から始まった火が燃え移り、第二書庫から少しずつ飲み込んでいた。火と煙で赤く、白くなっていく書庫を見ながらエドはなぜか壁暖炉を思い出した。
「もうすぐ全てが終わる」
司書長は椅子から立ち上がった。
「デブリアンが滅んで当然とは言っておらぬ。要するに、時代と歩調を合わせなければ時代から背を向けられることもあるということじゃ」
「……それはデブリアンに限った話じゃねぇだろ」
「そうじゃ。しかし、世の中の成り行きは大体同じもんじゃないかい?」
「ほれ、君が探しておったデブリアンの情報が入った本じゃ」
司書長は机の上に置いていた一冊の本を取り出してエドに差し出した。つられて本を受け取ったエドは表紙のタイトルを読んだ。
「『人類をめちゃくちゃにした最悪の発明品たち』……何だこりゃ!?」
「デブリアンの発明品は120ページくらいから出てくるのじゃ」
「それを言ってるんじゃねー! もっとまともな情報を探してるんだ!」
「禁書じゃ。君が探している本は王城の秘密書庫みたいな場所にあるじゃろう。この図書館にある本の中で一番事実的で客観的にデブリアンの歴史を書いているのはこの本しかない」
司書長はエドが選んできた本の中の1冊を選んで渡した。『エリアン王国没落史』と書かれた古くてボロボロの本だった。
「これも役に立つじゃろう。デブリアンの誕生はエリアン王国の歴史と密接な関係があるのじゃ。何であれ根本を知ることは大事じゃ」
エドは気に入らなかったが大人しく本を受け取って司書長が荷造りをするのを待っていた。司書長はエドが苦労して持ってきた分厚い本を痩せ細っている片腕だけで軽く持ち上げた。
「……は?」
「君が苦労してやっと持ち上げた本をわしが軽く持ち上げて驚いたようじゃの。本も赤ちゃんのように楽に抱く方法があるもんじゃ」
「チッ、分かったよ。終わったら行くぞ」
*
エドは先に歩いてベルダー近郊へ行く道を開けた。時折魔族と交戦しながらエドはあの司書長がどこまで知っているだろうか、自分が操っている力を見て見抜いたのかが気になったが、司書長は黙々とエドの後ろからついてくるだけだった。そうやって二人は近郊の外に出てから何も言わず離れた。
(時代の流れに歩調を合わせねぇと時代から背を向けられてしまう、か……)
(……)
「ここの人じゃないようだが、首都によく出入りしているようだな。何か探しているのか?」
いつの間にか楽器を持っている遊び人のように見える者が、魔族を倒して息抜きしているエドに近づいてきていた。こっちの奴らはお節介な奴らが多いな、と心の中でつぶやいた。
「そんなもんなんかねぇ。あの魔族の奴らが目障りだからやっつけているだけだ。クックッ」
「あー、助けには感謝するぞ。敵が多すぎて人では多ければ多いほどいい」
「フン、別にお前らのためにやってることじゃねぇんだよ。ほら、受け取れ」
「ん? これは何の薬瓶だ?」
「魔族の奴らが使っている。これを飲んだ奴らは怪しいほど強くなるぞ。ホアキンだとか何だとかの奴から持ってきたもんだ」
男は驚いて目を見開いて液体が入った薬瓶とエドを交互に見た。
「ああ~なるほどな。で、どうやってこんなことが分かったんだ?」
「ま、興味があって掘ってみただけだ、と言っておくか。詳しくは知らねぇから錬金術師に聞いてみろ。あのしゃべる犬にさ」
「ああ、すぐ確認してみよう」
男は大きい声で他の人を呼び集めて薬物の調査を指示した。エドはアルテラから追跡してきたナソード女王の信号をしばらく確認した。捕捉した信号は徐々に遠ざかっていたが、エドには彼らの次の目的地が分かった。
「ククッ、ハーメルか……まぁ、遠回りはしたが結局収穫はあった」
船が必要だな。ベルダーの奴らに情報の対価として要求することにするか。エドは口角を吊り上げた。海の向こうにはまたどんなことが待っているだろうな……。
港へ向かうエドは、躊躇なく前に進んだ。
ロゼ ストーリー「災いを防ぐための旅路」
いつもと変わらない平和なルーベン村の空が一瞬パッと光り、一人の人間と一体の謎の機械が地面に落ちた。
次元を超えて、着地に成功したロゼとゼロは周りを見渡した。
「んぐぐ……大変だったな! でも、今回はちゃんと着いたぜ!」
「ここがエリオス! よかったわ。今回も変なところだったらどうしようかと心配していました」
「安心するのはまだ早いぜ。ここは普通な田舎村っぽいな。大いなる災いの機嫌はここから遠いかもしれない」
「私が最初に落ちた所は機械と森がありましたね。あれは一体どこだったのでしょうか?」
「さぁ? 最初はクラウド博士がそれなりの理由があってあそこに送ったんだと思ったけどな。結局跳ね返されてまたエリオスに戻ってきたのを見れば、ただのヘマだったんじゃねーか」
「そうなのかしら……あ、あそこに村人たちがいますね」
「……ということがあって、他の村も物騒な雰囲気らしいです。そこもエルと関係がある事件でしょうかね~? 私達もルーベンのエルが盗まれたことがあるじゃないですか」
「確かに……うちの村はエルスがエルの欠片を取り戻してくれたが、またそんなことが起こらんとも限らんのう……。そういえばあいつらはどうしておるかの?」
「ロゼ、今の話聞いたか? エルが盗まれたことがあったようだな。これがオレたちが探していた手掛かりかもしれないぜ! ルーベンのエルはエルの欠片の中でも特別だという情報があったぜ! この事件が最初に現れた大いなる災いの兆しかもな」
「そうですか? では考える必要もありませんね。詳しい話を聞いてみましょう」
「失礼。今の話を詳しく聞かせてもらえませんか?」
「あっ! だ、誰ですか?」
「あ……驚かせてすみません。不審な者ではありませんわ。私が住んでいる所に災いが襲ってきて、その解決策を探してここまで来たのです。先ほどの話が解決の糸口になるかもしれないので、お話を聞かせてもらいたいですわ」
「災い……? 最近は世の中物騒な話が多いんじゃな。詳しく知っているわけではないが、この村で起きたことくらいなら話ができる。この村にあったエルの欠片が盗まれたんじゃが、エルスという子が仲間たちと追跡して取り戻したことがあったのじゃ」
「エルス……そうですか。その後には問題ありませんでしたか?」
「それからは特に問題はありません~」
「ルーベンのエルを取り戻してきて、すぐ村から出たということは……」
「なにか大きい事件があったかもしれませんね。お話、ありがとうございます」
*
村の人たちが教えてくれた道を進んで、ロゼとゼロはエルダー村に辿り着いた。静かな森の村であるルーベンと違って、エルダーは人が多くて賑やかな村だった。
「はぁ、はぁ……ここにきて何かが変わったのか、それとも環境が違うからなのか。長く走ってもないのに疲れちゃうわ」
「短期間に適応するためには、その分体を動かすしかねぇ。ロゼ、特訓だー!」
「ふぅ……ここはルーベン村より繁盛しているようですわ。どこの誰に聞けば情報が得られるか……」
「オレの話を聞いてるのか……?」
「……」
バチッ!
「わあっ! いてぇな! 何だ!?」
「お……ナソードだ。エコの目に狂いはない」
「このだるい目のガキは何だ!? オレはナソードじゃねぇんだよ! 皇都最高の……!」
「興味深い……ウォーリー領主が逃げる前に作ったものよりレベルが高い……分解してみたい」
「領主が逃げた……? あの、詳しい話を聞かせてくれませんか?」
「うーん……領主が盗賊団と組んで……ルーベンのエルを盗んで、禁じられた機械技術に手を出した。でももう大丈夫。ウォーリーは騒ぎを起こして……自分が作ったナソードに乗って逃げた」
「禁じられた機械技術……ナソードと呼ばれているのね」
「うん。エコは禁じられても別に気にしていないけど」
「ルーベンのエルを盗んだのがこの村の領主だったということは、エルスという人もこの村に来たのかしら?」
「うん、会ったよ。彼らがウォーリーを追い出してくれてやっと村が静かになった……。盗賊はまだいるから全て解決されたわけではないけど……」
「ウォーリーはどこへ行きましたか?」
「ウォーリーはベスマ峡谷に逃げた。それからの行方は分からないみたい。エコも詳しくは分かんない」
「領主が消えて色々大変でしょう……話を聞かせてくれてありがとうございます」
「別に……ウォーリーはもともと城に閉じこもって何もしてなかった。かなり前から村の商人の自治会が代わりに働いている。むしろ、ウォーリーがいなくなって、前より仕事がうまくいってるような気がする……。ちょうどエルスたちが厄介者の領主を処理してくれたお陰で……皆が力を合わせてよりいい村を作るために頑張ってる」
「ルーベンで起きた事件がここで繋がるんだな。次はベスマか? 峡谷……ずいぶん迷いそうだな」
「地形まではゼロのデータにないだろうし、かなり時間がかかりそうですね。ゼロ、皇都に現状を伝えましょう」
「してるぞ。してるけどな……繋がらねぇ」
「はい? 天界と通信できない状況なの? いつまた皇宮に怪物が現れるか分からないのに!」
「一時的な問題かもしれねぇ! ずっとやってるから……時間をくれ」
「そんな……皇女様……私は一体どうすれば……」
*
ロゼとゼロは不安な気持ちに蓋をして、まずは峡谷を越えてベスマ村に行ってみることにした。村が見えてきてもロゼの顔は心配で曇っていた。それを放っておけなかったゼロは彼女を慰めようとした。
「おいロゼ、そう心配するなよ。一時的な問題かもしれねーぞ。通信が繋がり次第、皇女様の状況を教えてやるから元気出せ」
「はぁ……はい。不安を抱えているだけじゃ、何事も上手くいきませんね。頑張ります」
「ああ。まだ始まったばっかりだし、ここでくじけちゃダメだ。ほら、あそこの人が何か知ってるかもしれねぇから行ってみるぞ」
「失礼します。もし、ベスマ村の方でしょうか? 逃げたエルダーの領主に関して何か知りませんか?」
「冒険者か? 私はベスマの保安官、ステラだ。ウォーリーの奴ならとっくに村を出ている。エル捜索隊にボコボコにされて逃げてしまったぞ。奴の行方はむしろ私の方から聴きたい。鉱山を無断で採掘した罪を問わなければならないのにな」
「エル捜索隊? もしかして、その捜索隊のリーダーの名前は『エルス』ではないでしょうか?」
「リーダーかどうかは分からないが、一番前に立ってる奴の名前なら、それで合ってる」
「またエルス……よく聞きますわ。その名前、エルを探しているほかに、別の任務も遂行しているのでしょうか」
「ふーん……そいつがオレたちが追っている全ての事件の中心人物かもしれないな。もしかしたら、大いなる災いの原因だったりとか?」
「それはまだ分かりませんね。ステラ様、そのエル捜索隊に関して何か知りませんか? 私は彼らに会いに来たのです」
「よく知っているわけではないが、世話にはなったな。彼らがリザードマンとの紛争を解決してくれた」
「エルと関係のある事件じゃなくて? どんなことでしたか?」
「いつからだろうか。リザードマン部族が攻撃してきて殺伐とした雰囲気になったな。もしも友好条約が破棄されてしまったら戦争になると心配する者も多かった。調べてみたら、それを企んだやつはカヤックというリザードマンのシャーマンだったよ。奴が死霊術でリザードマンを操っていたんだ」
「し、死霊術!? では、エル捜索隊がその死霊術師を討伐したのですか?」
「一応、そうだね」
「一応?」
「逃げてしまったんだ。奴に従う間抜けどもが襲撃してきたせいで。あんたたちもこの村に来るときに見ただろうけど、ベスマ峡谷は自然が作った逃げ道のようで、隠れられてしまえばだれも探せない。でも、また奴がうようよすることはないはずだ。ベスマで出くわす全ての人が敵になるだろうからな」
「完全に解決できたわけではありませんが……それでも村の平和を取り戻せてよかったですね。その後、エル捜索隊はどうなりましたか?」
「ウォーリーを追いかけて飛行艇に乗って、どこか行っちゃった。あれは見事だったな。行き先に関してはトマに聞いた方がいい」
「そうですか。ありがとうございます」
「あ、待て。最近この村に寄ってきてたな。ペイターからベスマに支援要請が届いたけど、あの時はカヤックの追従者の問題で手を焼いていたからな」
「最近だと? 急げば会えそうだな。どうする?」
その質問に答えようとしたロゼは、口をつぐんだ。
自分は天界に発生した異変の原因を探るために知らない世界に来た。そして、その異変の始まりであると推測されるエルが盗まれた事件と強くかかわっている人の後を追ってここまで来た。すなわち、この質問は遠回りをするのか、近道に行くのかの問題になる。もちろん近道の方が正しい選択だ。天界と通信ができない今、早く任務を解決して帰ることが優先だ。
「ペイターへ……」
しかし、皇女様の命令は大いなる災いの原因を探ること。任務を早く解決して復帰することは皇女様の命令ではなく、ロゼの希望にすぎない。
「……エル捜索隊が本当に異変と関係がある人物達なら、彼らを逃してはいけません。逆に言えば、彼らが本当に重要人物だったら、逃してはいけないターゲットになります。この世界についてもっと調べなければなりませんね」
ロゼは悩んだ末に決定した。
「度々失礼します。トマという方はどちらに?」
*
ロゼとゼロは浮遊島、アルテラへ向かった。飛空艇に乗った瞬間、驚きで感嘆の声を漏らしたロゼは、アルテラ島の機械を見てさらに驚いた。エルダーの錬金術師がゼロを見ても驚かなかったこともあったし、ナソードのことも知っていた。だから、この世界にもある程度光学技術があるだろうと予想していたが、実際のナソードはロゼの想像を超えていた。驚くべき火力、外見は多少洗練されていないが、高度なコードで構成されている上に、精密な機動性を持っていた。
ロゼはナソードを相手にしながら時折分析を行った。島の中心部であるコアに辿り着くまで、二人は揃って「ここにきて正解だった」と何回も言い合った。
「ふぅ、ついにアルテラコアに辿り着きましたね」
「本当にな。浮遊島に着いた時から機械技術に目が奪われちまって時間を使いすぎたな! この世界にこれほどの機械技術があるとは思わなかったぜ。特にエルエネルギー抽出機には感心したな。まさに効率の極みとしか言えない」
「はい! 本当に感心しましたわ。ここの技術を私たちの任務に使えたら、きっと役に立つと思います」
盛り上がってナソードの技術力に関して話し合っていたロゼは話を中断して周りを見渡した。行き止まりだった。
「それより、このメイン動力室は……空っぽですね。なんか残っているだろうと思ったのですが。ここに一体何があったんでしょう」
「ふむ……アルテラコアのセキュリティシステムを確認してみるか。時間が無いから全部のデータを確認するのはさすがに無理だけど、最近のデータだけ見れば十分だろ」
(ジジ……チッ)
『……ナソードの生存と繁栄のためだけならば……今の規模の兵力は必要ない……』
『私が無理にエルの欠片を集め……大規模なナソード軍団をつくった理由は、エリオス全体を脅かす存在を感知したからだ……。伝説としてしか伝わっていなかった魔の世界…魔界の存在である魔族』
「魔族……?」
『何故かこの地は魔界と深く繋がっている……そして、長い時間をかけてその影響を受けてきている。エルの大爆発以降…その動きが本格化し出し……現在、エリオスのあちこちに魔界に繋がる通路がつくられ、大々的な侵略の準備が行われている。このままエリオスが魔族の手によって破壊されてしまえば……ナソードの生存と繁栄に意味がなくなる……』
『ナソード最後の生存者よ……判断はお前に任せる……イヴ。……あとは……た……の……んだ』
映像はそこで終わった。

「……エル捜索隊はこの事件の後にルーベン村に戻って、またペイターに向かったのでしょう」
「エルが盗まれた事件を追って、世界を脅かす新しい危険と出くわしたということか……。さっきからずっと話していたことだが、すぐにペイターに行かなくて正解だったな」
「エリオス全体を脅かす魔界……問題はエルではない。もしかすればこれが大いなる災いの兆しかもしれません」
「知ってしまった以上、無駄にする時間はないぜ!」
「そうですね。ゼロ、早くペイターに行きましょう」
*
ロゼとゼロがペイターに着いた時には、すでに災いが過ぎ去った後だった。キングナソードの予測は間違っていなかった。兵舎は負傷兵でいっぱいだったが、治療は遅れているようだった。重症でない兵士は周辺の村へ移送されたが、それでも負傷兵の数は尋常ではなかった。
神殿の周囲に防御魔法をかけている魔法使いたちも疲れ切って速度を全然出せていない。魔力が底を尽き、めまいを感じている魔法使いたちが壁に寄りかかかって座り込んで呼吸を整えていた。
「思った以上に深刻な状況だな……まさか、エル捜索隊たちも巻き込まれたのか?」
「とりあえず助けましょう。魔法のことは分かりませんが、応急処置くらいなら手伝えますわ」
ロゼは衛生兵を助けて負傷者たちを治療した。衛生兵が不足していて負傷兵を診ている人は大体周辺の村の治療師だったため、ロゼは彼らの指示を受けて水を沸かしたり、救護品を運んだり、包帯を巻いて傷を消毒したりした。
「はぁ、はぁ……ありがとうございます。私はただ疲れているだけですので、気にしないでください。初めて見る顔ですね……冒険者様ですか? 手伝ってくださってありがとうございます。私はアレグロと申します」
「ロゼと申します。ご迷惑でなければここの状況をお聞きしたいのですが」
「どうぞ。お答えできることならば……」
「まず……ここはいつも暗いのですか? どうしてこんなに暗い所に神殿があるのですか?」
「……他の大陸から来られた方ですね。ペイター地域は昔から魔気が強い場所だと知られています。その力を抑えるためにエルの巫女がここに神殿を建設しました」
ロゼは、ゼロが後ろからそれくらいは分かってると不満げに言っているのを軽く無視した。情報を得る時には単刀直入な質問より、話しやすい内容で切り出した方がいい。実際、アレグロという魔法使いは、ペイターのことを知らない他の大陸からきた冒険家が負傷兵の治療を手伝ったことに関心している様子だった。
「……そして、つい最近魔界の存在たちが神殿の最上層に次元門を作って侵攻してきました。幸い防ぐことができました」
「よかったですね。なのに、どうして撤収しないのですか? ここは負傷兵を治療するには色々いい環境ではないと思いますが」
アレグロがふりふりと首を横に振った。
「まだ終わっていません。神殿最上階の次元門は閉じましたが、神殿の中に魔族が残っていないか確認が必要だし、濃くなった魔気に反応したのか、黒い森に魔物が現れ始めました。村に被害が出ないよう対処しなければなりません」
「そんな……負傷兵が安心して休むこともできないなんて……深刻な兵力不足ですね」
ロゼはペイターの状況を聞いてとても残念な気持ちになった。ペイターの駐屯兵が次元門を閉じることに成功し、神殿に残って籠城している魔族も多数討伐した後にもかかわらず、一部の兵力は首都を支援するために送られたと言う。大きい戦闘が終わったばかりなのに無理して兵力を送ったことから見ると、首都であるベルダーも深刻な状況だろう。
「もう一つ質問してもいいですか? 次元門を閉じるのを手伝ったという冒険者たちは無事にベルダーに向かいましたか?」
「はい。エル捜索隊の皆様がいなければペイターは魔力に占領されていたでしょう。ロゼ様はエル捜索隊を探してペイターに来たのでしたね。忙しい所を手伝ってくださって、ありがとうございました。よろしければ近道を教えますよ」
「あ、大丈夫ですわ、それは後でお願いします。まだやり残したことがあります」
ロゼは懐から銃を取り出した。
「それで……魔族は神殿のどのあたりに?」
ロゼとゼロはペイター神殿に残った魔族の討伐を手伝った。エル捜索隊とペイターの駐屯軍が活躍したおかげでロゼは彼らより少ない魔族を相手にしただろうが……。それでも油断できない敵だった。魔気に反応してさらに強くなったという黒い森のモンスターはペイター駐屯軍に任せて、二人はベルダー王国首都に辿り着いた。
「うっ……これは……」
首都はペイターより更に絶望的な雰囲気だった。大きい森の境界にあって、駐屯軍がいたペイターと違って、首都は一般市民たちの被害を受けたからだ。魔族は退治されていたが、これからの生活が大変になった人々の挫折と悲しみは聞かなくてもしみじみと伝わってきた。
ロゼは燃えている首都を見ながら苦しげに言った。
「……ベルダーの戦闘は終わったみたいですね」
「だな、幸いと言える状況じゃないけど……」
ロゼは何人かのベルダーの兵士に聞いてエル捜索隊が向かっている方向を突き止めた。彼らはベルダー港から他の大陸に行ったようだ。首都がこのように大きい被害を受けても、彼らは立ち止まることができないようだ。
「……この王国はどうなるのかしら」
首都を横切って港に向かっている間、ロゼとゼロはあまり話さなかった。話をする気分ではなかったから。長い時間交わした言葉は「そこ地面に気をつけろ。外側が崩れて破片が多いぞ」と「ありがとうございます」くらいだった。ロゼは崩れた城壁をぐるりと回って通り過ぎた。かつて孤高な姿で王城を守っていたはずの壁は、今は通行の邪魔になる危険な障害物になった。
「これは……外側に崩れていますね」
魔族たちはどうやってベルダーに侵攻してきたのだろう。エル捜索隊の後を追いながら、多くの人にベルダーで起こったことに関して聞いた。最近の事だったので人々の証言は大体一致した。一つだけを除いて。
魔族たちがどこから侵入してきたのかという質問には人それぞれ考えが違った。
(この王国はこれからどうなるのかしら。私が大いなる災いの兆しを防ぐことに失敗したら、次は天界でここと同じ光景を見ることになるかもしれない)
ロゼは不安を収めて足を速めた。
*
船はセナス領の外れに停泊した。ハーメルの船着き場に停泊する予定だったが、船着き場の被害復旧と交通統制のためにこれ以上は進めないと船長は説明した。
ロゼとゼロは無理してハーメルに入る必要はないと判断し、船を降りて少し調査を行った。調査の末、ベルダーから来た冒険者たちは砂漠の村、サンディールに向かったことが分かった。
「ハーメルはベルダーよりいい雰囲気でした。皆勝利に喜んでいるように見えました」
「つい最近に魔族が退治されたようだからな。もうすぐエル捜索隊に追いつけそうな気がするぞ。今は嬉しいだろうが、被害規模を把握しはじめたら、セナスもベルダー王国のように勝利の喜びは消えて、目の前の悲劇に集中してしまうだろうな」
「そうですね……でも、彼らは大海の台風と並みが生涯の敵ですもの。強い方々ですから、乗り越えられます。私はそう思っています」
ロゼは砂漠の砂を防いでくれる暴風服と食糧を手に入れた後、青い海を後にして金色の砂海がうねる砂漠へと向かった。
(ゴォォォ)
「うっ、ゼロ。目の前が全然見えませんわ。一体どういうことなの!」
「うあっ、砂が入ってきた! 中がめちゃくちゃになったぜ……! ロゼ、オレのデータによると、これがあの有名なサンディールの砂嵐だ! だからあの変なアンコウなんて無視しようって言ったじゃねぇか!」
「先にしつこくかかってきたのはアンコウの方ですわ! ケホ! ケホ! 砂嵐でも何でも、いつか収まるでしょう。皇都守備軍の名誉にかけて、なんとか突破して見せますわ!」
『そこに……は、いけません』
「!? ゼロ、今の声、聞きましたか?」
『……あ! 私の声が届い……すね!』
「突然頭の中で声が響いているわ……あなたは誰ですか?」
『詳しく説明する時間はありません。私の声について……い。この砂嵐を抜けられる道を教えてあげます。どうか遅れな……予言が……たらあなたにも……』
(予言? 私にも?)
「分かりました。あなたを信じます。道を教えてください」
『…………』
(ビュオオオ……ゴゴゴゴ……)
「……やっと風がやんだぞ! ウオォ! 抜け出してきたぜ!」
「はぁ……はぁ……本当に大変でしたわ。嵐を抜ければ声の主と会えると思いましたが……誰もいませんね。あれは一体誰だったんでしょう?」
「オレも知らねえ。とにかく、生きて出られてよかったぜ。あ! あそこを見ろ! あれはサンディール村に間違いねぇな。ロゼ! 砂嵐にまた巻き込まれる前に早く村に入ろうぜ!」
「おう? 旅人か? 君たち、どうやってこの砂嵐を潜り抜けてきたんだ? 砂嵐の日は砂漠アンコウのせいで、村の外に出られる奴も入れる奴もいないのにな……あの嵐を潜り抜けてきた人間は初めて見たYO! チェケラ!」
「それを知っていたらオレたちも風が止んでから来たぜ。誰かさんが行こうと意地張ったせいだ!」
「実は、どういうことかよく分かりませんが、砂嵐に巻き込まれた時に、ある少女の声が私を導いてくれました。その声についてきたら、この村に着いたのです」
「少女の声だと? 君たちは本当に運がいいな! そいつは風の巫女の加護に違いないYO!」
「風の巫女?」
「うむ……そういうことか! 風の属性のエルを管理する巫女らしいな」
「ああ、今はラノックス村の村長の連絡を受けてあっちに行ってるけどYO、用が済んだらすぐ帰ると思うYO」
「待てる時間はありませんね。何のことでラノックスから連絡を受けたのかご存知でしょうか?」
「詳しいことは分からないが、巫女の全員が集まる重要な会談があるらしいな」
「エリオスでエルはとても重要なものだぜ。エルを管理する巫女たちの役目の重要性は言うまでもねぇ。そんな彼女たちが全員集まる会談なら、きっと相当重要なことだろうな」
「会談……その会談というのは、予言と関係あるのでしょうか?」
「そうだ、どうしてそれを知ってるんだ?」
「やっぱりそうでしたね……風の巫女はあの時砂嵐から私を助けながら何か重要なことを伝えようとしました。よく聞こえませんでしたが……遅れてはいけないと……それから、『予言、あなたにも……』と言っていました」
「『あなたにも』だと? ロゼの他にも誰かがその予言に関わっているような言い方だな」
「ええ、私もそう考えています。おそらく私たちが追っている人たちでしょう。もうすぐ会えそうですね」
*
ラノックス村長の家の前。ロゼは大きく深呼吸してドアを開けた。
「失礼します。エルの巫女様でしょうか?」
「あれ? 悪いけど、今は重要な話をしているから入ってくるのは困るね」
「あ! イグニア様、待ってください。私の客です! はじめまして、あの時、砂嵐の中で迷っていたお方ですね?」
「はい! ロゼと申します。あなたがあの声の主ですね。あの時はお世話になりました。おかげ様で無事にここまで来られましたわ」
「えへへ~。お役に立てて何よりです!」
「あなたは……? 失礼ですが、どこから何をするためにここにいらっしゃったのかお聞きしてもよろしいでしょうか」
大地の巫女、アルテアは少し硬い表情になったが、すぐに優しい顔で質問した。一瞬の表情を見たロゼは、巫女たちの前では嘘を言う必要はないと判断した。
「オレたちは北部帝国から来た冒険家だ。目的は――」
「改めて紹介します。私はロゼ、エリオスではない他の世界から来た者です」
「おいっ!? ロゼ! それを言ったら……!」
「大丈夫ですわ」
ロゼは落ちついた表情で巫女の前に立った。少し緊張した顔で自分に注目した巫女たちを見ながら、自分の目的について話し始めた。
「私は、私が住む世界に訪れる悲劇を防ぐためにここに来ました。大いなる災いの根源がここ、エリオスにあると聞きましたわ」
「ん? 大いなる災い? エリオスが原因で?」
「エリオスが原因かどうかは分かりません。しかし、関係があるのは確かです。危険にさらされるのは天界だけではないかもしれませんわ。そういうわけで、私たちはエリオス各地を調査しながらエル捜索隊という人たちの足跡を追ってきました。お願いします。私たちの世界を救う方法を探すのを手伝ってください」
「ああ……」
巫女たちはお互いを見つめて少し沈黙した後うなずいた。
「実は……私たちがここで会談をしているのは、なにか肝心なことを見逃しているような妙な予感がしたからです」
「予感……ですか?」
「ただの気のせいじゃねーの?」
「普通なら気のせいと思って深く考えないでしょうけど、巫女の全員が同じ予感がしたのは、なにか根拠のあることだと思います」
「エル捜索隊の痕跡を追ってきましたと言いましたよね。どうでしたか? 彼らをどう思っていますか?」
「……最初は正義感あふれる冒険者だと思いました。盗まれたエルを取り戻してきて、助けが必要な人々を見て見ないふりをせずに助ける……そんな善良な人たちだと。しかし、彼らがずっと大きな事件に巻き込まれるのを見ると、少し疑っていました。もしかしたら、彼らが大いなる災いを招きこむ存在ではないのかと思ったことがありました」
「でも、今はそうは思いません。彼らは強い運命に導かれているのだと思います。危険にさらされているのは天界だけではないかもしれません。エリオスを襲ってきた危険を防ぎながら進む旅をする彼らの背中を追いながら、彼らなら大いなる災いを防ぐ鍵を見つけることができるという確信が生じました」
「……そうですか。私もそう思っています。私たちはロゼ様がおっしゃいました大いなる災いに関しては分かりません。しかし、エル捜索隊は昔から伝わってきた予言の人です。きっと、女神さまの按排だと思います」
巫女たちはロゼの話を信じてくれた。そして、エル捜索隊がいるところまで送る方法を考えた。しかし、いい方法は見つからなかった。
「実は……また予言を発動できるかどうかは分かりません。何もできないのがいっそう幸いで……ロゼ様を変なところに送ってしまうかもしれません」
「それはもう二度と経験したくありませんね……他の方法はありませんか?」
「おい……ロゼ。オレたちはその方法を知ってるかもしれねーぞ」
「……はい?」
「ハハハ。正確には『オレたち』じゃなくて『オレ』がな! 覚えてるか? エリオスに来る前に間違って行った次元があっただろ?」
「間違って……あ! 機械がいっぱいあった森のことですか。まさか。それはただの偶然とかミスではなかったかもしれない、ということですか?」
「ああ! オレは運命なんか信じないけど、それでも試してみる価値はあると思うぜ。どうする?」
「試してみましょうよ! 皆様をお助けします」
*
遥かな残骸、エリアンの遺跡。
「こんな所に遺跡があったなんて……」
「ふぅ……。では、始めます」
「……1番目の祈りは風。神の元へと導く音なき翼」
「2番目の祈りは海。光の中で眠る傷も存在もない夜の揺りかご」
「3番目の祈りは砂。黄金色の時間の中を彷徨う旅人。」
「4番目の祈りは歌。月への願いと夜空に輝く静かな囁き。」
「5番目の祈りは黄昏。輝き燃えるたった一つの命に辿り着く場所。」
「最後の祈りは約束。太初と遠い未来の名前、明日を開くたった一つの道。」
(パァァ!)
巫女たちが祈りを捧げると、足元からゆっくりと強い光の柱が上がった。ロゼは慎重な顔で光の柱に行く準備を済ませた。
「柱の中にお入りください! 光が皆様をエルの巫女がいる場所へ導くでしょう!」
「座標の設定も完了したぜ。ロゼ、警戒を怠るなよ!」
「どうかご無事で! きっと風が、ロゼ様の向かう場所へと導いてくれるはずです!」
「ありがとうございます。では!」

「うう……成功したかな? これを二回もやるとはね。結構疲れるのよ、これ」
「そうですね。予言をこんなに頻繁にしてもいいのでしょうか……」
「別の世界に迫ってきた危険、エリオスを侵略した魔界、そして、次の次元に繋がる予言……」
「……偶然というには、あまりに運命的なことだと思います。これから、エリオスに何が起こるのでしょうか」
「それは分からない。でも、彼らはきっととんでもないことをやってくれるよ」
「……どうでしょうか? 先ほどの方は無事に辿り着けたでしょうか」
「あの方たちもエルの導きを受けていらっしゃるのなら、無事に辿り着けると思います……私はそう信じています!」
「どうか……皆無事にまた会えますように……」